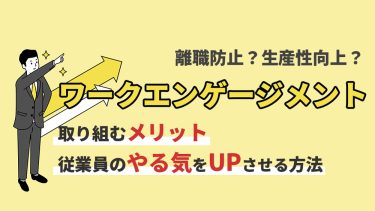社員同士の結束を高めたり、業績アップを後押ししたりするチームビルディングについてご存じでしょうか?
今回は、チームビルディングの概要や効果・メリット、導入方法などを解説します。
チームビルディングとは

チームビルディングとは、直訳すると「チームを作る」という意味となります。
社員それぞれの個性や保有スキル、強みを最大限に引き出しながら、目標達成できる強いチームを作ることや施策そのもの(ワークや研修)をチームビルディングと言います。
チームビルディングの対象層
チームビルディングは、新入社員や若手社員のみを対象にしているわけではありません。目標、業績達成のためのチームに関わる社員全員が、チームビルディングの対象者となります。
チームビルディングの施策や研修を行う際に、あえて階層別に実施することもありますが、基本的には役員や社長も含めた全社員が対象者です。
チームワークとの違い
チームビルディングと似た言葉にチームワークがありますが、両者は意味や目的が全く異なります。
チームワークは、同じワーク(業務)を複数名でこなす際に、チームを構成する社員同士で協力をすることを指します。チームワークという言葉を使うときは、特定のワーク(業務)を行うためにメンバーが集められます。ワークを達成することを目的として集まっているため、課題の解決手法や手順、全体像がある程度予測つくのがポイントです。
一方、チームビルディングは、特定のワークをもとにチームが構成されるわけではありません。特定のワークやタスクの達成が目標になっておらず、抽象的な「企業理念」や、より大きな「会社の業績アップ」といった目的を目指すためにチームビルディングを行います。
チームビルディングで達成する目的は大小さまざまであることや、必ずしも数値目標を達成することだけがミッションにならない点が、チームワークと異なります。
チームビルディングでは、個々のスキルや個性を引き出して、最大限に付加価値を高めていくことに注力しているのです。
チームビルディングを行う目的
チームビルディングは、1人では成しえない大きなビジョンや業績目標、社会貢献といった広い視野でのミッションをチームで達成するために、チームに付加価値をつけていくことが目的となります。
また、個々の強みを理解した適切な人事配置や、キャリア制度の構築、経営理念の浸透などもチームビルディングの付随目的と言えるでしょう。
チームビルディングのメリット・効果
チームビルディングのメリットや、導入効果について見ていきましょう。
相互理解が深まる
チームビルディングを実施すれば、社員同士の理解が深まるメリットがあります。
チームビルディングは、小さなタスク達成を目標としておらず、あくまでも1人ひとりの能力を引き出す点がポイントです。1人ひとりの考え方、価値観の違いや強み・弱みの把握をチームビルディングで進めることで、相互理解が深まり、コミュニケーションが強化されます。
生産性の向上
チームビルディングは、生産性の向上に寄与するのもメリットです。チームビルディングを行うことで相互理解が深まり、心理的安全性が高まることで、社員が失敗を恐れずチャレンジできる風土が生まれます。多くのチャレンジを生み出せば、今まで達成し得なかった目標に到達することが期待できるでしょう。
また、社内コミュニケーションが活性化することで、日ごろのケアレスミスを削減したり、業務効率化を目指せたりもするため、結果として生産性向上ができるのです。
チームビルディングの5段階プロセスとは

チームビルディングを行う手法に、タックマンモデルという5段階プロセスの概念があります。心理学者、ブルース・W・タックマンが提唱した5段階プロセスの流れを簡単にご紹介します。
1.形成期
形成期では、その名の通りチームビルディングに加わるメンバーを決め、チームの土台を形成します。チームメンバーはお互いを深く知らず、発言の際も心理的安全性が低いためためらいが多く、不安や緊張感が漂います。
リーダーが適切な誘導をしながら、量を重視したコミュニケーションを継続するのが重要です。
2.混乱期
混乱期では、徐々にお互いの意見の違いや価値観の違いから、対立が生まれていきます。チーム内でヒエラルキーが生まれてしまったり、「私だったらこうする」と、個人の主張が強くなったりするなど、メンバー同士の食い違いが多発する時期です。
混乱期ではコミュニケーションの質に目を向けて、対話重視のチームビルディングを行います。
3.統一期
統一期では、ようやくチームメンバー個々の性格や個性が理解され、チーム目的やビジョンが明確に共有され出します。
それぞれがチーム内での自分の役割を理解し、建設的な議論が生まれます。
4.機能期
機能期はもっともチームのパフォーマンスが上がる時期となります。
統一期で得た結束を、より強固にしていきながら、外に向かって大きなエネルギーを発揮するようになります。リーダーは、個々のメンバーの強みが活かされるようサポートに徹することが求められ、業務外でのラフな交流機会も設定していくと良い時期と言われます。
5.散会期
ある程度のミッション、目的を成し遂げたタイミングで、一部のメンバーはより高みを目指して退職・異動する時期です。時間的な制約から解放され、チームそのものが解体となり、それぞれが新たなミッションに向けて動き出す準備をします。
チームビルディングを行う際は、この5段階のプロセスを意識しながら運用していくと良いでしょう。
チームビルディングを行う時の注意点
コミュニケーションを活性化し、大きな成果を生み出すチームビルディングですが、導入時にどういった注意点があるか確認しておきましょう。
価値観や目標を強制しない
チームビルディングはトップダウンで行うと失敗する可能性が高いです。チームに与える目標を押し付けたり、仕事の価値観やあるべき姿などを強制することは避けましょう。
チームビルディングでは、個々が自分の役割を認識し、自発的に動けるようになることが理想です。
チームビルディングリーダーの重要性と役割
チームビルディングでリーダーに課されている役割は非常に重要です。一般的にリーダーや、リーダーシップというと「チームを牽引していく強いリーダーシップ」が想像されやすいです。しかし、チームビルディングにおいては、強いリーダーよりも、メンバーのコミュニケーションを導いていく力が重要視されます。
具体的には、チームメンバーの相互理解のため、または信頼関係の構築のために、コミュニケーション機会を提供するのが役割となります。機会提供の際は、それぞれが発言しやすいよう場づくりをしたり、コミュニケーションを促したりするファシリテーション能力が求められます。
常にリーダーが上に立って、お手本を見せるのではなく、メンバーを主役としながらリーダーが潤滑油となるのがポイントです。
チームビルディングの具体的な手法・取り組み例

最後に、チームビルディングの取り組み方法について具体例を挙げながらご紹介します。ゲーム感覚で、準備なく導入できるものも多いのでぜひ参考にしてみてください。
ジェスチャーゲーム
ゲーム形式のワークを行ってチームビルディングを高める手法です。ジェスチャーゲームとは、チームメンバーの1人が皆の前に立ち、お題を身体の動きのみで表現して、見ているメンバーに答えを予想してもらうものです。
2~3名の少人数から10名単位の大人数まで対応でき、準備するものが少なく、いつでも実施できるのが魅力です。チャットなどでお題を送れば、オンラインでも実施が可能な施策です。
自己紹介ゲーム
普通の自己紹介を行うのではなく、ちょっとしたルールを取り入れて行うゲーム感覚のチームビルディングです。形成期には自己紹介が必須ですが、何の仕掛けもなく自己紹介を行うよりも工夫をこらして進めるほうが効果的でしょう。
ゲームのルール例としては、「イラストのみで自己紹介を行う」「1分間など時間制約を設けて自己紹介を行う」「私、実は~~です。と冒頭にカミングアウトを入れて自己紹介を行う」などがあります。
筋トレやヨガ
身体を動かす企画を通してチームビルディングを行う手法です。リモートワーク中の運動不足にもつながり、心身ともにリフレッシュしながら交流を深めます。
筋トレやヨガであれば、1人が横になれるスペースがあれば気軽に実施できますし、運動を通して相手の意外な一面を見つけられるかもしれません。
制限時間内に何回腹筋できるかなど、チーム戦にしてみてるのも良いでしょう。ヨガであれば、実施前後にそのとき感じている気分、気持ちを言葉にして伝えあうのも効果的です。
まとめ
チームビルディングは、メンバー1人ひとりの個性や能力を最大限に引き出し、組織のミッションや大きな成果達成を目指していくものです。
リーダーがコミュニケーション量・質を意識しながらファシリテーションし、タックマンモデルの5段階ステップを意識した施策を導入していけば、組織活性化や生産性向上が期待できます。
チームワークとの違いを理解したうえで、ゲーム感覚の施策から気軽に導入してみてください。
ワークエンゲージメントとは従業員の仕事に対する充実感や、メンタル面での健康レベルを示す概念です。従業員エンゲージメントや、従業員満足度などと合わせて、ワークエンゲージメントを高めることに注目している企業が増えています。 今回はワークエ[…]