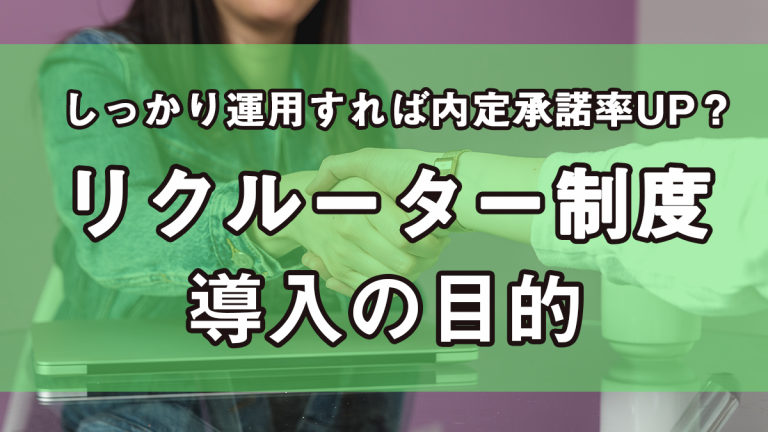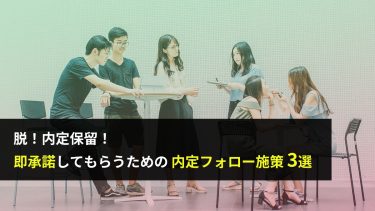本日はリクルーター制度の現状や役割、活用事例についてご紹介させて頂きます。
『リクルーター』は採用活動のキーパーソンとよく言われていますが、そもそもリクルーター制度って何?といったところから抑えるべきポイントやリクルーター制度がもたらす企業のメリットなど、有益になるご情報をお届けできればと思います!!
リクルーター制度とは?
リクルーター制度とは、自社採用において、1~5年目くらいの若手現場社員が、入社を志望する就活生に直接接触することをいいます。
以前の買い手市場から現在の売り手市場によって多くの企業が頭を抱えている採用難に陥る企業の増加や、2016年度以降の選考解禁日の後ろ倒しなどの採用市場の変化に伴い、近年リクルーター制度が見直され、各企業の導入数も増加傾向にあります。
また、競合他社に優秀な学生を取られないよう、早い段階でリクルーターが学生たちと接点を作り、より自社に入社するよう囲い込みなどを行っています。
実際この制度を実施し、学生の声から多くの評価が事例としてあるので、しっかりと理解し進めていきたいところです。
そもそも「リクルーター」とは?
では具体的にリクルーターとは、どのような人を指すのでしょうか。
実は人事担当とリクルーターの明確な定義はないのですが、一般的には学生と年が近い入社数年程度の社員が務めることが多いです。
年齢の近い社員をリクルーターにすることは、学生に「親近感を湧かせられる」「入社後のイメージを持たせやすい」などの狙いがあげられます。
リクルーター制度の重要性・導入の目的
 多くの企業でこのリクルーター制度が導入されていますが、具体的にどういう重要性、目的があるのでしょうか?
多くの企業でこのリクルーター制度が導入されていますが、具体的にどういう重要性、目的があるのでしょうか?
リクルーター制度を行う際、押さえておくべき5つのポイントをご紹介させていただきます。
まずはやってみよう!ではなく実施するうえでしっかりとポイントを押さえつつ、効率よく動けるようにしていきましょう。
志望度の高い学生を多く集める(母集団の形成)
新卒採用において最も重要とされているのが「母集団形成」です。少子化によって、今後ますます応募数が減少していくと考えられる新卒採用においては、応募人数の確保は必須事項です。
『なかなか人が集まらない、、、、、』自社でこんなふうに思うことってありませんか?
そんな時まず初めにリクルーターが行うのは、候補者=学生を集めるということです。
その際企業側の意識として、自社で働きたいと思う意識がある学生に対して、少しでも多くアクションを起こす必要があります。
しかし、ここで企業にやってしまいがちなケースとしては、単純に数だけ集めてしまうパターン。
確かに現状、各企業や各業界との競争率は年々激しくなっていく中で「少しでも多くの学生と接触をしておいたほうが、、」といった考え方になってしまうのは間違ってはいないです。
ですが、その行動に執着しすぎると
- 自社とのマッチングがうまくいかずに欲しいと思える人材に出会えない
- 結果見定める重要なポイントで自社にあった採用がうまくいかずに、獲得した人材が入社後、早期の離職に繋がる
などの問題が発生してきます。
これは、近年の企業様にもよく起こりえる問題として声が多くあがっている点です。
初めの「集める」という時点で『学生を見極める』という行為をしないと、結果その後のフローで、つまずくことが増えるので注意しましょう。
学生の囲い込み
実際に学生から応募があったとしても、他にも多くの会社に面接へ行っているはずです。
特に売り手市場の現代では、学生たちがより自由に企業を精査し好きな会へ入社できる傾向が強いため、内定を出しても他社へ流れてしまうことが多いです。
そのため、リクルーター制度を導入し学生とコンタクトを取り続けることは、他社に学生が流れないようにするために非常に重要なことと言えます。
双方にとっての相互理解を統一する
次にリクルーターの役割として重要なのは、学生に対して適切なコミュニケーションを行い、適切な情報を伝えるということになります。
学生への情報を伝える手段としては、学校への説明会や候補者へのコミュニケーションなどがありますが、このコミュニケーションを通じて学生への理解を深めることや、志望度が低い人たちに興味を持ってもらうことをしていきます。
その後リクルーターは、採用面談を通して会社にとっての有益な人材かを判断すると同時に、お互い認識の違いなどがないように相互理解を統一していくことが重要になってきます。
適切な人材を入社に結び付ける
リクルーターは面談が進んだ候補者に対して、不明点の解消や自社の魅力を知れなかった人たちへのフォローをするのも1つの役割です。
採用面接の際に聞けなかったことや、わからなかったことはないか?と学生が安心して次の選考に進めるようにサポートすることが必要です。
学生が入社を決めている理由の1つとして採用担当者の方が親身になってサポートしてくれたといった理由が挙げられています。
学生1人1人に向き合った採用をするためにも、人事担当者はリクルーターがきちんとコンタクトできているかを確認し学生へのコミュニケーションエラーがないようにしましょう。
企業への理解度向上
学生の入社意欲を向上させるためには、自社の理解を高めてもらうことも重要です。
現役社員との接点を増やすことで、学生がより会社のことを理解し入社意欲が高まる効果もリクルーター制度では期待できます。
リクルーター制度がもたらすメリット
実際に理解をしていて動くか、行動のままに動くのではリクルーター側の企業としてもどんな学生かを見極めるにあたって違いがでてきます。
そして学生に対してアプローチをする際、企業側の対応によって志望順位にも大きく影響が出てくるのでしっかり理解した上で実施していきたいところです。
早い時期に学生と接点が持てる
就活解禁よりも早い段階で学生と接点を持つことができます。
特に特定の大学のOB・OGをリクルーターに起用することで、その大学の学生と早い時期にコンタクトを取れるなどもメリットがあります。
学生目線で見ても、自分の大学の先輩から仕事の話を聞くことで親近感が湧き、よりリアルなイメージが持てるため、関係性のない社員から話を聞くよりも会社への理解度が深まるはずです。
内定辞退を抑えることができる
学生との接触回数を増やすことで、将来的に内定辞退を抑える役割も期待できます。
学生からすると、就活解禁前から接点を持っている企業の方が、そうでない企業と比べ理解が深まり、心情的に思い入れが強くなります。そのため、接触回数自体を増やすことが実質的に学生を上手く囲い込むことにも直結します。
また、年齢の近いリクルーターがいてくれることで学生の緊張も和らぎ、コミュニケーションが取りやすくなることで、より学生の本音を聞き出しやすい環境を作ることができます。その関係性を内定後も継続的に取り続けば、たとえ他社内定で志望度が下がっても、すぐにフォローすることが出来、内定辞退を防ぐことに繋がりやすくなります。
学生ひとりひとりに効果的なアプローチができる
リクルーター制度は、自社の魅力について個人単位でアピールできるメリットがあります。
会社説明会では、質疑応答の時間を設けていたとしても、限りある時間の中ではなかなか自社の魅力を伝えきれません。
そこで、リクルーターが、説明会では伝えきれなかった会社の雰囲気だったり、仕事の細かい内容を1対1で伝えてあげることで、より効果的に自社の魅力をアピールすることができ、「自社の社風を伝える」「学生の個性を把握する」などといった話を、団体ではなく個人単位で行うことができます。
会社の中身を知っていただくことによって、選考が進むに連れ、自社に対する理解・興味が深まれば、その分志望度もあがってきます。そのため、面談できる人数は少ないものの、面談ひとつひとつの質が高いことから、学生の入社意欲を上げることができるメリットもあります。
リクルーター制度の注意点・デメリット
魅力の多いリクルーター制度ですが、逆にその制度がもたらすデメリットも存在します。
接点を持てる学生が限られる
基本的に接触できる学生は、リクルーター社員の母校やインターンシップの参加者に限られています。そのため、アプローチ先がやや狭く、企業側が行動できる範囲に制限が生じます。
また主にマンツーマンでの面談が基本となるため、企業説明会などと比べると一度にリーチできる人数が低いとういデメリットもあります。
社員の負担が増える
入社数年程度の社員をリクルーターに起用するのがおすすめですが、その場合彼らの本業に支障をきたしてしまう場合があります。
人事専任ではない社員にリクルーターの役割を与えると、就活期間中は自分が本来取り組むべき業務に役割が上乗せされるため、本来期待できる成果や作業効率に影響が出てしまうことが懸念されます。
人事部以外の他部署の社員にリクルーターをお願いする場合は、負担を感じさせないようにフォローすることも大切です。
リクルーターの質が採用結果に直結する
実際に最も学生との接点が多くなるリクルーターは、その質が非常に重要です。リクルーターの質や学生への対応によって自社のイメージダウンにも繋がってしまうことがあるためです。
そのため、いかに学生の心に寄り添えるか、悩みを解決してあげられるかなどがカギとなり、リクルーターの人選ミスは採用失敗に直結する場合があります。
リクルーターを選ぶ際は、慎重に協議を重ね適した人材を起用する必要があります。
「応募した際に初めに会う人=会社の顔」とも言われ、その人たちの接し方や対応によって学生からの期待値の低下が起こると逃げていく傾向もあります。話し方や話す内容に関してもリクルーターの質の向上が求められます。
応募者にはどういうメリットがあるのか?
ここまでは企業側のメリットを解説してきましたが、一方で応募する学生側にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
具体的には以下のようなメリットがあげられます。
就活前に情報収集ができる
年々早期化する就職活動において、学生側にはスピード感も求められています。
多くの学生が就活解禁前にインターンシップに参加するなど早い段階で行動を起こしているため、リクルーターと早期に接触して情報収取することは、学生が就職活動を行う上でも大きなメリットになります。
社員や会社の雰囲気を理解できる
年の近い現役社員をよく観察することで、その社員や会社の雰囲気を事前に把握することができます。
学生にとっても会社の雰囲気などは就職の際非常に気になる点であるため、現役社員との交流は企業理解を深めるうえでも非常に有意義な時間となります。
自分の将来がシミュレーションできる
上記に加えて年の近い現役社員とコンタクトを取ることで、自分の数年後の未来がある程度シミュレーションできます。
さらにはシミュレーションを行うことでよりリアルな職場環境が見えてきて、将来的なミスマッチを事前に防げる可能性も大きく上がります。
リクルーターにアサインすべき人材要件
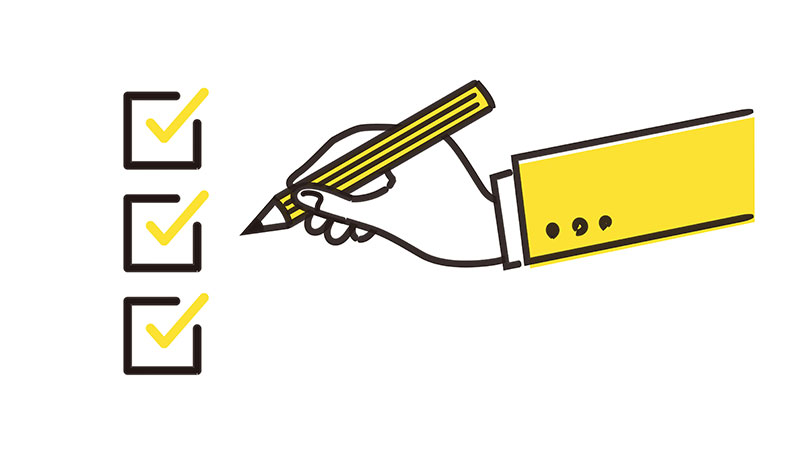 では、実際にどのような社員をリクルーターに起用したらいいのでしょうか?迷っている人事の方は、以下のような条件を参考にしてください。
では、実際にどのような社員をリクルーターに起用したらいいのでしょうか?迷っている人事の方は、以下のような条件を参考にしてください。
入社5年以内の社員
リクルーターに起用するのであれば、ある程度若い社員の方が良いでしょう。目安としては役職に就く前の5年以内あたりの社員がおすすめです。
より学生と立場が近いため、学生とコンタクトを取る際に学生側も親近感を持って話をすることができます。
コミュニケーションスキルがある社員
コミュニケーションスキルもリクルーターには必須の能力です。
不安や悩みを抱えている学生や、あなたの会社のことを詳しく知りたい学生などを相手にするため、リクルーターは一定のコミュニケーションスキルが求められます。
就活を頑張っていた社員
実際に就活で苦労した社員を起用するのも、一つの手段と言えます。
現在就活を通して悩んでいる学生たちに、実体験を基にアドバイスができるため、より学生からの信頼を得られやすく、企業自体の評判を上げることも可能です。
リクルーター制度導入の手順
リクルーター制度の導入手順をご紹介しますので、導入の際は参考にしてみてください!
リクルーターの選出
まずは社内の人材でリクルーターに適している人材を選出します。
先述通り、コミュニケーションスキルがある人や、学生へ寄り添うことができる若手人材を選出し、まずはリクルーターのチーム編成を完成させる必要があります。
リクルーターの育成
選出後はリクルーターの育成を行います。
人材採用そのものは非常に難しく、対人とのコミュニケーションが求められるためリクルーターを一人前に育てる必要があります。
また先述通りリクルーターの質は採用結果に直結しかねないので、企業ごとにレギュレーションを設け、リクルーターの育成には時間をかけることをおすすめします。
具体的な戦略立案
最後に、実際どのような役割や戦略でリクルート活動を行うべきか話し合いの場が必要です。
企業説明会と違い、リクルーター制度では少ない人数に質の高いアプローチが求められます。そのため、事前に学生に何を伝えるのか、学生から質問された場合どう答えるかなど、ある程度共通事項を決めておいた方が良いでしょう。
リクルーター制度の導入事例
実際にリクルーター制度を導入し、新卒採用を成功させている企業をいくつか紹介します。
三井住友銀行
三井住友銀行は採用活動の早い段階からリクルーター制度を導入しています。
三井住友銀行のリクルーター制度は面談回数が多いのが特徴で、学生によっては5~7回ほど面談を組み、学生への理解を重視しています。
加えて面談時に学生の入社後の成長できるかなどのポテンシャルを審査し、良い人材にはさらに多くの面談回数を設定しています。
トヨタ
世界的にも有名な企業であるトヨタでは、内定者のほとんどにリクルーターをつけて面談を行っています。
基準としてはトヨタへの入社意欲が高い人にリクルーターをつけて囲い込みを行い、内定辞退者を抑えるよう働きかけています。
またリクルーターの決裁権も大きい部類で、リクルーターが認めた学生の面接回数を減らすなど、人事さながらの役割を担っているのがトヨタのリクルーター制度の特徴です。
ニトリ
北海道に本社を構え、全国規模活躍を見せているニトリでは、学生に合わせたタイミングでリクルーター制度を活用しています。
インターンシップで良い印象のある人にはリクルーターを早期につけたり、面接の過程で光るものを感じた学生には最終面接前にリクルーターをつけたりなど、その場の状況に合わせて柔軟にリクルーター制度を活用しています。
まとめ
学生の就職活動の早期化や、年々の採用状況の変動などで、学生獲得の競争率はどの企業も苦戦している中にあります。
どんな状況であっても大切になってくるのは、企業にとって自社に適した人材の確保です。
入社してからの早期離脱は企業側として避けたい部分ですので、まずは学生の心に寄り添うことが成功への1歩であると考えます。
なので、学生に適したフローで学生が欲しているニーズに反応し、双方にとって長く働いてもらう、仕事に楽しさや、やりがいを感じていただくそのような採用活動の実現のための人材戦略の1つとして、リクルーター制度を導入してみてはいかがでしょうか。
最近、クライアント様先に訪問させて頂くと 人事担当者 「ここ数週間で学生に逃げられてしまった(T_T)」 「今年は、例年以上に、保留になるんです。。。」 と、嘆きの声をよく耳にします・・・。皆さんは、如何でしょうか?[…]