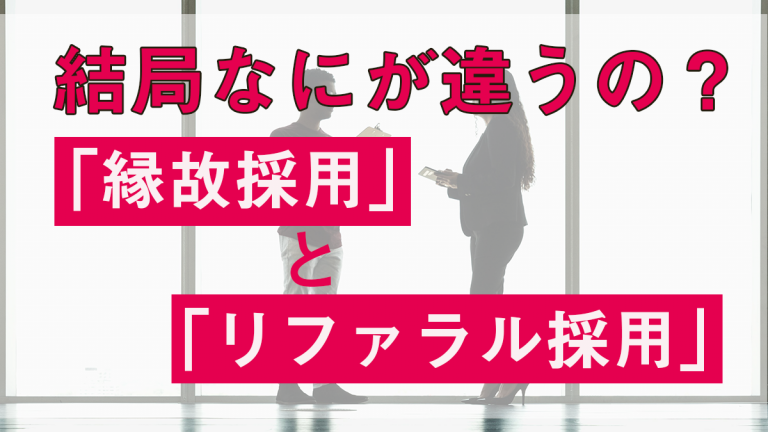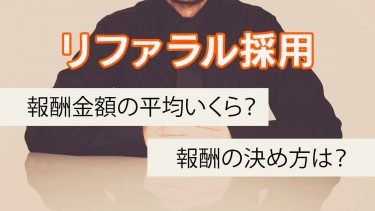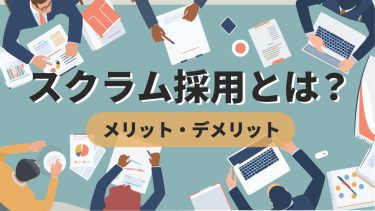皆さんの企業では、縁故採用に取り組んでいますか?縁故採用やリファラル採用という言葉はしているものの、実際に取り組んだことのない企業に向けて、縁故採用の基本事項をご紹介していきます。
縁故採用(コネ採用)とは?
 縁故採用とは、社長や役員、社員などのつてで人材を紹介してもらう採用活動を指します。
縁故採用とは、社長や役員、社員などのつてで人材を紹介してもらう採用活動を指します。
縁故とは「人の間のつながり」を意味しています。つまり、社員の知人、家族、親族など何かしらの接点のある人を会社に紹介し、採用活動を行うことを縁故採用と呼びます。類似表現で、コネ採用や、リファラル採用とも呼ばれます。
人の縁・繋がりを活用することで、求人媒体や人材紹介を使わずに求職者と接点を持ち、採用コストの削減・採用後のミスマッチを減らすなど、効果的な人材募集をすることが可能になります。
ただ、最近のイメージとしては否定的な意味で使われることが多いかもしれません。
リファラル採用との違いは?
ただ純粋に、知っている人を連れてくる縁故採用とは異なり、リファラル採用は知り合いの中でも自社に合っていそうな人を選んで推薦する、という意味合いが強くなります。
リファラル採用と縁故採用を細かく使い分けずに、両者とも「社員の知り合いを採用する方法」と、ざっくりとらえている人も多いです。
企業風土や仕事内容などを事前に知ることができ、入社後のミスマッチを防ぐためにリファラル採用は有効だといわれています。
ここ最近、採用マーケットにおいて「リファラル採用」という言葉をよく耳にします。 中途採用において、検討の方も多いのではないでしょうか。しかし、導入するにあたり「報酬の相場」は気になりますよね。 本記事では、リファラル採用を導入す[…]
新卒と中途ではどちらが多い?
縁故採用は、新卒採用と中途採用のどちらかで多いとは言いづらいです。縁故採用を実施した企業数、採用数などの公的なデータはありません。
縁故採用のメリット/デメリット
縁故採用のメリット・デメリットについて、企業と候補者それぞれの目線で整理してみましょう。
縁故採用のメリット
ネガティブイメージがあるように思われる縁故採用ですが、実はメリットとしてはかなりパフォーマンス性が高いものがあります。
採用にかかるコストを削減できる
最近では、求人媒体を活用することが当たり前のようになっていますが、媒体の活用はコストがかかってきます。
縁故採用では広告を打つ必要もなく、転職エージェントなども必要がありません。
さらに言うと採用試験や面接を省くこともでき、時間という部分も削減することもできます。
転職サービスを活用したりすれば、時間と数十万円から数百万円のコストがかかることを考えるとかなり大きなメリットになります。
求める人材を採用できる可能性が高い
縁故採用では企業として求める人物像を掲げたうえで、企業としての特性を理解した社員が採用されるケースが多いです。
そのため、定着率も高く「育てていたのにすぐに辞めてしまった」などの結末を迎えるリスクは低くなります。
採用側として求める人材かどうかも把握したうえで採用することができます。
縁故採用のデメリット
時間やコスト面のメリットに対して、デメリットは人のしがらみの部分が多いような気がします。デメリットについても、把握しておきましょう。
望むような人材ではないが採用を迫られることもある
身内だから、ということで親族から迫られるケースもあります。
本当に必要な人材を採用できないのであれば、デメリットになってしまうのも縁故採用。判断を誤ってしまうことが無いようにしておきたいものです。
採用計画が立てづらい
縁故採用は「求人広告や人材紹介のように候補者がたくさん出てくる」という性質のものではなく、応募人数を見込みづらいというデメリットがあります。
それに伴って、採用計画を立てるのも容易ではありません。
そして、採用開始から入社までに時間を要するため、緊急性の高い新規プロジェクトや欠員募集では利用することができないという点が、デメリットです。
縁故採用をすべき企業の特徴
 縁故採用のメリット・デメリットなどから、ぜひ取り組んでほしい企業の特徴をまとめました。
縁故採用のメリット・デメリットなどから、ぜひ取り組んでほしい企業の特徴をまとめました。
社員のエンゲージメントが高い
既存社員の働く満足度、エンゲージメントが高い企業は、縁故採用を取り入れると良いでしょう。満足度が高い企業の社員は、自社の良さを理解しているため縁故者を口説くのに向いている傾向があります。
一般的な不人気業界・ニッチ業界
「求人広告を出しても、そもそも応募数が集まらず苦戦している」「ニッチな仕事すぎて認知度が低い」といった企業こそ、縁故採用に取り組むべきです。世間からの「大変そう・ブラック企業」というイメージは、そう簡単には払しょくできません。世論を動かすよりも、自分たちの口で語りかける方が、説得力がありますし、応募数がもともと少ないのであれば縁故採用のような能動的アクションは必須と言えます。
面接はする?縁故採用の採用方法
縁故採用に取り組んでみたい企業向けに、縁故採用の一般的な流れをご紹介します。基本を押さえたうえで、独自の縁故採用フローを作成していきましょう。
1,縁故採用の基本ルールを決める
まず始めに、縁故採用の運用するためのルール決めを行います。決める項目は以下を参考にしてください。
- 縁故採用を実施する目的
- 採用ターゲット
- 採用基準(他のルートからの応募者と分けるべきかどうか)
- 紹介NGにする条件
- 紹介者に対する特典の有無(例:紹介者が一人連れてきたら商品券を渡すなど)
- 紹介OKの最低基準
- 紹介者が縁故者を連れてくる前に必ず伝える情報、伝え方など
2,社内周知
1でルール決めを行ったら、縁故採用に関する情報を社内周知します。口頭で一度伝えただけでは社内浸透は難しいため、繰り返し伝えたり、縁故採用プロジェクトの責任者を決めたりするのがおすすめです。
3,募集・選考開始
募集を開始したら、月ごとや四半期ごとなどに、誰から何名の紹介があったか記録を行い公表しましょう。いきなり選考に進むのはハードルが高いため、職場見学会や既存社員との座談会ランチなど小イベントを企画して、社員が呼び込みやすいよう促すのもおすすめです。
縁故採用で成功する秘訣
 縁故採用を成功させるための秘訣を2つご紹介します。
縁故採用を成功させるための秘訣を2つご紹介します。
縁故採用の目的を繰り返し伝える
縁故採用は、一度社員に伝えても形骸化しやすいものです。縁故採用がなぜ必要なのか、縁故採用にどのようなメリットがあるかなど、繰り返し伝えることが重要です。
紹介しやすいサポートをする
「紹介してね」と言われても、社員は採用のプロではありません。
募集時に候補者に伝えるべき情報、どういった話で候補者を動機づけしていくかなど、社内研修を行うなどサポートをしていきましょう。縁故者に簡単に渡せるパンフレットや、Webページの作成もおすすめです。
縁故採用をする際の注意点2つ
縁故採用を行う際の注意点は主に次の2つです。
- 公平性を保つ
- 既存社員の満足度を意識する
公平性を保つ
一つ目に、縁故採用で連れてきた人に対して雇用条件の金銭的な差をつけたり、一部の人にしか採用試験を受けさせないなど不公平な募集方法にならないよう注意が必要です。
縁故採用は、紹介者と関係構築がしやすいなどのメリットがあるものの、入社前後の条件提示時や入社後にトラブルも置きやすいと厚生労働省が発表しています。詳しくは以下資料をあわせてご確認ください。
「縁故募集には人間関係などで長所がある反面、雇用条件が不徹底であるなどの就職後 の定着等に比較的問題が多いといわれております。 このため、次の生徒に限っては、縁故募集を行えますが、各種のトラブルを防止する ため、できるだけ公共職業安定所へ求人申込みを行って、雇用条件等を明確にしておい てください。 ① 事業主(中小企業については、事業主及び職長並びに管理職的職務にある者を含 む。)と6親等内の親族又は3親等内の姻族の関係にある生徒 ② 事業主と直接親しい間柄(従前から現在まで相当期間親しい交際関係の存在して いた間柄。)にある生徒 」 引用:厚生労働省
「男性または女性については、自宅通勤可能な者や縁故者など一部の者にしか採用試験を受験させない。」引用:厚生労働省
既存社員の満足度を意識する
もう一点、注意点としては、縁故採用がうまく進まない場合は必ず既存社員の働く満足度に注視するということです。
先の章でもお伝えしましたが、既存社員が自分の給与や待遇、働き方や社風など全般に満足していなければ、大事な縁故者を紹介しようとは思いません。
無理やり「一人何人紹介しなさい」と仕向けるのではなく、目の前にいる社員の気持ちと向き合うことを心掛けるようにましょう。
まとめ 結局、どっちがいいの?
ここまで縁故採用とリファラル採用について書かせて頂きましたが、では結局自分の企業が取り入れる際はどっちがいいのだろう、と思った方も多いはずです。
結論から言わせていただきますと、縁故採用とリファラル採用に明確な違いはありません。
しかし、強いていえば、
・紹介者が主導で企業と候補者の接点を作る偶発的な採用を「縁故採用」
・採用戦略の一環として行う採用を「リファラル採用」
このような形で使い分けられると思います。
もし、自社でどちらかを考えているのであれば、この違いを軸に考え自社に適しているのはどちらだろうと考えてみるといいかもしれません。
▼え?それはリファラル採用じゃないの?社員の知人の紹介採用…「スクラム採用」とは??
近年、労働人口の減少により人材獲得競争が激化していることから、これまで一般的だった採用手法では優秀な人材の確保が難しくなっています。 そこで、注目されているのが「スクラム採用」です。 この記事では、スクラム採用とは何かをはじめ、[…]