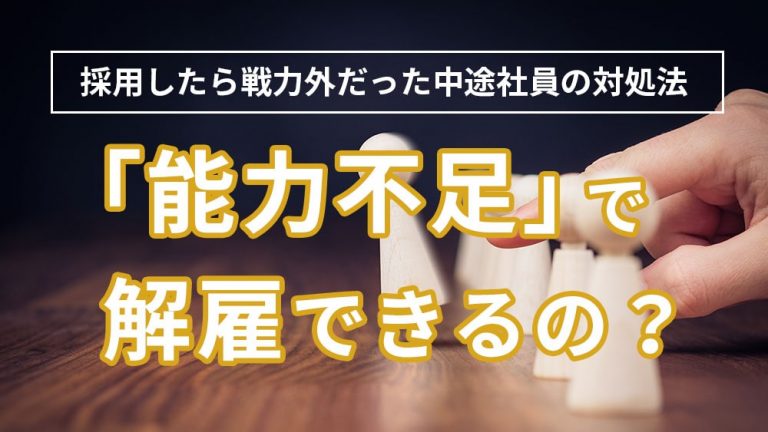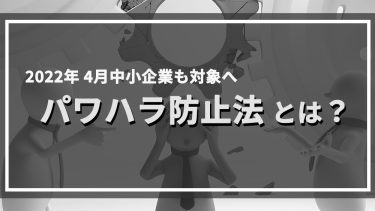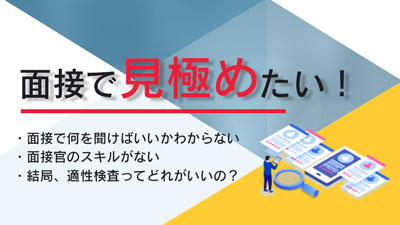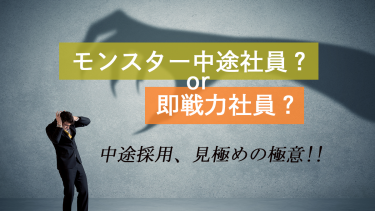即戦力を期待して中途採用を行ったものの、思ったよりも能力が低く、このままでは会社のプラスにならないと感じたことはないでしょうか?
実際に解雇に踏み切りたくても、法律的な縛りもあり、なかなか難しい部分がありますよね。
そこで今回は、能力不足の人材を中途で採用してしまった場合の対処方法、不当にならない解雇方法などをお伝えいたします。
能力不足で解雇はできるのか?
結論から言うと、単に能力不足というだけで社員を解雇するとは非常に難しいです。
具体的な理由や適切なプロセスを踏まずに能力不足で解雇をしてしまうと、解雇権濫用法理とみなされ会社側に大きなデメリットが生じます。
後ほど詳細を解説しますが、能力不足の社員を解雇したいのであれば、正しいプロセスを踏むことや、証拠を集めるなどして正しい順番で解雇をする必要があるので注意してください。
試用期間中だったら解雇してもいい?
 中途採用の場合、多くの企業が3ヶ月前後の試用期間を設けています。
中途採用の場合、多くの企業が3ヶ月前後の試用期間を設けています。
しかし、その試用期間の最中で実力不足だと判断した場合、試用期間満了前に解雇を行うことはできるのでしょうか?
結論としては、原則試用期間中は社員を解雇することができません。
あくまで今後会社で活躍できるかどうかを判断するのが試用期間であるため、試用期間中に解雇をすることはいわば制限時間内にテストを回収するのと同義です。
しかし、状況次第では試用期間中でも解雇をすることが可能です。
試用期間中の解雇方法
基本的には試用期間中の解雇はできませんが、以下のような場合であれば試用期間中に解雇をすることが可能です。
- 病気や怪我などで復帰が難しい場合
- 勤怠態度が著しく悪い場合
- 経歴詐称が発覚した場合
一般的には試用期間中においても、上記に当てはまっている場合には解雇することが可能となります。
中途採用社員に対して、期待していたほどのパフォーマンスが発揮できていな場合、試用期間中に解雇に踏み切りたい企業も多くあるでしょう。
しかし、能力不足での解雇は場合によって解雇権濫用法理として訴えられる可能性があるため、試用期間中に解雇をしたいのであれば、上記の3つが理由となるように運んでいく方がベターです。
採用人材が「能力不足」だった場合の対処法
そもそもなぜ、能力不足で解雇を考えるのでしょうか?
おそらくどの企業も、解雇をすることが目的なのではなく、成果が上がらないことをどうにかすることが本質的な問題のはずです。そのため、能力不足の社員に対しては、まずどうすれば能力が上がるのか考えてみてください。
頑張って教育する
最もシンプルな方法ですが、まずは社員が能力を発揮できるように教育に力を入れてみてください。
能力を発揮できていない社員に対して、1on1ミーティングを組んでみたり、OJTに力を入れてみたりと、解決方法は様々あります。
そのため、能力がないから会社に貢献できない、つまり解雇すると言う結論に至るまで、まずは教育など会社側ができることに全力で取り組んでみてください。
中途採用の多くが即戦力になることを期待されて採用されるため、意外と教育面に関して見落としがちですが、教育や研修にテコ入れをすることでパフォーマンスが大きく向上することもあります。
異動の辞令を出す
現在パフォーマンスが上がっていない原因として、配属された部署がその人の実力とあっていない可能性があります。
単なる能力不足に見える社員でも、部署を異動することで業務に変化が生まれれば、もしかすると本来の実力を発揮できるのかもしれません。
そのため、改めてその社員の能力や実績を確認し、実力が最大限発揮できる部署を探して異動させることも一つの手段です。
また、自分の支店や支社で育てきれない社員であれば、異動をさせることで自分に掛かる負担を減らすこともできます。
もしも教育が上手くいきそうになければ異動辞令を出し、他の部署で教育してもらうことも検討しましょう。
退職を推奨する
一方的に解雇をすることは違法ですが、退職を促すことは違法ではありません。
教育しても伸びしろがなく異動も難しいのであれば、本人の意志による退職を引き出す手段も考えなければなりません。
そのためにはまず、合理的で正当な理由を集めて、なぜ退職を推奨するか理解してもらうようにしましょう。
この段階で理解が得られないと一方的な解雇となり、パワハラや違法とみなされ最悪の場合裁判に発展する場合もあります。2022年4月からは中小企業に対してもパワハラ防止法が施行されていますので、訴えられるようなことにならないように慎重に事を運ばせていく必要があります。
近年、耳することが多くなった“パワーハラスメント”という言葉ですが、定義が曖昧で、パワハラの受け手(部下)の主張が大きく反映されやすい言葉です。 また、大企業では2020年6月からは「パワハラ防止法」という新しい法律が施行され、ますま[…]
合理的な理由がしっかりとまとめられたら、面談を組み退職を推奨していきます。その際、一方的な権力を行使した進め方は絶対にNGなので注意してください。
「不当解雇」と判断されないための解雇方法
 では実際にどのような状況であれば、能力不足の社員を解雇できるのでしょうか。
では実際にどのような状況であれば、能力不足の社員を解雇できるのでしょうか。
具体的には以下の方法があります。
試用期間の終了を待つ
中途採用を行う場合、基本的には試用期間を設定し、その期間内で期待する能力があるかどうかを見極めます。そのため、試用期間中は単なる能力不足での解雇は原則できません。
つまり、能力不足という理由で解雇を行うのであれば、まずは試用期間が終了するのを待つ必要があります。加えて、試用期間内に能力を発揮できなければ本採用にならないことを、予めしっかりと伝えておくことも重要となってきます。
いざ試用期間が終わり、能力不足で解雇に踏み切ろうとしても、なんの前触れもなく解雇を言い渡してしまうと、スムーズな退社につながらないこともあるので注意が必要です。
明確な解雇理由を提示する
能力不足による解雇の場合、明確な理由を提示する必要があります。
ただ日本の労働法は雇用される側に対して有利なものが多く、基本的には労働者が守られるような仕組みが多いです。
そのため、能力不足での解雇の場合、以下のようなフローをたどり、最終的に正当な理由を作ることが望ましいです。
- 全面的な教育支援
- 既存社員とのパフォーマンス比較
- 将来的な活躍像
このように能力不足を理由に解雇をしたいのであれば、まずは会社側が全力で教育を行ったことはしっかりと提示しましょう。
そして、それにも関わらず既存社員に比べ大きくパフォーマンスが低いことを数値などで表します。
最終的の上記の2点より、今後の活躍が見込めないことを整理して伝えることで、相手に納得してもらえる理由となります。
事前に目標値を決めておく
能力不足での解雇において、まずは何を持ってして能力不足になるのかは明確にしておく必要があります。
特に中途採用においては、面接時や入社時などのタイミングで予め目標値を明確に設定しておくことが求められます。
営業職であるならば、試用期間内に売上をどれくらい上げるのかなど、KPIを明確にするようにしてください。
逆に言うと、この条件をクリアできなければ試用期間後に本採用を結びませんということなので、双方ともに明確なハードルを設定することができます。
事前にこの目標数値を設定せず、感覚的に能力不足などで解雇しようとしてしまうと、退職推奨の際に亀裂が生じスムーズに進めることが難しくなってしまいます。
そのため、事前に能力不足かどうかを図るラインとして、具体的な目標を数値として双方が把握しておくことは、後々能力不足で解雇を行う際、非常に有用な判断材料となります。
中途採用者の解雇をめぐる裁判事例
能力不足による解雇は、正当な場合と不当な場合両方があり状況によっては企業側に罰金が課せられる場合があります。
また、実際過去には以下のような裁判が開かれています。
しかし採用者は入社後に会社側が指示した営業先にセールスをしなかったため、業務指示に従わなかったとし解雇されています。
この場合の判決は、能力不足だけにとどまらず、業務指示に従わないため、正当な解雇とされました。
(平成30年10月15日東京地方裁判所判決)
このケースでは、雇用契約書に特別の業務能力を必要としない前提での採用であったため、能力不足は認められるものの、十分な指導や改善機会を与える前に解雇をしたことにより不当解雇とみなされました。
そしてその結果、企業側に約2,500万円の支払いが命じられています。
(平成30年2月26日東京地方裁判所判決)
まとめ
もしも現在能力不足の社員に困っており、解雇を検討しているのであれば、ぜひこの記事を参考にして、正当な解雇方法でお互いに納得のできるように努めてほしいと思います。
ですが、このように、単なる能力不足で中途採用で獲得した社員を解雇したい場合、状況によっては違法となるため、慎重に進めなければなりません。そのため、人事の方は解雇を考えるときに正当な理由を集めたり、面談を組んだりと取り組むべきフローが非常に多く、解雇するまで相当な労力がかかります。
入社の前段階で「モンスター中途社員」を見極められたら、きっとこんな苦労はしなくて済むはずです。ぜひ選考段階で見極める力を養ってください!
【資料内容】
■惹きつける面接と見極める面接
■面接の質問例(新卒・中途)
■オンライン面接での見極めポイント
業界経験が長く、人柄も良さそうだと思って中途社員を採用したものの、現場で全く使い物にならなくて困っている企業様は少なくないでしょう。即戦力になりそうだと経験者を採用したにも関わらず、彼らのスキルを活かしきれないのは何故なのでしょうか? […]