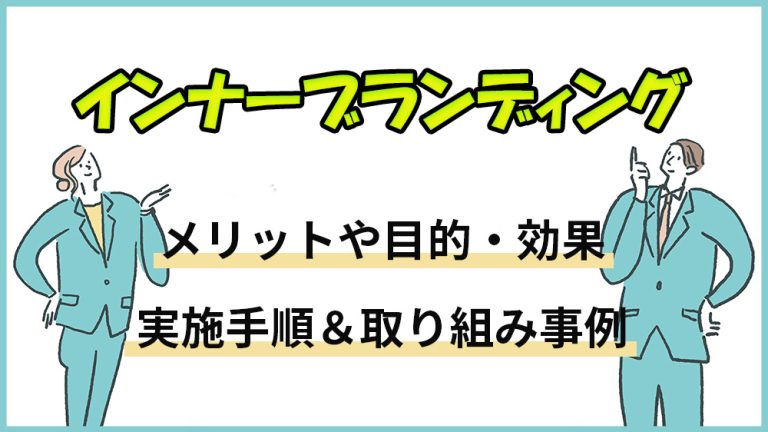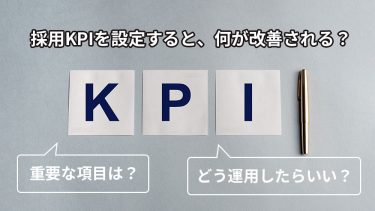インナーブランディングとは、自社の社員に対して実施するブランディング活動です。ブランディングというと、つい社外発信をイメージしてしましますが、インナーブランディングとアウターブランディングは密接につながっています。
今回は、インナーブランディングを実施する目的や効果、具体的な施策例などをご紹介します。
インナーブランディングとは

画像引用:chibico「インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?」
インナーブランディング(インターナルブランディング)とは、企業理念やミッション・ビジョン・バリューなどの価値観を明確化し、社員に向けて発信・浸透させる活動を指します。ブランディングというと、一般的には社外に向けた認知拡大であるアウターブランディングをイメージする方も多いのではないでしょうか。
- インナーブランディング…対社員。企業や事業の価値観、企業の在り方を理解浸透させる
- アウターブランディング…対消費者、ステークホルダー。自社ブランドの認知拡大を行う
上記2つが機能して初めて、企業のブランディングが確立されると考えられます。
インナーブランディングを行う目的と効果
インナーブランディングを行う目的は、社員に正しく企業・事業の在り方やメッセージを理解させ、社外に向けた発信や活動の質を保つことが挙げられます。
また、インナーブランディングを強化することで、結果的にアウターブランディングも回り出し、企業価値そのものを高める目的もあるでしょう。
- インナーブランディングを実施して得られる効果例
- 企業理念を始め、ミッション、ビジョン、バリューやクレドなどの一貫性と浸透
- 自社ブランドに対する愛着心の向上
- 顧客やステークホルダーに対する情報の一貫性、サービスの質向上
- 社員の定着化 など
上記のように、インナーブランディングへの取り組みは、企業に多くのメリットがあります。
一方、インナーブランディングに注力していない企業は、社員の口で「自社らしさ」「自社の良さ・悪さ」を説明することができません。またブランディングという単語から、インナーブランディングはクリエイティブ力を高めることと勘違いしているケースも見受けられます。
どんなに企業ロゴやホームページをかっこよく、クリエイティブに仕上げても、企業理念や価値が社内に浸透しなければインナーブランディングの効果は得られないと言えます。
インナーブランディングのデメリット・注意点
インナーブランディングに取り組めば、社員の士気も高まり、企業理念や存在意義に一貫性が増すなどメリットが多い一方で、デメリットもあります。ここではインナーブランディングに取り組む際のデメリット、注意点を見ていきましょう。
時間・費用がかかる
インナーブランディングは、一朝一夕で実施できるものではありません。インナーブランディングで社員に浸透させるべき、以下の項目を整理し、正しく言語化することは非常に骨の折れる作業となります。
・ミッション、ビジョン、バリュー
・クレド
・行動指針
・事業の役割、方向性
・社員の在り方、存在価値
・事業や社員の介在価値 など
これらが曖昧なままでは、インナーブランディングはスムーズに進みません。また、どのような状態が「インナーブランディングが高まった状態」と言えるのか、判断基準も設けなければなりません。
インナーブランディングは時間がかかるうえに、多くの議論の場や施策実施が必要となるため、費用もかかる点がデメリットといえます。インナーブランディングのために、外部コンサルティング会社を頼る場合、数十万円~数百万円ないし、それ以上のコストがかかるケースもあるでしょう。
インナーブランディングの手法・具体施策

インナーブランディングの実施手順をご紹介します。ここでは、あくまでも基礎的な流れの説明となるため、必要に応じてカスタマイズして活用ください。
ステップ1:現状の課題を確認
まずは、自社の現状を正しく把握することから始めましょう。
経営層が自社ブランドをどのように考えているのか、現場の社員の考えとギャップはあるかなど、アンケート調査や聞き取り調査を進めましょう。出来る限り、複数の視点で調査を行い、数値で確認できるものは数値で計測していくのがおすすめです。
ステップ2:インナーブランディングの実施目的を言語化
次に、インナーブランディングを行う目的を決めます。
ただ一方的に「インナーブランディングをやります」と言っても、忙しい業務の中で社員から煙たがられる場合もあります。明確に目的、ゴールを言語化することで、説得力が増すでしょう。
ステップ3:企業理念など浸透させる価値観を見直し、策定
社員に浸透させる企業理念やミッション、ビジョン、バリューなど価値観を見直し、もし無ければ一つずつ策定していきます。
ステップ4:KPI設定
目標設定時と同じく、定量的な数値判断できる評価基準を設定しましょう。
「企業理念が浸透した」状態は、本来非常に抽象的なものです。数値化しづらい項目も多々ありますが、アンケートの回答率なども含めて、わかりやすいKPIを決めていきましょう。
各企業では事業を行う際に、一般的には目標達成のためのKPIを設定しています。 基本的には決められたスケジュール感で、どれだけの売り上げや成果を上げられるかをもとに、KPIは決められます。そんなKPIですが、実は採用活動においても非常に[…]
ステップ5:施策の検討、実施
現状把握の中で出てきた課題に合わせて、インナーブランディング施策を検討していきます。全てを一気に進めることは難しいため、優先順位をつけて戦略を立てていきます。
ステップ6:定期振り返りの実施
施策を実施した後は、必ず振り返りの時間を確保しましょう。どのような施策も、やりっぱなしでは全く効果を得られません。毎回の実施前、実施後に数値計測や聞き取り調査を行い、継続していくことで変化がえられます。
インナーブランディング施策例
最後に、インナーブランディングの成功事例をご紹介します。
カードや特設サイト、グッズの作成
企業理念やビジョン、企業の方針を社員に常に意識してもらうために、持ち運べるサイズのカードに企業理念などを記載して持たせるのも有効です。社員証や通行証と一緒に常に携帯させて、朝礼や定期的な集まりの際に取り出し、読合わせするのも良いでしょう。
カード以外にも、社員向けのメッセージをまとめた特設のWebサイトをつくったり、動画メッセージで社長から語りかけたりするのも効果的です。毎日使うボールペンやクリアファイルなどのグッズに、企業のクレドや行動指針などを記載するのも良いでしょう。
社内報
インナーブランディング施策として社内報を実施する企業も多いです。社内報に毎月、社長や役員陣からのメッセージを載せることで、定期的な情報発信が仕組み化できます。また、一方的な配信ではなく、「今月の企業バリューを体現した社員の紹介」「事業価値を高めた良い取り組みの表彰」など、インナーブランディングに関する話題、社員が体現できた話を取り上げて紹介するのもおすすめです。
読み物として飽きが来ないよう、純粋に楽しめるコンテンツ(占いや社員の誕生日紹介などもOK)を盛り込むことで、社内報を浸透させることができるでしょう。
オウンドメディア
事業に関するニュース、業界の気になるトピック、役員陣や社員の異動情報などをオウンドメディアに掲載することで、社外の発信と社内向けの発信を同時に進めることができます。
近年では、採用広報の一貫として採用オウンドメディアに取り組む企業が増えていますが、採用候補者向けの情報は、同時に社内向けの重要な情報になります。
ワークショップや研修
企業理念や事業の方針を頭ではわかっていても、いざとなると実践できない人も一定数います。社員のアウトプット力を高めたり、理解度を深めたりするためには、社員参加型のイベントやワークショップ、研修を実施するのも効果的です。
自社で取り組むのが不安な場合
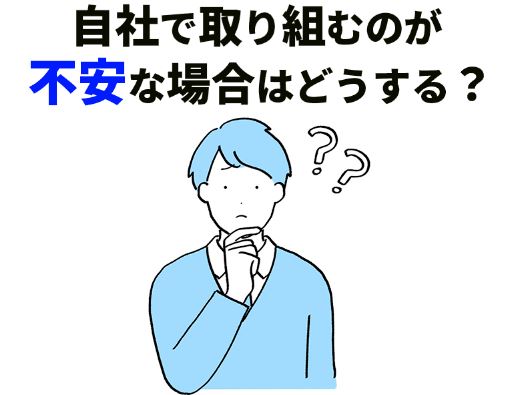
インナーブランディングは、無理に自社だけで取り組む必要はありません。インナーブランディングに欠かせない企業理念やクレドなどの作成を支援してくれるコンサルティング会社や、社内報やクレドカードなどの制作を請け負ってくれるサービスも多数存在します。
全体の進め方がわからない場合は、人事コンサルティング系の会社に依頼をして、具体的な施策ごとに手が足りない場合は、その都度研修会社や制作会社などに頼るのもおすすめです。少しでもご興味ある方は、お気軽にキャリアマートにご相談ください!
まとめ
インナーブランディングに取り組むことで、企業ならではの価値観や文化が醸成され、人材の定着やサービス提供の質向上など様々なメリットがあります。
インナーブランディングの強化には非常に時間がかかり、効果を数値計測しづらいなどの難しい側面もあるため、根気強く取り組み必要があります。まずは自社の現状を見直し、理念や事業の存在価値について考え直してみてください。
新卒や若手社員の成長のため、目指す先として掲げられるようなロールモデルを組織の中心に配置することは、チーム編成において非常に大きな効力を発揮します。 しかし、ロールモデルの配置と言っても、どの様なメリットがあるのか、どの様に採用すれば[…]