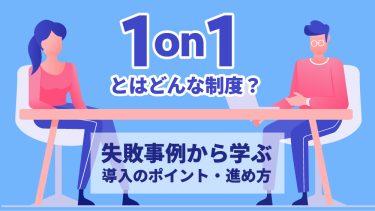燃え尽き症候群(バーンアウト)という言葉をご存じでしょうか?
仕事に意欲的だった従業員が突然やる気をなくしてしまうことをバーンアウトといいます。今回の記事では、社会人ならだれでも陥る可能性があるバーンアウトの症状や、なりやすい人の特徴を詳しく解説します。
症状がひどいバーンアウトを発症した場合、休職しなければならないこともあるでしょう。バーンアウトの予防策やその後の対応についても具体例を紹介しますので、人事担当者や部下がいる人はぜひ参考にしてください。
燃え尽き症候群(バーンアウト)とは
バーンアウトとは、熱心に仕事に取り組んでいた人が突然やる気を失ってしまうことを指します。日本語では「燃え尽き症候群」と呼ぶこともあります。
バーンアウトは真面目な性格で、完璧主義の人ほど陥りやすいとされているので、部下や同僚、自分の性格に当てはまる人は注意が必要です。ストレスが蓄積された状態で無理して働き続けた結果、バーンアウトを発症し、仕事の手抜きや欠勤などを繰り返すようになります。
バーンアウトは1970年代のアメリカで、精神心理学者ハーバート・フロイデンバーガーによって唱えられた概念です。今から50年以上前から労働者のメンタルヘルスの重要性が提唱されてきました。
燃え尽き症候群(バーンアウト)の初期症状と兆候
バーンアウトの具体的な症状は3種類に分類され、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下があります。それぞれの具体的な症状を詳しく見てきましょう。
疲労が蓄積して体力が低下し、ため息が絶えない時や、頭痛・腹痛などの身体的な不調もバーンアウトのサインです。今まで仕事に熱心に取り組んでいた人に、ある日突然以下のような症状が現れたらバーンアウトを疑ってください。
情緒的消耗感
- これまで楽しいと思っていた仕事なのに急に意欲や興味がなくなる
- 仕事に集中できず、ぼーっとすることが増えた
脱人格化
- 同僚や顧客の悪口が増える
- 仕事中に周囲に配慮できなくなりイライラするようになった
- ミスを人のせいにして自分を守る言動が増える
個人的達成感の低下
- ミスが増えて仕事の質が著しく低下した
- タスクを先延ばししてしまい期日を守れなくなる
- 仕事をしていても達成感が感じられず、自分に自信がなくなったと感じる
燃え尽き症候群(バーンアウト)の主な原因
バーンアウト発症の要因は、個人的要因と環境要因に分けられます。
個人的要因
真面目な性格で、完璧主義の人ほどバーンアウトを発症しやすいといわれています。
「成果を出そうと仕事を頑張ってしまう人」や「高すぎる目標を掲げて頑張りすぎてしまう人」は特に注意が必要です。自分や周りの人がこのような性格に当てはまる際には、バーンアウトにならないように心がけて対策をしましょう。
また、男性よりも女性の方が感情を消耗しやすいため、バーンアウト発症の可能性が高いことも分かっています。
環境要因
労働環境もバーンアウト発症を左右する大きな要因です。長時間労働、不規則な勤務時間、高いノルマが設定されているなど、精神的にも肉体的にも負荷がかかっている状態だとバーンアウトしやすいです。
また、近年増加しているリモートワークでも注意が必要です。プライベートと仕事の切り替えが難しく、つい仕事のことを考えてしまい結果的に長時間労働になりかねません。
仕事が終わったらコーヒーを一杯飲んで休憩する、10分間近所を散歩するなど、ルーティーンを設定して仕事とプライベートの境界をはっきりさせると良いでしょう。
燃え尽き症候群(バーンアウト)の予防策
人事部としては、従業員に心身ともに健康に働いてほしいと願うのではないでしょうか。ここからは、バーンアウトの予防策を「職場環境」と「メンタルケア」の観点に分けてチェックしていきましょう。
職場環境の改善
まずは、職場の環境を改善する方法の具体例をご紹介します。
1on1ミーティングの導入
上司と部下が一対一で行うミーティングを「1on1ミーティング」といいます。部下が抱えている業務量や悩みなどの現状が上司に伝わるので、バーンアウトの対策に効果的です。また、状況に応じて部下の成長もサポートできるので、バーンアウト対策だけでなくチームの成長にも繋がります。
具体的には、15~30分程度の短時間の面談を、週に一回もしくは月に一回など定期的に繰り返します。
上司と部下との間で今まで以上にコミュニケーションをとるようになり、信頼関係を構築する時間としても有効です。
「若手がなかなか育たない」「離職が続いて人手不足」といった悩みを抱えていませんか? このような問題解決の手立てとして、1on1の導入があります。近年1on1を導入する企業が増えていることから、耳にしたことがあるかもしれません。 […]
公正な評価システムの構築
人事評価制度の見直しも、バーンアウトになりにくい環境作りのポイントです。成果だけを上司が求めている環境では部下にストレスがかかってしまい、バーンアウトの要因になりかねません。一人ひとりの仕事への姿勢を公正に評価できるように環境を整えましょう。成果だけではなく、仕事への姿勢や努力した点をチェックする「プロセス評価」も取り入れてみてください。
さらに、成果が出た際にはチームでその成果を祝うのもポイントです。会社や同僚への愛着が持てる機会を積極的に作りましょう。
メンタルヘルスサポート
次に、メンタルケアの具体例を2点紹介します。
メンタルヘルス教育の実施
従業員にメンタルヘルス教育をするのも、バーンアウト対策に効果的です。仕事におけるメンタルケアの重要性を学び、バーンアウトの症状や予防策を理解すると、自分自身の現状を客観的に判断可能になるでしょう。また、自分自身だけでなく、同僚の変化にも気付きやすくなります。
相談体制の整備
従業員が自分自身でメンタルケアをするには限界があるため、会社は悩みやトラブルが発生した場合にすぐに相談できる窓口を設置しましょう。会社内に安心して相談できる相手がいると、トラブルがあっても一人で抱え込まずに済み、バーンアウト対策になります。
なお、直属の上司や同じ部署の人には相談しにくい内容も考えられるので、メンターとして別部署の相談役を設定すると効果的です。
燃え尽き症候群(バーンアウト)にさせないための対応
では、部下がバーンアウトを発症しないように上司ができることはどんなものが挙げられるのでしょうか。4点ご紹介するので、部下がいる方は以下の項目に注意して接してみてください。
日常のコミュニケーションを大切にする
1on1ミーティングなどで部下とのコミュニケーションを積極的に取りましょう。ここで、上司から部下へ一方的に話すだけではバーンアウト対策としては不十分です。部下からの話をよく聞き、「対話する」という点に注意してください。
お互いに理解を深めることでトラブルが起きた際に相談しやすい信頼関係が構築でき、部下にとって安心できるホームになります。
変化に敏感になる
バーンアウトの対策は、早期発見が重要です。先述したように、上司と部下とのコミュニケーションを増やして信頼関係を構築すると、業務量や悩みなどのちょっとした変化に気付きやすくなるでしょう。
十分な休息を促す
長時間のストレスによって引き起こされるバーンアウト対策には、休息が有効です。一日の仕事の中で部下に疲労やストレスが溜まっているようなら、5分程度の短い休憩時間を何度か取るように促しましょう。特にデジタルデバイスから離れて心をリラックスさせると良いでしょう。
周囲の助けを求めるよう促す
部下をバーンアウトさせないためにはチームで協力体制を築き、仕事を抱え込まないような環境作りが必要です。業務が偏らないように上司がバランスを取ると良いでしょう。
業務が一人に集中している場合は、上司が声をかけて業務を分散させるように促してください。
燃え尽き症候群(バーンアウト)社員への対応
どれだけ対策をしても、バーンアウトになってしまうことがありますが、そこで誤った対応をすると離職に繋がる可能性があります。では、上司はどのような対応をすると良いのでしょうか?
休職と回復支援
まずはバーンアウトした部下が心身ともに回復できるように支援しましょう。
休職を促す
休暇や休職制度を利用して、できるだけ仕事から距離を取るように促しましょう。個人差がありますが、バーンアウトから回復までに必要な期間は平均で3カ月半ほどといわれています。
休職中はしっかりと睡眠や食事を摂り、まずは健康になることを目指します。趣味など、リラックスできることを生活に取り入れることで、ストレスの軽減に役立つでしょう。
ここで注意が必要なのが、同僚からの声かけです。「あなたが休んでから仕事が大変になった」など、バーンアウトした本人が不安になるような声かけをしてはいけません。
専門家のカウンセリング受診を勧める
心の状態は目には見えないので、素人では判断が難しいことがあります。医師の診断を受けるのも良いでしょう。精神科医や産業医に現状を伝えて、判断を仰いでください。場合によっては、休息だけでなく投薬治療を始める可能性があります。
職場復帰のサポート
休職していた従業員の心身が回復したら、いよいよ職場復帰です。復帰後に無理をしてしまわないようにサポートしましょう。
段階的な復帰プロセスの構築
バーンアウト前の環境のままでは再発の可能性があります。本人が無理なく働けるように、段階的に復帰すると良いでしょう。本人のワークライフバランスの希望を聞き、業務量や時間を調整します。
時短勤務や、業務内容の調整をした「試し出社」で徐々に仕事に慣れていくのも効果的です。
継続的なサポートとフォローアップ
復帰後の従業員がバーンアウトを再発しないよう、周囲の人による継続的なフォローも忘れてはいけません。上司や人事担当は、従業員が無理をしていないか声かけが重要になります。長時間労働をしていないか、無理な目標設定をしていないか、バーンアウトの兆候がみられないかを適宜確認してください。
まとめ
今まで意欲的に働いていた人でも、ある日突然バーンアウトに陥ってしまうことがあります。バーンアウトの初期症状や、どんな人が発症しやすいのかを知っておくことで、早めの対処が可能です。企業としては従業員に心身ともに健康で働いてもらうため、労働環境を整えておく必要があります。
また、バーンアウトになってしまったとしても、従業員が休みやすい・復帰しやすい制度を作ることで従業員の離職を防げるでしょう。従業員が働きやすい環境を作り、バーンアウトを予防しましょう。
企業の中核を担うエース社員や中堅社員の場合、会社からの信用度も高く安心して業務を任せられます。 そのため、企業としては、エース社員や中堅社員の退職は、手遅れになる前に防ぎたいのが正直なところでしょう。 「エース社員の退職理由を知りた[…]