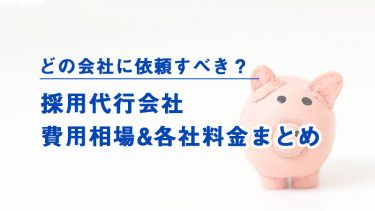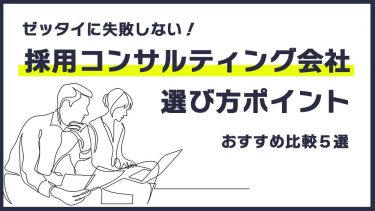組織のパフォーマンスアップに貢献する人材は、やみくもに採用しても確保できません。企業の事業成功のためには、適切な人材を採用して配置・異動することが大切であり、そのための採用計画は企業にとって、とても重要といえます。
この記事では、採用計画の必要性をはじめ、採用計画を立てるメリットや立て方についても解説していきます。採用計画立案時のポイントだけでなく、立案後のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
採用計画とは?
 採用計画とは、経営戦略や事業計画を達成するために「採用活動をどのように進めていけばよいか」という最終的な目的を明確にした計画書のことです。
採用計画とは、経営戦略や事業計画を達成するために「採用活動をどのように進めていけばよいか」という最終的な目的を明確にした計画書のことです。
- 「なぜ採用するのか」
- 「いつまでにどの部署に何人必要なのか」
- 「能力や経験を考慮してどのような人材が必要か」
- 「採用手法はどうするのか」
などを具体的に明らかにする必要があります。
企業の事業を成功させるためには、適した人材を適した部署に配置することが大切です。
採用計画の必要性
まずは、採用計画の必要性について解説します。
適した人材を効率よく採用するため
採用計画は、自社に適した人材を効率よく採用するために必要です。また、採用計画は採用に関わる各部署の社員と共有することが重要です。
うまく機能しなければ人事部門と現場で採用したい人材の認識がずれてしまい、採用機会を逃すことにも繋がりかねません。そのような事態を防ぐためにも採用計画の立案と共有が大切といえます。
競合企業との差別化を図るため
近年、少子高齢化が進み労働市場が変化したことで、人材確保が難しくなり採用難に苦しむ企業が多くなっています。特に、大企業に比べて社会的知名度が低くなりがちである中小企業は、応募者が集まりにくいのが現状でしょう。
そのような中、各企業が採用計画を立案せずに採用活動を行っても、自社の望む人材を採用するのは難しいといえます。競合企業との差別化を図り、希望する人材を確保するためにも採用計画をしっかりと立てる必要があります。
母集団形成を効果的に行うため
採用計画を立てずに、段取りの悪い採用活動をしていては効果的な母集団形成を行えない可能性があります。自社が求める人材に合致する応募者を増やすためには、採用要件をあいまいにせず明確にした採用計画の作成が重要です。
採用計画を立てるメリット
では、採用計画を立てるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
採用成功率が上がる
まず、大きなメリットとして、採用成功率が上がることが挙げられます。採用計画を立てていく過程で、求める人物像を明確化してみましょう。
「どこの部署にどんなスキルを持つ人材が何人必要なのか」という具体的な項目を計画します。そうすることで、企業側が本当に獲得したい人材に対して効果的にアプローチでき、採用成功率を上げることに繋がります。
ターゲット像が明確になる
採用活動をスタートさせる前に、きちんとした「採りたい人物像」を明確化して、採用にかかわる全ての人と共有させることで、ミスマッチのない採用ができるようになります。
採用活動の進捗確認ができる
採用活動には予期せぬアクシデントがつきものです。採用スケジュールをきちんと戦略立てて計画しておけば、今回の新型コロナ感染のような事態が起きても、どこからどう巻き返しをすれば良いか早期に発見できるのも採用計画を立てる上でのメリットとなります。
人材管理や見直しにも繋がる
また、採用計画を立てることで、社内の人材管理や見直しにも繋がるでしょう。なぜなら、採用計画を立てる際には現在企業で働いている人員構成を把握する必要があります。
そのため、
- 「それぞれの部署に社員が何人いるのか」
- 「どのような仕事内容か」
- 「人的課題はあるのか」
など現在の人材状況を把握でき、その結果を踏まえて人材の適切な異動や配置にも活かせるでしょう。
採用計画の立て方5ステップ
採用計画を正しく立てるためには、5つのステップを踏む必要があり、正しい手順で進めていくことが大切です。以下で詳しく解説していきます。
- 採用人材の基本条件を洗い出し
- 採用人数の明確化
- 雇用形態の明確化
- 採用方法の明確化
- 採用スケジュールの明確化
採用人材の基本条件の明確化
採用計画では、採用する人材の基本条件を明確化しておく必要があります。「営業の経験が豊富」「コミュニケーション力が高い」といった抽象的なものではなく、業務経験やスキルをさらに具体的にすることで、企業が求める求職者の応募を増やすことに繋がります。
採用人材の基本条件を明確化するためには、採用ペルソナを設定することが重要になってきます。詳しい採用ペルソナの立て方、設定のやり方は以下の記事で詳しく解説しています。
「採用活動を行なっても、なかなか求める人材からの応募がない」「採用しても、すぐに会社を辞めてしまう」と頭を抱えている人事担当の方もいるのではないでしょうか。これは、自社の採用ペルソナが定まっていないことが原因かもしれません。 採用ペル[…]
また、採用する人材を明確化するために、人事部は現場と日頃からコミュニケーションをとり関係性を構築しておきましょう。そして、現場が求める人材や自社の強みに合う人材像を具体的に把握しておくことも大切です。
採用する人数の明確化
採用する人物が明確化した後は、企業にとって必要な人材の人数を算出し、何人採用すべきか、という点を明確にしていきます。人事異動も選択肢にしつつ、どこの部署に何人採用すのかを考えていきましょう。
適正な要員の算出方法には、トップダウン方式とボトムアップ方式があります。トップダウン方式は目標利益から、ボトムアップ方式は業務量から適した要因の数を導き出します。
雇用形態の明確化
採用人数が明確になった後は、どのような雇用形態で人材を採用するのか、という点を明確化する必要があります。正社員や契約社員などのほか、業務の一部を社外へ委託するアウトソーシングを視野に入れるケースもあるでしょう。以下ではそれぞれについて解説していきます。
正社員
正社員は採用計画を立てるうえで、中核を担ってもらいやすい雇用形態といえます。正社員は長期的に活躍することを視野に入れられるため、任せられる業務内容が広がるほか、人材育成のための投資も行いやすい点がメリットです。
契約社員
契約社員は正社員とは違い、あらかじめ労働期間を定めて労働契約を結び採用します。企業にとって契約社員は、人件費を抑えて採用できる点がメリットといえます。また、専門性の高い人材を一時的に採用したい場合などにも有効な雇用形態です。
派遣社員
派遣社員は事前に企業側が定めた期間、企業に派遣されて仕事を遂行する雇用形態です。派遣社員も契約社員同様、一時的に専門性の高い人材を確保しやすい点がメリットでしょう。
大きな違いは、企業側と直接雇用にある契約社員と異なり、企業が派遣社員ではなく派遣会社と雇用契約を結ぶ点です。
アウトソーシング
アウトソーシングは、企業の業務の一部を社外に委託するサービスです。業務を委託して企業側が報酬を支払うことで成立するため、雇用契約ではありません。しかし、新しい事業スタートの時など、一時的に業務量が増える場合に対応しやすい点がメリットです。
また、社員を新しく採用するよりコストも抑えられます。企業の状況に合わせてアウトソーシングの活用を検討してみるのもいいでしょう。
このようなお悩みをお持ちの方におすすめの記事です。 採用活動がうまくいっていない 採用業務を外注に依頼したい 採用アウトソーシングを導入したいが費用相場がわからない 本記事では、「採用代行(RPO)・採用アウトソ[…]
採用方法の明確化
採用する人数や雇用形態が決定した後は、採用方法を選定し明確にする必要があります。
少子高齢化に伴い、各企業の人材確保が厳しくなっている中、採用方法は年々多様化しています。求人媒体、人材紹介、SNS採用、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、採用方法はさまざまです。
例えば、即戦力になる人材を中途採用したい場合、直接スカウト可能なダイレクトリクルーティングを活用するなど、その時にほしい人材に合った採用方法を明確化します。それぞれの採用方法の特徴を把握し、かかるコストも考慮しながら決めていきましょう。
採用スケジュールの明確化
採用計画の内容を確実に実行していくためには、採用スケジュールを明確化する必要があります。その際、スケジュールは、中長期と短期の2つで考えていきましょう。
中長期のスケジュールは企業の課題や現状を整理して、企業目標実現に向け3~5年でするべきことを明確にして組みます。短期スケジュールは1年単位で組んでいきます。全体スケジュールのほか、募集開始から入社手続きまでの各タスクに分けて作成すると分かりやすいでしょう。
採用計画を立てる時のポイント
正しく採用計画を立てるためには、いくつかポイントを押さえておく必要があります。ここでは、そのポイントについて解説します。
採用計画を立てる前に下調べをする
正しい採用計画を立てるためには、事前に調査して準備をしておくことが大切です。リサーチする内容には、社会情勢や景気によって変化する求職者の動向や、競合企業の採用活動が挙げられます。
また、新卒採用の場合は、活動開始日などが定められた就活ルールについて把握しておくことも重要です。
現場社員との協力体制を確立する
採用計画を立案した後、内定者が配属される予定の部署と連携して協力体制を確立しておくことも大切です。採用スケジュールや実施する内容を、採用活動に関わる全ての人が共有しあえる環境に整え、役割分担などの認識を一致させておきましょう。
採用計画を意識的に見直していく
綿密な採用計画を立てたとしても、それが問題なく計画通りに行えるとは限らないため、意識的に見直していく必要があるでしょう。採用計画を見直す時期は、定期的に見直せるようあらかじめ期間を設定しておくとスムーズです。
募集を開始しているのにも関わらず定めた期間内に応募がない場合は、募集方法などが適していなかったと考えられます。問題点を改善するためにも採用計画は意識的に見直しましょう。
新卒採用と中途採用の違いを意識する
採用計画を立てるのに新卒採用と中途採用の違いを意識することもポイントです。
新卒採用の場合、一般的に採用対象者は学生で、社会経験が浅いという点に配慮する必要があります。社会経験やビジネスマナーの理解が浅いケースも考えられるため、研修などに時間がかかることも考慮して長期的な採用計画にします。
中途採用の場合は新卒採用とは違い、社会経験の少なさや基本的なスキルを心配する必要はなく、即戦力として期待できます。ただし、中途採用では採用対象者がまだ他社に在籍しているケースがほとんどといえます。そのため、採用対象者の前職状況を確認し、入社までの期間に余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。
採用計画は振り返りも大切!
採用計画を遂行した後は、採用計画の振り返りの実施も大切です。
振り返りのポイントとしては
- 「余裕のあるスケジュールを組めていたか」
- 「応募者とのやり取りにミスはなかったか」
- 「採用コストは適していたか」
- 「内定辞退した人の理由は把握できているか」
などです。しっかり振り返りを行うことで、今後の採用活動に反省点を活かすことができます。
このとき、採用代行(RPO)・採用アウトソーシングを導入していれば、振り返りを基に次年度の採用計画はどうすべきかまでも対応してくれるため、計画~振り返りまでの業務を自社で対応するのは時間的にも人数的にも厳しいといった企業の場合には、ぜひ採用代行・採用アウトソーシングの活用がおすすめです。
フォーマットやテンプレートを活用する
採用計画をスムーズに立案するためには、フォーマットやテンプレートの活用もおすすめです。採用計画のテンプレートは種類が豊富にあり、無料と有料どちらもあります。
例えばExcelの場合、採用計画に役立つテンプレートがあらかじめ用意されています。スケジュール表や管理表とも呼ばれるガントチャートや、分析シートなどを活用するのがおすすめです。
作成した採用計画を部内で共有したい場合は、Googleスプレッドシートの利用を検討するのもいいでしょう。Googleのアカウントがあれば誰でも利用可能で、スマホやパソコン、タブレットなど、どのデバイスでも作成できるのもポイントです。
各職種ごとの理想候補者像を具体的に描けるペルソナ設計シートです。
求めるスキルやキャリアパスを明確化し、採用戦略の強化に直結いたします。
シンプルながら柔軟にカスタマイズ可能なため、自社の採用プロセスに最適なツールとして実務に即した活用法も掲載しております。
まとめ
採用計画は、企業が円滑な採用活動を行うために重要な指針といえます。そのためには、社会情勢によって変化する求職者の動向や、競合企業の採用活動といった点を考慮しながら採用計画を具体的に立てる必要があります。
今回紹介したポイントなどを参考に、採用計画をしっかりと作成し、採用活動を効率的かつ効果的に行いましょう。
また、この記事を読んでも「難しそう」「自社でうまく採用計画が立てられない」とお悩みの場合には、採用コンサルティングを検討してみるのもおすすめです。どう計画を立てていけば採用成功に繋げられるか、親身になってアドバイスしてくれるでしょう。
採用コンサルティングサービス会社も世の中たくさんありますので、選び方のポイントなどを以下の記事で紹介しています。合わせてご参考ください。
「採用手法がマンネリ化し、改善の糸口が見つからない…」そんな悩みを抱える人事担当者は少なくありません。 限られたリソースで新卒・中途を同時に進めるなか、戦略的な採用活動の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。 そんなと[…]