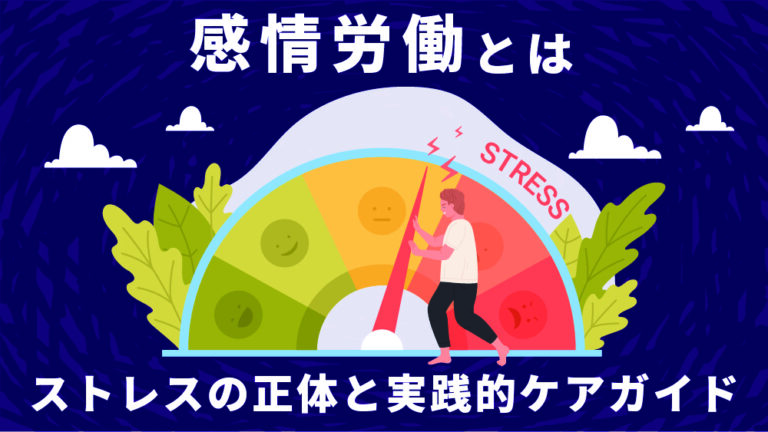「頭脳労働」や「肉体労働」に続き、第三の労働カテゴリーとして昨今注目されているのが「感情労働」です。感情労働では、ストレスなど精神的な不調が生じやすいとされており、企業は従業員のメンタルヘルスに関するケアをする必要があります。
しかし、実際にどのような影響を受けるのか、どのようなケアが必要なのかがわからない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、感情労働の定義をはじめ、メンタルに及ぼす影響やケア方法などを紹介していきます。いざというときに従業員を守れるよう、企業は感情労働に関する知識を蓄えておきましょう。
– 感情労働がストレスやバーンアウトにつながる仕組みとその影響が具体的にわかる
– 人事担当者として現場で実践できる感情労働への支援策やチェック方法がわかる
– 従業員のメンタル不調や離職の背景にある原因を深く理解したい中小企業の人事
– 社内で感情労働への理解を広げ、支援体制を整えたいと考えている管理職・労務担当者
感情労働とは?
まずは、感情労働について理解を深めましょう。感情労働の定義・背景や頭脳労働・肉体労働との違いなどを解説していきます。
感情労働の定義と背景|ホックシールドが提唱した概念
感情労働とは、仕事において自分の感情を良い方にコントロールし、相手に印象良く見られるよう振る舞う働き方のことです。
怒りや悲しみなどの感情を表に出さず、楽しみや喜びなどの前向きな感情を表現することが求められます。
1983年にアメリカの社会学者ホックシールドが、感情労働について「他者の感情状態を変化・維持することを目的とし、適切であるとみなす感情を声や表情あるいは身体動作によって表現し、そのために自分自身の感情を調整する労働」と定義しました。
頭脳労働・肉体労働との違い
冒頭でも説明したように、感情労働は、肉体労働、頭脳労働に続く、第三のカテゴリーとして注目されています。ここでは、感情労働と、肉体労働・頭脳労働との違いを解説していきましょう。
まず、肉体労働とは、ブルーカラーともいわれる、身体や体力を使ってする仕事を指します。
仕事をこなすために、自分の体や体力を調整し適切に活かすことが必要です。建設業や土木、農業などが肉体労働に当てはまります。
頭脳労働とは、ホワイトカラーともいわれる、頭を使ってする仕事を指します。企画や提案の質によって報酬を得る仕事です。
例えば、エンジニアや企画職、医師や弁護士などの専門職などが頭脳労働に当てはまります。
表層演技と深層演技がもたらす心理的負担とは
感情労働は、表層演技と深層演技の要素に分けられます。表層演技とは、TPOに応じて求められる表面的な行動を変化させることです。例えば、作り笑顔や愛想笑い、お辞儀などを指します。
自分の感情を押し込めることもあるため、ストレスを感じる方もいるでしょう。
深層演技とは、求められる表面的な行動と、自身の内面的な感情があたかも同じように振る舞うことです。
例えば、対応が難しいお客様やクレーマーに対して、笑顔で接客し適切な対応をすることなどが挙げられます。内面的な感情と外面的な表情を合わせる必要があるため、無意識のうちに疲弊する方もいるかもしれません。
感情労働が求められる主な職種

では、感情労働が求められる職種とは何なのでしょうか。ここでは、感情労働が必要な主な職種について解説していきます。
感情労働が多い対人サービス業とは
感情労働が特に求められるのは、接客や顧客対応など、人と接する機会の多い対人サービス業です。
具体的には、以下のような職種が挙げられます。
-
飲食店スタッフ
-
販売員
-
ホテルスタッフ
-
客室乗務員
-
コールセンター職員
これらの職種では、たとえ自分の感情がネガティブであっても、常に笑顔や丁寧な対応を保ち、顧客に良い印象を与える必要があります。
そのため、自分の本音を抑え、業務として感情を演出する負担が大きくなりやすいのが特徴です。
看護・介護・教育など専門職の感情労働
医療や福祉、教育の現場でも、感情労働は重要な役割を果たしています。
たとえば、看護師や介護士は、専門的なスキルだけでなく、患者や利用者との信頼関係を築くために、思いやりのある態度や穏やかな声かけが求められます。
患者に寄り添う姿勢や安心感を与える言動は、治療効果やサービス満足度にも影響を与える重要な要素です。
教育現場においても同様に、教師は知識を伝えるだけでなく、生徒の悩みに寄り添ったり、モチベーションを引き出したりする必要があります。
生徒の前では常に冷静さややさしさを保ち続ける必要があり、精神的なエネルギーを使う場面が多くなります。
感情労働に向いている人・向いていない人の特徴
感情労働は、自分の真の感情をコントロール、または抑える必要があるため、精神的なストレスを感じやすい人もいます。
感情労働に向いている人
感情労働に向いている人には、以下のような特徴があります。
-
感情労働そのものにやりがいを感じられる
-
高いコミュニケーション能力を持っている
-
気持ちの切り替えが早く、オンオフを明確にできる
-
相手の立場に立ちつつも、自分の感情をコントロールできる
たとえば、理不尽なクレームに対しても冷静に対応できる人は、感情労働に適しているといえるでしょう。
感情労働に向いていない人
一方で、感情労働に向いていないとされる人の傾向は以下の通りです。
-
共感力が非常に高く、相手の感情に引きずられやすい
-
感情を抑えるのが苦手で、表情や態度に出やすい
-
他人の言動に敏感に反応してしまう
-
長時間の対人対応で強い疲労を感じる
こうした特徴を持つ人は、感情労働の負荷によってストレスを抱えやすく、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクも高まります。
感情労働によって引き起こされるストレスの種類
感情労働に従事する人は、業務上の対応で無理に感情を抑えたり、作り笑顔を見せたりすることが少なくありません。
このような感情の使い方が、知らず知らずのうちにストレスの蓄積につながることがあります。
表層演技と深層演技がもたらす心理的負担
感情労働では、「表層演技」と「深層演技」の2種類の演技が存在します。
-
表層演技:自分の感情に反して、表面的に笑顔や丁寧な態度を装うこと
-
深層演技:相手や状況に合わせて、感情そのものを調整しようとすること
どちらの演技も、自分の本当の感情を抑える必要があり、ストレスの原因になりやすいです。
特に表層演技は、自分の内面と外面の乖離が大きく、「自分を偽っている」感覚が続くことで、心理的疲労を引き起こすことがあります。
実際の業務で感じやすいストレスの例
感情労働では、業種を問わずさまざまな場面でストレスが生じます。以下はその代表的な例です。
■ よくある感情労働のシーン
-
接客業
理不尽なクレーム対応時に怒りや不快感を抑え、笑顔で丁寧に対応しなければならない。 -
看護・介護職
患者や利用者に安心感を与えるために、自身の体調や感情にかかわらず穏やかな対応が求められる。 -
教師・教育職
生徒の気分や状況を汲み取りながら授業を進める必要があり、常に神経を使う。 -
営業職・カスタマーサポート
厳しい要求や高圧的な態度の相手に対しても、冷静で建設的な対応を求められる。
このような業務では、本音と建前のギャップを日常的に演じることがストレスとなり、やがて慢性的な疲労や心理的疲弊へとつながっていきます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)という言葉をご存じでしょうか? 仕事に意欲的だった従業員が突然やる気をなくしてしまうことをバーンアウトといいます。今回の記事では、社会人ならだれでも陥る可能性があるバーンアウトの症状や、なりやすい人の特徴[…]
感情労働がメンタル不調や離職に与える影響
感情労働によって生じるストレスは、一時的な疲労にとどまらず、長期的に心身へ悪影響を及ぼすリスクがあります。
特に近年では、感情労働が原因となって、メンタル不調や離職に至るケースも増えています。
感情労働とバーンアウトの関係
感情労働は、業務の中で「常に自分を抑える」必要があるため、人によっては深刻な精神的ストレスを抱えるようになります。
その結果として起こりやすいのが、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」です。
バーンアウトは、仕事に意欲的だった人が突然やる気を失い、精神的・肉体的に限界を迎える状態です。
燃え尽き症候群(バーンアウト)という言葉をご存じでしょうか? 仕事に意欲的だった従業員が突然やる気をなくしてしまうことをバーンアウトといいます。今回の記事では、社会人ならだれでも陥る可能性があるバーンアウトの症状や、なりやすい人の特徴[…]
企業が注意すべきストレス対策の重要性
感情労働に伴うストレスは、従業員個人だけでなく、職場全体の生産性や定着率にも影響を及ぼします。
そのため、企業や管理職は、従業員が抱える負担に早期に気づき、メンタルヘルス対策や職場環境の改善に取り組む必要があります。
特に以下のような状況が見られる場合は注意が必要です。
-
長時間の対人対応が続く
-
自由な感情表現が制限されている
-
就業時間外も対応を強いられている(例:リモートワーク・休日対応)
実際にあった中小企業でのバーンアウト事例
実際の企業現場でも、感情労働によるストレスが深刻な問題となっています。
ある中小企業では、就業時間外の業務対応が常態化しており、従業員の睡眠の質が低下。十分な休息が取れず、体力や集中力が回復しにくい状態が続いていました。
その結果、ミスの増加や判断力の低下、ストレス耐性の低下といった悪影響が見られるようになり、複数の従業員がバーンアウトに陥る事態となりました。
業務パフォーマンスの低下だけでなく、従業員の仕事への意欲やエンゲージメントも著しく低下し、最終的には離職者が相次ぐ結果となったのです。
人事ができる感情労働の対策とケア方法
感情労働による精神的不調やバーンアウトを防ぐには、適切な対策とケアが必要です。ここでは、人事ができる感情労働の対策とケア方法を紹介していきます。
制度・評価・業務設計からのアプローチ
「目的が見失われて機能していない制度があるが、ルールとして従っている」という企業もあるでしょう。
形骸化した制度は、従業員にとってストレスになりやすいため、現状に合わせて適切に見直すことが大切です。
また、感情労働は高いコミュニケーション能力が求められる一方、その能力は個人の特徴や性格によるものと判断されやすく、適切に評価されない場合があります。
そのような評価制度を見直すことも、従業員の不満やストレスを減らすことにつながるでしょう。
加えて、煩雑な業務設計は、対応する人のストレスとなります。適切な業務設計に見直すことで、ストレスや負担を軽減できるでしょう。
人事評価制度が活かせているかいまいち実感がなかったり、従業員に会社の方針が浸透していないのではと感じたりしませんか? せっかく運用している人事評価制度も、従業員のモチベーション向上や会社の成長に活かせていなければ意味がありません。 […]
面談・1on1での対話で早期発見する方法
定期的な面談や1on1での対話では、従業員が抱える不満やストレスの早期発見につながります。また、「相談できる場がある」という事実も、従業員にとって安心材料となるでしょう。
面談・1on1での対話は、問題の早期発見・解決だけでなく、従業員との信頼関係の構築やモチベーション向上にも役立つとされています。
研修やセルフケア支援を制度化するには
従業員が感情労働により疲弊するのを防ぐには、仕事で求められるコミュニケーション能力やストレスに対応する力、日常的なセルフケアの方法などが習得できる研修が必要です。
これら研修や支援を制度化するには、導入する目的や背景を周知させ、実際に運用した結果を社内に伝えることが大切といえます。
人事向け:感情労働ケアに活かせるチェックリスト

ここでは、人事担当者にぜひ利用してほしい、感情労働のケアに活かせるチェックリストを紹介していきます。
現場社員に使える簡易チェックシート例
ここでは、現場社員に使える管理チェックシートの一例を紹介していきます。
《仕事について》
- こなさなければならない仕事がたくさんある
- 仕事が時間内に終われない
- 勤務中はいつも仕事のことで頭がいっぱいだ
- かなり注意して業務をこなさなければならない
- 働きがいのある仕事だと感じる
《自身について》
- 生き生きとしている
- 怒りを感じている
- 疲れている
- 不安がある
- 集中しにくい
回答については、1〜4段階程度から選択できるように作成するのがおすすめです。また、ストレスに関するチェックシートは、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
管理職に共有すべき観察ポイント
感情労働によって、部下が他人には言えない疲れや誰にも気づかれないようなストレスを抱えていたとしても、ぱっと見では判断しづらいものです。
そのため、管理職の社員には、部下の業務に感情労働の要素がどの程度含まれるかを観察するよう共有する必要があります。
管理職や上司が感情労働について理解を持つだけでも、部下の気持ちや仕事に対するモチベーションは変わるとされています。
社内で感情労働を話しやすくする工夫
社内で感情労働について話しやすくするには、帰属意識を高めることが大切です。帰属意識とは、会社や組織に対して愛着を持ち、心理的なつながりを感じることを意味します。
会社や組織に対して愛着や心理的つながりを感じられれば、感情労働によるストレス・悩みを打ち明けやすくなるでしょう。
社内のコミュニケーションが活性化し、感情労働による疲弊や負担の早期発見・解決が期待できます。
まとめ|感情労働の理解と職場改善の第一歩
自身の感情をコントロールして行う感情労働は、なくてはならない仕事といえる一方で、ストレスや負担を感じやすい仕事です。
企業や人事担当者は感情労働に対してよく理解した上で、定期的なストレスチェックや面談を通して、従業員のバーンアウトや精神的不調を防ぎましょう。
まずは、従業員の本音を聞き出すことが大切です。従業員が安心して相談できるよう制度や環境を整えることから始めましょう。
近年では、「メンタルヘルス」という言葉を耳にする機会も増えました。厚生労働省によると、メンタルヘルス不調者が休職・退職している事業所は年々上昇傾向にあるという調査結果もあります。 従業員の心の健康を守り、定職率を上げるためには、企業の[…]