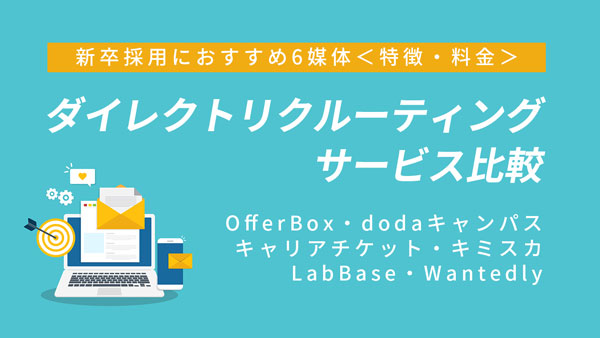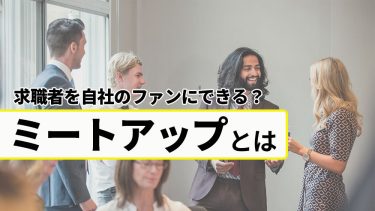「せっかく求人を出しても学生からの応募が少ない…」 「説明会を開いても反応が薄く、なかなか次につながらない…」 「大手企業と比べると、どうしても魅力をうまく伝えきれない気がする…」
そんな課題を感じていませんか?
今の学生たちは「安定」や「お給料」だけでなく、働きやすい環境や成長のチャンス、社会とのつながりなど、より幅広い視点で企業を見ています。
ところが、企業側の伝え方がその価値観とずれてしまうと、本来の魅力が十分に伝わらず、採用活動に苦戦してしまうケースも多くあります。
本記事では、学生が今、どのような点を重視しているのかを紐解きながら、中小企業ならではの強みを効果的に発信する方法や、実際の採用成功事例をご紹介します。
この記事を読むことで、自社の魅力をより的確に届け、採用成果を高めるヒントが得られます。
– 中小企業が訴求すべき魅力とその具体的な伝え方がわかります
– 採用成功事例を通じて実務に活かせる改善策がわかります
– 中小企業として限られたリソースでも効果的な採用広報を行いたいと考えている採用担当者
– 学生が企業を選ぶ際に何を重視しているのか、実務に役立つ情報を探している方
学生が企業を選ぶときに重視するポイント
学生が企業選びを行う際に重視しているポイントとはどこなのでしょうか?ここでは、いまどきの学生の企業選定ポイントについて解説していきます。
学生が注目している会社選びの基準

画像引用:マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査
就活生の企業選択のポイント1位は、7年連続で「安定している会社」となっており、学生は企業に「安定」を求めています。
同様に「給与の良さ」も選考理由として重視される傾向が高まり 、近年の物価高への経済的不安が大きいことが読み取れます。

画像引用:マイナビキャリアリサーチLab 2026年卒大学生就職意識調査
一方で、仕事に対して「楽しく働きたい」「個人との生活と仕事を両立させたい」と考える学生は依然として多く、引き続き多くの学生がワークライフバランスを重視している状況です。
「収入さえあればよい」と回答する学生も年々増加しており、ここでも経済面での安定を求める傾向が読み取れます。
つまり、今の学生は「経済面での安定」「働く上での精神的な安心感、生活との両立のしやすさ 」の両立を求めており、企業規模やブランド力だけが「安定」ではないと考える傾向が強まっています。
こうした背景を踏まえると、中小企業であっても人間関係や福利厚生、柔軟な働き方、制度など、学生が安心して働ける環境を打ち出すことが学生の志望度を高める重要な手掛かりになります。
企業選びで重視されるランキング上位の項目
そのほか、学生はどのような点を重視して企業選びをしているのでしょうか。就活生対象のアンケート結果の上位は、以下の通りです。
- ワークライフバランス・柔軟な働き方
- 充実した福利厚生
- 働きやすい環境・雰囲気
- 成長できる環境
- 給与・待遇
就活生が企業選びで重視するポイントは、多面的になっています。
まず「ワークライフバランス・柔軟な働き方」は、私生活や将来設計を犠牲にせず安心して働ける点が評価されます。次に「充実した福利厚生」では、住宅手当や育休、奨学金返済支援など生活を支える制度への期待が大きいです。
さらに「働きやすい環境・雰囲気」も重視され、社風や人間関係が合うかどうかが、心理的安定に直結します。加えて「成長できる環境」も重要で、研修制度や挑戦機会がある会社は、キャリア形成を後押しできると映ります。
最後に「給与・待遇」も依然として大切ですが、それ単体ではなく上記の環境要素とあわせて評価される傾向にあります。
つまり、学生が考える安定は経営基盤の堅さ以上に、働きやすさや成長性、生活の安心を支える総合的な環境にあります。
文系・理系で異なる重視ポイント
さらに企業選びのポイントは、文系学生と理系学生で少し異なるようです。

文系学生・理系学生ともに企業選びの際に最も重視しているのは、「ワークライフバランスが確保できる」ですが、給与と志向の優先順位が異なります。
ワンキャリア「2026年卒 就活実態調査」では、文系学生は「自分のやりたい仕事・職種につけるか」を非常に重視しており、給与や福利厚生よりも自己実現の観点が強く表れています。
一方で理系学生は、「給与水準」「福利厚生」といった待遇面の安定性を重視する傾向が高く、研究や専門スキルを活かした仕事で安定的にキャリアを築ける点を重んじています。
つまり、文系は「やりがい・興味との合致」、理系は「待遇や将来の安定感」をより強く求める構図です。この違いを理解した上で、企業は自社の魅力を学生の志向に合わせた形でアピールすることが効果的だといえます。
学生の企業選びに影響を与える価値観の変化とは?
ここまで、近年の就活生の企業選定ポイントは「安定」であることで、「安定」とは企業の経営基盤ではなく以下の点が軸になっていることをお伝えしてきました。
- 働き手の心理的安心感
- 福利厚生
- 成長機会
- 働きやすさ
- 自分らしさの尊重
では、なぜ学生が「安定」を求めるようになってきたのでしょうか。企業選定ポイントを左右する、イマドキ学生の価値観の変化について解説します。
「ワークライフバランス」重視の定着

マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒大学生就職意識調査」の就職観の推移アンケートによると、「個人の生活と仕事を両立したい」が3年連続で増加しています。

反対に、「行きたくない会社」についてのアンケートでは、「転勤の多い会社」が5年連続で増加しており、勤務地や柔軟な働き方が、応募判断の重要な要素になっています。
背景として、近年の学生は生活の「安定」を求める傾向にあることや、コロナ禍を経験しオンラインでのやり取りに慣れた世代であること、共働き志向が上昇していることなどが挙げられます。
画像引用:マイナビキャリアリサーチLab 2026年卒大学生就職意識調査
「給与・待遇」意識の強まり
前述した「給与の良さ」の上昇傾向に関して、「収入さえあればよい」と考える学生が徐々に増えていることもアンケートから読み取ることができます。
物価高や初任給引き上げの影響で、待遇差が志望動機に直結していると考えられます。

画像引用:マイナビキャリアリサーチLab 2026年卒大学生就職意識調査
さらに、近年の情勢を受けて、企業規模にかかわらず、初任給引き上げを行う、または検討すると回答した企業は半数以上で、増加傾向にあります。
大手のみでなく中小企業も初任給引き上げを検討しており、給与改善が企業への関心や志望度の向上につながる可能性もあります。
「中小企業志向」の拡大

画像引用:マイナビキャリアリサーチLab 2026年卒大学生就職意識調査
企業の経営基盤ではなく、労働環境・生活環境の「安定」を求める価値観と、それに伴い転勤や長時間労働を嫌う学生が増えた結果、中小企業志向が高まりつつあります。
企業志向についてのアンケートを見ると、中小企業志向は43%になっています。さらに、中小企業を志望する学生も前年度比1.9%増となっています。
待遇条件が改善すれば中小でも挑戦可能と考える学生が増えており、採用戦略において差別化ポイントの提示をすることが有効です。
中小企業に対する学生のリアルな不安

中小企業に関心はあっても、「中小企業に就職を決めてしまってもいいのだろうか。」といった学生の悩みは尽きません。多くの学生が抱える中小企業に対する不安について紹介します。
「成長できないのでは?」というキャリア不安
学生が中小企業に対してよく抱く第一の不安は、「自分が十分に成長できないのでは」というキャリア面での懸念です。
大手企業と比較すると研修制度や教育体制が整っていないのでは?とイメージされがちで、「社会人としてのスキルが磨けずに将来のキャリアが限定されてしまうのでは」と考える学生は少なくありません。
しかし実際には、中小企業の多くは幅広い業務に関わる機会があり、若手のうちから責任ある仕事を任されることも多いのが特徴です。
この不安を解消するためには、OJTでの育成の具体例や資格支援・外部研修導入などをわかりやすく発信することが大切です。
経営の安定性・将来性に不安を感じやすい
次に挙げられるのは、「会社が長期的に安定しているのか」という不安です。
「中小企業は大手と比べて経営基盤が弱いのでは?」「業界の先行きで将来が不透明では?」という懸念がどうしても浮かびやすいのが実情です。
特に学生や保護者は、「倒産リスク」に敏感であり、就職後に安心して働けるかどうかを重要視しています。
この不安を払拭するには、財務の健全性や成長戦略をわかりやすく発信することや、地域や取引先との長年の信頼関係を紹介することが効果的です。
さらに、社員インタビューや業界の将来展望を交えれば、学生が「将来性が見える会社」と感じやすくなります。
職種やキャリアパスの選択肢が少ないのではという不安
中小企業に対しては「配属の幅が狭く、多様なキャリアを築けないのでは」という不安を持つ学生もいます。
大手企業に比べて部署や職種の数が限られることは確かにありますが、逆に一人ひとりの裁量が大きく、複数の業務を横断的に経験できる点は中小企業ならではの強みです。
この不安を和らげるには、実際に幅広い業務経験を積んでキャリアを伸ばした若手社員の事例を紹介することが有効です。
また、「ジョブローテーション制度」「社内公募制度」「外部研修や資格取得の支援」などを導入したり、発信したりすることで、キャリアの選択肢が可視化され、学生にとって安心につながります。
中小企業が学生から選ばれるために必要な打ち出しポイント
中小企業が採用で選ばれるためには、大企業との比較で不利になる点を補うのではなく、自社しか持たない強みを明確に示すことが重要です。
大企業にない「やりがい」や「成長実感」を伝える
多くの学生は「自分が役立っている実感」や「社会に貢献している感覚」を求めています。
中小企業は人数が限られる分、一人ひとりが担う役割が大きく、成果が会社全体に直結するため、日々の業務の中で、やりがいや、成長実感を得やすい環境です。
大企業では数百人が関わるプロジェクトの一部しか経験できないこともありますが、中小企業では最初から中心メンバーとして業務を任されるケースも多いのが強みです。
採用広報では事例を交えて「自分の成長が見える」「挑戦できる環境がある」と伝えることが、学生の共感を得るうえで効果的です。
若手社員の活躍や裁量の大きさを伝える
学生が不安を抱くポイントのひとつは「本当に若手でも活躍できるのか」ですが、中小企業は年次に関わらず裁量の大きな仕事を任せる風土があります。
そのため20代でも企画・営業・新規プロジェクトなど、会社の成長を左右する役割を担うことが可能です。採用広報では、実際の若手社員の経験談やキャリア事例を紹介し、リアルな声を伝えることが効果的です。
「入社1年目から〇〇を任された」「若手が主体となって新規サービスを立ち上げた」といったストーリーは学生にとって強いインパクトがあります。
年次を問わず成長できる環境と、自分らしいキャリアを描ける可能性を示すことが重要です。
中小企業ならではの社会貢献や地域密着性も打ち出す
大企業が全国的・グローバルなスケールで事業を展開する一方、中小企業は地域や業界に深く根ざし、直接的に人や社会に貢献できる点が特徴です。
たとえば「地域の企業や住民を支える仕事」「地場産業を未来につなぐ取り組み」など、働く意義を実感できるエピソードを発信することで学生からの共感を高められます。
また、中小企業は経営者や社員同士の距離が近いため、自分の意見や行動がダイレクトに会社や地域に還元される感覚を得やすいのも魅力です。
採用広報では、地域との関わりや社会課題への取り組みを具体的に示し、「規模は小さくても地域社会や業界の中で、重要な役割を果たしている企業 」であることを印象づけましょう。
企業が採用情報を発信するための主な手法
下記アンケート結果のように、学生はナビサイト以外にもスカウト型や説明会でも企業情報を収集しています。

画像引用:人事ZINE 【25・26卒】就活生が企業に求めるものに関する意識調査アンケート|夏期インターンの希望は?
就職ナビサイト
冒頭では、大手就職ナビサイト以外で情報収集する学生が増えてきていると紹介しましたが、学生が就職活動で主に使うものとしては、やはり大手就職ナビ媒体が挙げられます。
26卒の登録学生数を見ると、マイナビで約60万人、リクナビで43万人(2025年3月)となっているので、就職活動を行うほとんどの学生がナビ媒体を活用している現状です。
ここで発信すべきものとしては、基本的な企業情報から実際の仕事内容の流れなどの幅広い情報を掲載することが重要になります。
自社ホームページ
自社ホームページも学生が重要視するものとなっています。BtoCや知名度の高い企業であれば、直接学生がHPから情報収集することも考えられます。
しかし、BtoBや知名度が低い企業など、学生からの認知を得ることが難しい企業であれば、ナビサイトにURLを記載するなど、自社ホームページへの導線を多く設置することがポイントです。
逆求人型の就活情報サイト
ここで指している逆求人型の就活情報サイトは、DR(ダイレクトリクルーティング)サイトで、企業側から学生へスカウトを送るツールです。
認知していない学生へスカウトを送る際は、先ほど紹介した学生が求めている情報と組み合わせて、自社のアピールポイントを記載することが大切です。
【新卒】ダイレクトリクルーティング比較6選
OfferBox・キミスカ・dodaキャンパス・キャリアチケット・LabBase・Wantedly
オウンドメディア
ここでいうオウンドメディアは、ウェブサイトや自社ブログ、パンフレットや広報誌も含まれます。
ウェブサイトや自社ブログでは、エントリー後の学生に対し、より細かい情報を伝達するものとして効果的です。また、パンフレットや広報誌は、直接学生に魅力を訴求するものではなく、学生の親に対しても安心感を与えます。
採用オウンドメディアのメリット・デメリットや、始め方、成功事例についてこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
オウンドメディアは会社のブランティング、プロモーションを行いながら、集客や会社のファンを増やすことができる企業独自のメディア(媒体)です。中でも求職者をメイン読者ターゲットとしたオウンドメディアを、採用オウンドメディアと呼びます。 今[…]
メールマガジン
一度だけ接触するのではなく、定期的に情報を伝えることのできるものがメールマガジンです。
これはエントリー増加を図るものではなく、エントリーしてくれた学生へ、自社の魅力訴求を行うものとして有効策となっています。
学生のフェーズに合わせて発信する内容を変えることで、志望度や入社意欲を高めることが可能です。
動画メディア(YouTube・TikTok)
就職活動中の学生含め、多くの若者が利用している動画サイトでも企業の情報発信は求められています。
文章だけでは伝わりにくい企業の魅力やリアルな雰囲気を伝えやすい点がメリットで、ブランディングとしても効果的です。
YouTubeやTikTokでは、企業情報のようなものではなく、実際に働いている社員や会社自体の雰囲気が分かる動画を発信するのがおすすめです。
YouTubeを採用活動に利用するメリットや成功事例など、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
コロナ禍での採用活動に苦戦を強いられているという企業も多い昨今、Youtubeを活用した採用活動が新たなスタンダードとなるかもしれません。採用活動のオンライン化が急激に進み、Youtubeに採用動画をアップする企業が増えています。 本[…]
SNS
SNSに関してはTwitterやInstagram等が主流です。
YouTube・TikTok同様に多くの若者が利用するツールであり、企業ホームページや就活ナビサイトなどでは分からないような企業の情報を得たいと考える学生が多く、SNSではよりリアルな意見が得られることから、情報収集源として学生から重宝されています。
また、メールマガジンと同じく、学生のフェーズに合わせてSNSで発信する内容を変えることで志望度や入社意欲を高めることが可能です。
Instagram採用について気になる方は、始め方や注意点を紹介しているこちらの記事を参考にしてください。
Instagramとは、SNS大手Facebook社が買収した、写真や動画をシェアできる著名なSNSサービスです。「インスタ映え」という言葉の流行りとともにユーザー数は現在3300万人を超えました。 今回は、日常の「映え」写真を知人同[…]
採用関連のイベント
各媒体で行われているイベントに参加している学生は、就職活動に対して意識が高く、選考参加率も高いため、いかに本選考に進んでもらえるかが重要です。
ここで学生が求めている情報としては一般的なものではなく、詳細な業務内容や企業理念等の企業の特徴が分かるような情報です。
採用イベントの一つである「ミートアップ」のメリットとデメリットについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
ミートアップというワードを聞いたことがある人は少ないのではないでしょうか。 最近では、このミートアップを採用に活用している企業が増えています。そこで今回はミートアップについて、採用に取り入れるときのメリット・デメリット、導入企業事例な[…]
会社説明会や採用サイトに盛り込むべき情報とは?
採用活動の成否を左右するのは、学生が知りたい情報をナビサイトや会社説明会でどれだけ具体的に発信できるかです。特に「働く日常」や「福利厚生」など、安心して将来を描けるリアルな情報が求められています。
1日の仕事の流れ
仕事内容や勤務時間の実態は、学生が特に関心を持つポイントです。

画像引用:No Company Z世代就活生のSNS活用に関する実態調査
No Companyが行った調査によると「働くイメージが湧く情報」を重視する傾向があります。
また、情報発信のフォーマットに関して「パッと目を引く」「短時間でポイントがつかめる」 など、テキスト以外の視覚的、聴覚的に把握しやすいフォーマットでの情報発信を望む学生が多いというアンケート結果も出ています。
魅力訴求方法として、説明会での1日のスケジュール紹介や採用サイトでの具体的なタイムライン表示が効果的です。
例えば「出社~退勤」までの時系列や業務内容の割合を図解すると、学生は自分が働く姿をイメージしやすくなります。部署別や職種別に複数の事例を用意するとさらに訴求力が高まります。
福利厚生
学生にとって福利厚生は「安心=安定」の象徴です。住宅手当、育児休暇、奨学金返済支援、リモートワーク制度など生活設計に関わる支援制度があるかは大きな判断軸になります。
説明会やサイトには具体的な制度内容だけでなく、実際に利用している社員事例を載せると説得力が増します。
特にZ世代に該当するイマドキ就活生は、「ライフイベントとキャリアを両立できるか」を重視するため、安心感を与える紹介が重要です。
オフィス環境・設備の紹介
学生は「働く場の雰囲気」から会社との相性を判断する傾向があります。オフィスデザイン、社内設備、休憩スペース、カフェテリアやリモートワーク環境といった情報を写真や動画で伝えると効果的です。
また、オフィスの清潔さや最新設備の充実度は、心理的な働きやすさの判断材料にも直結します。採用サイトでは「オフィスツアー動画」や「設備紹介ページ」を設けると学生が安心して応募を検討できます。
先輩社員のインタビュー記事・動画
学生が最も信頼する情報源の一つは「実際の社員の声」です。仕事内容や入社理由、やりがい、職場の雰囲気などを語るインタビューは、自分の将来像を投影する大きな材料になります。
説明会では社員が直接登壇し質問に答える場を設けたり、採用サイトには記事や動画を掲載し、職種ごとのリアルな声を紹介したりが有効です。
形式的ではなく「失敗から学んだ経験」なども盛り込むと、より共感を得やすくなります。
社内のキャリアステップ具体例
就活生は「成長できるか」を大きく意識しています。採用サイトでは入社後3年~10年のキャリアモデルを図示し、各段階の仕事内容や役割の変化を分かりやすく示すと安心感に繋がります。
説明会では実際にキャリアを積んだ社員の事例を紹介し、研修制度や挑戦機会と合わせて伝えるのが効果的です。
Z世代は、努力がどう評価されるのか、キャリアにどうつながるのかの具体的なイメージ 、を重視するため、具体的なロードマップが響きます。
学生に選ばれた中小企業の成功事例

知名度で勝負できない中小企業だからこそ、採用戦略が必須です。実際に学生に選ばれている中小企業の採用戦略や、採用ブランディングの成功事例について紹介します。
採用メッセージを刷新してエントリー数が4倍になった事例
<課題>
大手競合と比べて知名度が低く、学生からの応募が思うように集まらないことが課題でした。
<取り組み・工夫>
採用メッセージ内で「売上成長力」を前面に打ち出し、自社独自の成長ストーリーを訴求しました。加えて「巻物型パンフレット」などの斬新なツールを活用し、他社との差別化を図りました。
<成果・成功ポイント>
その結果、エントリー数は従来の約300名から13,000名へと4倍以上の大幅増加に成功しました。大手と比較されても強みが明確に響く設計が成果を後押ししました。
経営理念の確立とリアルの発信で内定承諾率アップ
<課題>
企業文化や働く環境のリアルな姿を伝えきれず、なかなか内定承諾につながらないことが課題でした。
<取り組み・工夫>
ともに自社を作り上げていく人材を採用するために、明確な経営ビジョンと理念を発信しました。さらに、学生が自身のキャリアと今後の人生を考えられるように、採用イベントを開催しました。
<成果・成功ポイント>
企業の思いをしっかりと伝えることで学生の共感を得られ、内定承諾率の向上に結びつきました。リアルな情報提供により、入社後のミスマッチ防止にもつながり、会社の理念や目指す姿に共感してくれる「質の高い学生」を4名採用することができました。
InstagramとYouTubeで企業の雰囲気を可視化した成功例
<課題>
地方中小企業で通常の求人媒体では応募が集まらず、人材採用に苦戦中。
<取り組み・工夫>
Instagramを採用広報チャネルとして新規に立ち上げ、「社員の日常」 「職場の雰囲気」 「仕事内容紹介」など、求人票だけでは伝わらないリアルな情報を中心に採用情報を発信しました。
自社での投稿だけでなく、ターゲット層に届くように「ハッシュタグ」「投稿のタイミング」「写真・動画の見栄え」に工夫を加えました。
<成果・成功ポイント>
「求人媒体では伝わらない日常感・社風をSNSで直接発信できたこと」および「視覚的で直感的な訴求が可能なInstagramを活用したこと」により、運用開始からわずか2ヶ月で応募40件を獲得しました。
広告費をかけずに効果が得られたため、地方の中小企業における「低コスト採用手法」として有効性が証明されました。
まとめ
この記事では以下のポイントをお伝えしました。
- イマドキの学生は「安定」を重視して企業選びを行っている
- 「安定」とは、柔軟な働き方や働きやすさ、自己実現可能な環境、給与を含むワークライフバランスが整っているかどうかである
- 中小企業が採用戦略において差別化するためには、自社ならではの強みを明確に打ち出す必要がある
- 情報発信はテキストベースではなく、一目で見てわかりやすい画像や動画で発信すると効果的
この記事が貴社の採用活動の一助となれば幸いです。
自社の魅力をいかに伝えるか、どう工夫していくのかは採用担当者の頭を常に悩ませる部分です。
学生の企業選びのポイントを理解したうえで、どのように採用活動に反映させていくのか、説明会やイベントでの魅力訴求方法ついては以下の資料にて紹介しているので、合わせてご覧ください。
資料ダウンロードはこちらから