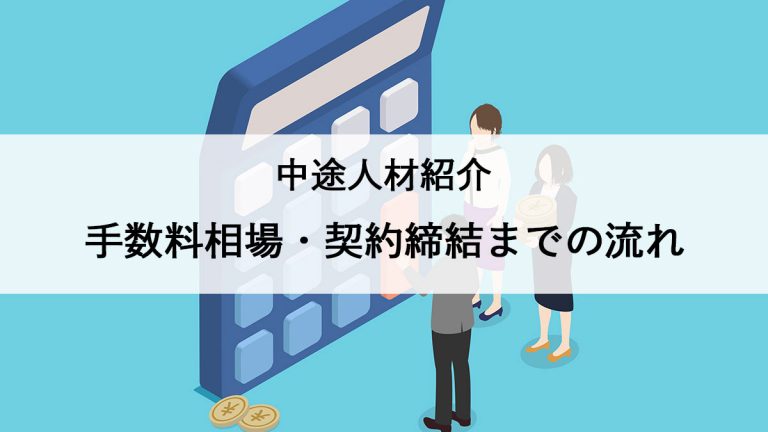人材紹介を利用したいけど「手数料の相場が分からない」「紹介会社の選び方に不安」と悩んでいませんか?本記事では、手数料の基本知識、成功報酬の仕組み、相場感、選ぶべき会社の特徴などを簡潔に解説します。
採用担当として複数社を比較・利用してきた経験を基に執筆しています。読まずに契約を進めると、不当な手数料や早期離職による損失リスクもあります。
本記事の結論は「手数料相場と契約条件を総合判断し、信頼できる紹介会社を選ぶことが成功のポイント」です。ひとことで言えば「人材紹介の賢い使い方を学べる記事」です。コスト、リスクを減らす参考になれば幸いです。
– 主要な人材紹介会社の手数料体系や返金規定の違いが比較できる
– 手数料交渉や返金規定確認の実務的なポイントがわかり、実務に役立てられる
– 人材紹介の費用を比較検討して、コストパフォーマンスの良いサービスを選びたい人
– 手数料交渉や返金規定のポイントを押さえて、実務に活かしたい人
人材紹介の手数料相場
新卒人材紹介サービスの手数料相場は、1名あたりおよそ100万円前後です。中には50万円程度の低価格なサービスもありますが、希少価値の高い理系学生や、高学歴・スポーツ系の学生などは紹介料が高くなる傾向があります。
中途人材紹介サービスの場合は、報酬を理論年収の30〜35%に設定しています。理論年収とは、入社する人が年度のはじめから1年間在籍したと仮定した場合の年収です。
紹介手数料はこの理論年収に基づいて算出されます。求人票に記載する「想定年収+想定賞与」を合算した額を基準に考えると分かりやすいでしょう。
新卒と中途どちらも、料金体系は成功報酬型が主流で、内定承諾や入社が決まってから費用を支払うため、初期費用はかかりません。
また、万が一辞退者が出た場合でも返金対応を行う会社が多く見られます。このようにリスクを抑えつつ優秀な人材を確保できるため、コストパフォーマンスに優れた採用手法として注目されています。
人材紹介の手数料の種類
人材紹介の手数料には主に「成功報酬型」「着手金型(リテイナー型)」の2種類があります。
成功報酬型は、採用が決定した時点で手数料が発生する形式で、多くの企業で採用されています。リスクが少ない反面、競合紹介会社が同一人材にアプローチするケースもあります。
一方、着手金型は、採用活動の開始時に一部の手数料を支払い、残りを採用決定時に支払う方式です。
特に経営幹部や専門職など、希少性の高い人材を探す際に利用されることが多く、専属契約となることが一般的です。目的や人材のレベルに応じて選択が必要です。
また、成功報酬型の手数料には以下の2種類があります。
成功報酬型の仕組み
人材紹介における成功報酬型の仕組みとは、求職者が紹介先企業に入社して初めて紹介手数料が発生する契約形態です。
企業は採用が決定するまでコストが発生せず、採用の成果に応じて報酬を支払います。
手数料は、一般的に採用者の年収の一定割合(30〜35%)で設定されます。入社後、早期退職があった場合には、返金規定を設けてリスクを軽減することもあります。
成果重視のため、効率的な採用手段として広く活用されています。
届出制の人材紹介手数料
人材紹介における「届け出制の手数料」とは、厚生労働省が定めた範囲内で、人材紹介会社が自社の手数料率を設定・届け出する仕組みのことです。
日本の職業紹介事業では、手数料に関して「上限手数料率(原則:年収の50%まで)」が厚労省により定められており、それに基づいて各紹介会社が手数料率を届け出ます。
届け出制により、手数料の透明性と公正性が保たれ、企業と求職者の信頼性が担保されています。
企業が紹介会社と契約する際は、その会社がどの料率を届け出ているか(例:25%、30%など)を確認し、それに基づいてコストを把握することが重要です。紹介会社は、申請した料率を超えて手数料を請求することはできません。
上限制の人材紹介手数料
上記で触れた成功報酬型には、上限制という形もあります。人材紹介における上限制の手数料とは、紹介手数料に上限額を設ける契約形態のことです。
通常、手数料は採用者の年収に連動して計算され、高年収になるほど手数料も高額になります。これに対して上限制を導入することで、どれだけ高年収の人材を採用しても、手数料がある一定額を超えないように調整できます。
たとえば、「紹介手数料は年収の30%、ただし上限は200万円まで」といった契約です。これにより、企業側はコストを予測しやすくなり、高年収帯の採用に伴うリスクを軽減できます。
上限制は特に、マネジメント層や専門職の採用時に交渉により導入される場合があります。導入の可否や条件は紹介会社との契約によるため、事前の確認が重要です。
人材紹介手数料の算出方法
人材紹介手数料は、理論年収×手数料の計算式で算出できます。実際に式に数値を当てはめると以下のように算出できます。
人材紹介手数料が35%の場合
- 300万円(理論年収)×35%=105万円
- 500万円(理論年収)×35%=175万円
- 700万円(理論年収)×35%=245万円
人材紹介手数料の発生タイミング
- 求職者が内定を受諾し、雇用契約が成立した時点で手数料が発生するケース
- 実際に求職者が企業へ入社した日をもって手数料が発生するケース
- 入社〇日後という期限を決め、それを過ぎた段階で正式に請求・支払いが行われるケース
主に上記のようなタイミングが挙げられますが、ほとんどの人材紹介会社が入社日を発生のタイミングとして定めています。
理論年収とは
理論年収とは、企業が提示する給与額をもとに、1年間働いた場合に得られると想定される年収です。通常、月給や固定の手当、賞与(想定額)などを合算して算出されます。
理論年収の計算の仕方
| 支給項目 | 理論年収に含まれるか | 備考 |
| 基本給 | 〇 | |
| 賞与 | 〇 | 満額(「賞与算定基準額×賞与支給月収」で算出) |
| 成果報酬 | △ | 入社後の実績に応じて算出するため、基本組み込まれない |
| 住宅手当 | 〇 | |
| 固定残業手当 | 〇 | |
| 残業手当 | × | 残業時間数によって変動するため含まれない |
| 通勤手当 | × | 税務処理上、非課税のため含まれない |
| 出張手当 | × | 出張回数によって金額が変わるため含まれない |
| 家族手当 | 〇 | |
| 資格手当 | 〇 |
理論年収は、下記の式で算出可能です。
理論年収=月給×12+(想定)賞与
しかし求人票に「基本給20万円・諸手当5万円・賞与100万円」と記載されている場合の理論年収は下記のように試算できます。
400万円(理論年収)=25万円×12+100万円
理論年収と実際の年収は異なる
理論年収と実際の年収が異なるという場合も存在します。例えば賞与は、満額支給された場合の額が理論年収の中に組み込まれます。
在籍期間が多分に影響する賞与の場合、初年度に満額支給されることはほぼないといえます。
また、残業手当に関しては理論年収に含まれないため、理論年収よりも、その分金額が増える可能性があります。
早期退職した場合の返金手続きについて
人材紹介には、「紹介した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合に、紹介手数料の返金を請求できる」という返金条項が存在します。
手続きの流れとしては、採用した人材が入社後、一定期間内(相場は1ヶ月~3ヶ月)に退職した場合、企業側が退職事実を紹介会社に報告し、手続きを行う形になります。
紹介会社によってこの「一定期間」には幅があるので、契約前に注意する必要があります。
また、フリーリプレイスメントという補償を行っている場合もあります。フリーリプレイスメントとは、人材紹介サービスを通じて入社した人材が短期間で退職してしまった場合に、代わりとなる人材を無料で新たに紹介してもらえる補償制度です。
この補償のメリットとしては、早期退職が発生した後に、再度人材を補充する手間を省けることです。人手不足を一刻も早く解消したい企業にとって、非常に有効な手段です。
入社後のミスマッチや早期離職を防ぎたいと考えている人事担当者の中には、「RJP(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)」という採用手法に関心を持っている方も多いのではないでしょうか。 しかし、RJPの意味や効果がよくわからず、自社に導[…]
人材紹介サービスを上手に利用するポイント

人材紹介サービスを企業側が上手に利用するポイントを紹介します。
紹介会社との連携体制を構築する
人材紹介サービスを企業側が上手に活用するには、まず自社の採用ニーズや求める人物像を明確にし、紹介会社としっかり共有することが重要です。
募集背景や職場環境、選考プロセスの特徴などの情報を詳細に伝えることで、ミスマッチを防ぎ、質の高い候補者と出会える可能性が高まります。
紹介会社とは定期的にコミュニケーションをとり、採用状況やフィードバックをこまめに伝えることも効果的です。
また、信頼できるパートナーとして紹介会社を位置づけ、良好な関係を築くことで、長期的にスムーズな採用活動が可能になります。
複数の人材紹介サービスの手数料率を比較する
リクルートエージェント、マイナビエージェント、dodaエージェントなどの総合型人材紹介の場合、手数料は基本的に30~35%になります。ただし、特化型の人材紹介会社の場合、人材の貴重性を加味して総合型よりも手数料が高くなることもあります。
人材紹介会社を使う場合、自社がどのような職種でどのような人材を採用したいのかということを明確にし、対象の人材に強い紹介会社の中から、手数料を比較する必要があります。
手数料の支払いタイミングを確認する
手数料の支払いタイミングは、採用決定者が入社した時点での支払いが一般的です。ただし、入社から既定期間が経過した時点で紹介報酬が発生するケースも見られます。
報酬の支払時期は紹介会社ごとに異なるため、事前の確認が重要です。あわせて支払い期限についても確認し、トラブルを防ぎましょう。
人材紹介と他の採用手法の比較
| 採用手法 | 費用感 | 特徴 |
| 人材紹介 | 理論年収(30~35%)
求職者の収入によって変動する |
企業の求める条件に合った人材を人材紹介会社が推薦し、採用が決定した場合に成功報酬が発生するサービス
採用の手間を軽減し、専門職や即戦力人材の獲得に適している |
| 求人広告 | プランによって変動する(中間のプランで50万程度) | 不特定多数の求職者に向けて広く情報を発信でき、短期間で多数の応募を集めやすい。媒体や掲載内容により効果が異なる |
| ダイレクトリクルーティング | 新卒の場合
成功報酬:約30~50万円(一人当たり) 定額型:60~250万円/年 中途 の場合 成功報酬:理論年収の15%程度 定額型:200~400万円/年 |
企業が求職者に直接アプローチする採用手法で、即戦力人材とのマッチングやスピーディな採用が可能 |
| 求人検索エンジン | 無料~企業側が決められる | 複数の求人媒体や企業サイトから情報を自動で収集し、一括で検索・比較できるため、求職者は効率的に仕事探しができる |
| ハローワーク | 無料 | 国が運営する職業紹介機関で、無料で求人を出すことができる |
人材紹介のメリットとしては、採用担当者の業務の工数が省かれることです。また、人材紹介会社が企業に人材を直接紹介する形になるため、専門職などで人材が限られている場合はもっとも理にかなっている採用手法ともいえます。
失敗しない人材紹介会社の選び方
失敗しない人材紹介会社を選ぶには、自社の採用ニーズを理解してくれる専門的なエージェントを選ぶことが重要です。
業界や職種への理解が深く、質の高い候補者を提案できるか確認しましょう。担当者の対応力やヒアリング力も見極めポイントです。
また、紹介実績や返金保証制度の有無、契約条件の明確さも重要です。複数社を比較して、自社と相性の良いパートナーを見つけることが、最適な採用成功への近道です。
その会社の得意分野を確認する
人材紹介会社にはそれぞれ業種別、職種別、対象者層別で得意分野が分かれています。
現在、自社でどの人材が欲しいのかを明確にしたうえで、人材紹介会社を選ぶことが必要です。
手数料や返金規定を確認する
手数料や返金規定も人材紹介会社によって異なります。手数料に関しては、相場通りなのか、特化型で金額が上がっているのかなどについて確認する必要があります。
また、返金規定に関しては、フリーリプレイスメントなのか、返金条項に基づいたものなのか、自社にあったものを選定する必要があります。
リクルーティングアドバイザーとの相性を確認する
リクルーティングアドバイザーとの相性は、採用成功に直結します。
企業の文化やニーズを正確に理解し、的確な人材を提案してくれるリクルーティングアドバイザーと連携することが大切です。
信頼関係を築き円滑なコミュニケーションを取れば、結果的に人材のミスマッチを防ぐことができ、効率的な採用が可能になります。
「即戦力となる人を採用したいけど、何を活用したらいいかわからない……」 「採用手法が増えてきて、どれを活用することが自社にあっているかわからない……」 今回は上記のように悩む採用担当者向けに、即戦力の採用をするのにぜひ活[…]
【中途】主要な人材紹介会社の手数料比較
中途採用における人材紹介会社の手数料と返金規定について、各社の情報を見ながら比較してみましょう。返金規定は、「紹介した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合に、紹介手数料の返金を請求できる」ことを指しています。
| 会社名 | 手数料 | 返金規定 (※紹介手数料に対する返金割合) |
| リクルートエージェント | 約30~35% | 入社後1ヶ月以内 80%
入社後3ヶ月以内 50% 入社後6ヶ月以内10% |
| マイナビエージェント |
1年間に支払われる賃金の100%(または10,000,000円) 上記のうちどちらか高い方とする |
入社後3カ月以内で50% |
| JACリクルートメント | 35%(エグゼクティブ層は45%) | 入社後3ヶ月以内 50% |
| Geekly | 35%(最低料金100万円) | 手数料の5%~100% (会社ごとに期間・料率が決まる) |
| アスカグループ | 約30% | 入社後1ヶ月以内 100%返金
入社後2ヶ月以内 50%返金 入社後3ヶ月以内 30%返金 入社後1年以内5%返金 |
大手総合型と特化型では、手数料の大きな差はなく、相場通りであるといえます。しかし、会社ごとに返金規定がかなり異なることがわかります。
手数料を確認することはもちろんのこと、返金規定までしっかりと確認することが必要になってくるでしょう。
【新卒】主要な人材紹介会社の手数料比較
| 企業名 | 手数料 | 返金規定 (※紹介手数料に対する返金割合) |
| doda新卒エージェント | 文系110万円 理系130万円 | 入社後1ヶ月以内 80%
入社後2ヶ月~6ヶ月以内 20% |
| キャリタス就活エージェント | 文系100万円 理系120万円 | 明記なし |
| アイデムエージェント新卒 | 文系100万円 理系120万円 | 承諾後に学生が辞退した場合は、全額返金。 入社後の返金規定はなし |
| DYM | 文系150万円 理系200万円 | 明記なし |
| マイナビ新卒紹介 | 文系学生:85万円
理系・体育会系・海外大学留学生:100万円 |
明記なし |
中途採用の人材紹介とは違い、文系、理系で明確に金額が違うことがわかります。返金規定に関しては、明記がないことも多いので、しっかりと人材紹介会社に確認することが重要です。
人材紹介会社を利用する際の注意点
人材紹介会社を利用する際は、紹介会社の得意分野や実績を事前に確認し、自社の業界や職種に合っているかを見極めることが重要です。
また、担当アドバイザーとの相性や対応姿勢も採用成功に大きく影響します。紹介される人材の質や社風との相性、料金体系や契約条件、返金規定なども事前にしっかり確認しましょう。
採用実績がないままだと紹介されづらくなる
採用実績がない企業は、人材紹介会社から「成約見込みが低い」と判断されやすく、紹介の優先順位が下がる傾向があります。
また候補者側にも、入社事例がないことで不安を与えるほか、選考プロセスも不透明と見なされ、マッチング精度の面でも敬遠される可能性があります。
紹介されやすくするには、選考スピードの向上、明確な採用基準の提示、面接フィードバックの徹底、紹介会社との密なコミュニケーションが効果的です。
候補者への直接連絡は行わない
人材紹介経由での採用活動において、企業が候補者に直接連絡を取るのは原則NGとされています。
紹介会社との契約上、候補者とのやり取りは紹介会社が一括して管理するルールが一般的で、直接連絡は契約違反や信頼関係の毀損につながる恐れがあります。
また、選考スケジュールや条件交渉、フィードバック対応なども紹介会社が担うことで、効率的かつトラブルのない進行が可能となります。
面接当日の案内や内定後の連携強化などの一部ケースでは、紹介会社の許可のもとで連絡が行われる場合もありますが、常に事前確認が必要です。
信頼構築のためにも、ルールを守った丁寧な対応が重要です。
社内に採用ノウハウが蓄積しにくい
人材紹介を活用した採用では、候補者の選定や応募経路の分析など、重要なプロセスが紹介会社に委ねられるため、社内に採用ノウハウが蓄積しにくい傾向があります。
また、初期接点や辞退理由などの情報も社外で完結することが多く、面接手法の改善やマーケティング的視点の習得も難しくなります。
中長期的には自社ノウハウ構築のため、他の採用手法と併用し、学びを取り入れる取り組みが求められます。
【FAQ】人材紹介の手数料についてよくある質問

人材紹介会社の手数料についてよくある質問を紹介します。
人材紹介の手数料は高い?
人材紹介は他の採用手法(求人広告やダイレクトリクルーティングなど)と比べて、1人あたりの採用コストが高めです。
一般的に年収の30%前後が紹介手数料としてかかるため、コスト面では割高に感じることもあります。
ただし、即戦力人材を短期間で確実に採用できる点や、成功報酬型により、費用の無駄を抑えられる点を考慮すると 、費用対効果が高い採用手段といえます。
人材紹介の手数料はなぜ年収の30~35%前後なのですか?
人材紹介の手数料が年収の30〜35%前後に設定されているのは、候補者の発掘、選定、面接調整、内定後のフォローなど、紹介会社が行う業務の工数や専門性に見合った対価とされているためです。
また、採用が成立しないと報酬が発生しない「成功報酬型」であることから、企業側のリスクを軽減しつつ、紹介会社のリソース投下分を補う適正な水準として業界で定着しています。
手数料は交渉可能ですか?
人材紹介の手数料は交渉可能な場合があります。特に複数名の採用や継続的な取引を見込める場合、紹介会社によっては割引に応じることもあります。
ただし、手数料を下げすぎるとサービスの質に影響が出る可能性もあるため、バランスを考慮した交渉が重要です。
まとめ
人材紹介は他の採用手法と比較して確かに費用が高めです。しかし、候補者が企業に直接紹介されるため採用の確実性が高く、また「成功報酬型」のため、採用に至らなければ費用が発生しません。
そのため、無駄なコストが発生しにくいという特徴があります。
さらに、採用プロセスにかかる工数も他の手法と比べて格段に少ないため、採用担当者の負担軽減につながります。ただし、職種や業界によって適切な人材紹介会社は異なるため、自社に合ったパートナーを見極めることが重要です。
なお、他の中途採用手法についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
今まで通り求人媒体に掲載するだけでは、簡単に応募が集まりづらくなった現代で、本当に効果のある採用手法はどのようなものなのでしょうか。 本記事では、「基本的な採用手法を1からおさらいしつつ、ここ数年で新たに出てきた採用手法や採用成功につ[…]