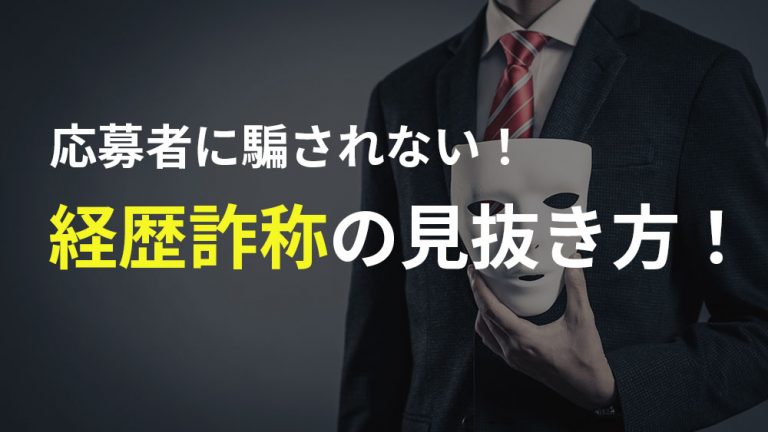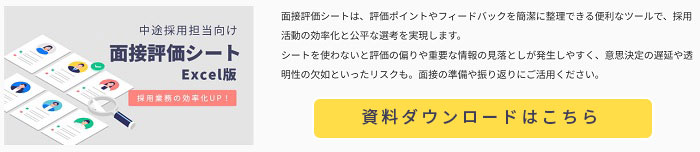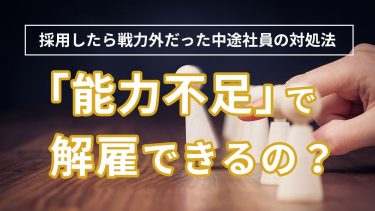今回のテーマは「経歴詐称の見抜き方」についてお届けします!
誰しも、自分が入りたいと思う企業に対しては、よく見せようとする心理が働いてしまうものです。しかし、そう思うがあまり、間違った方向に進んでしまい、経歴までも詐称をしてしまう人が稀に存在していることを知っていますか?
せっかく良い人材だと思って採用決定したのに、入社後に経歴を詐称されていたとわかっては、現場社員も本当に信用して良い人間なのか不安になってしまいます。
今回は、そんな事態に陥る前に、きちんとした見分け方を知って、未然に防いでもらえたらと思っています。
経歴詐称とは
経歴詐称とは、就転職活動中において、自身の実績や学歴などをよく見せようと経歴に嘘をつくことです。
具体的には年齢、学歴、職歴、犯罪歴、過去の実績などの項目があり、それらの項目を事実とは異なるよう捏造したりする求職者も少なからずいます。
ただ、0から1を作るような真っ赤な嘘ではなく、実績を少し盛ったような、いわば1を3や4にするような詐称であれば、大目に見ている企業もあり、状況はケースバイケースです。
経歴詐称の種類
経歴詐称にはいくつかの項目が種類ごとに分けられています。一体、どの様な経歴詐称が主に発生しているのでしょうか。
年齢詐称
キャリア形成を考えて、募集要件を35歳以下に絞っている企業も多くある一方で、その基準をオーバーしている、36歳以上の求職者が経歴を詐称するケースがあります。
この場合は生年月日を偽り、自身の年齢を調整するなどして、募集要項を満たすような動きが多く見られます。
年収の詐称
企業によっては、前職の年収を考慮し内定者の年収を決める企業も多くあります。その制度を逆手に取って、自身の年収を実際よりも多く申告する求職者もいます。
この場合、実際に証明書などを要求しなければ、口頭で好きなように言えるため、見抜くことが難しいです。
学歴詐称
中途採用で多いのが、学歴の詐称です。
出身大学を有名大学に偽造したり、海外での留学がなくてもあたかも留学経験があるかのような詐称をする人も非常に多くいます。
また場合によっては、出身大学は偽りがないものの、留年などを隠すために在籍期間を詐称するケースも増えてきているので注意が必要です。
資格・スキルの詐称
前職での職務内容や、自身ができるキャパシティを偽り、少しでも優秀に見せようとする人の場合、資格や経験を詐称する傾向が強いです。
そのため、面接の際に話を聞いた分には優秀だと感じたものの、実際に採用をすると期待ほど仕事ができないなんてことにもなりかねません。
転職回数の詐称
日本は海外と違い、転職回数が多いことに関してまだまだネガティブなイメージを持っています。
そのため、転職回数が極端に多いと、在籍期間の少なかった会社を記載しないなどして、転職回数を偽ることもあります。
解雇できる場合とできない場合
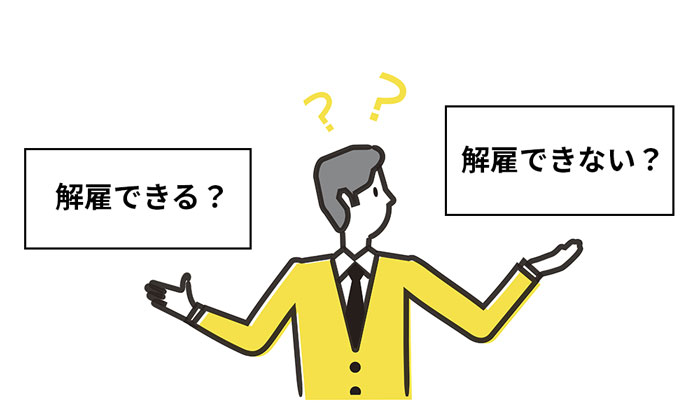
経歴詐称は人事にとって非常に厄介なもので、選考時に気づけば良いものの、実際に採用してしまってから発覚した場合は面倒なことになりかねません。
そこで、経歴詐称が発覚した際、解雇することはできるのか、またどういう場合には解雇できないのか知る必要があります。
懲戒解雇できる場合
経歴詐称が発覚し、懲戒解雇できる一般的な基準としては、「重大な経歴詐称」があったかどうかになります。
重大な経歴というのは、採用条件に直接関わるものを言い、選考段階においてもし本当のことを知っていたら雇用契約は結ばなかったであろう経歴です。
例えば、
・TOEIC800点以上が最低条件であるのに、650点を850点と申告した場合
などです。
また他にも、犯罪歴や病気歴があるのにも関わらず、それらを伏せて詐称したことが後から発覚した場合、企業側は解雇をすることができます。
解雇できない場合
では逆に解雇ができない場合はどの様な場合でしょうか?
それは、「採用条件に直接かかわる詐称」以外の場合は解雇ができません。また、学歴、職歴、犯罪歴の詐称があったとしても、就業規則にその旨を記載しておく必要があり、詐称が発覚したからといって、直ちに解雇できるとは限らないのです。
そのため、採用の合否に直結しない程度の詐称であれば解雇をすることができず、逆に解雇をしてしまうと不当解雇となり賠償金を支払わなければならないケースに発展します。
そのため、経歴詐称は選考段階で見抜けるよう、人事側で対策を取っていく必要があります。
詐称発覚後、解雇できない場合の対処法
本来であれば、選考段階で経歴詐称を見抜きたいところですが、それができなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
経歴詐称の有無を公表するか決める
その場合には、その社員とは上手く付き合っていく必要があります。そのうえで、まずは経歴詐称があったことを社内で公表するかどうかを決めましょう。
重大な経歴詐称の場合は社内で公表する企業が多いですが、そこまで大きな問題でない場合、一部の上位層のみが把握し、末端の社員には伏せておくことが多いです。
給与を下げる場合には
また、企業によっては給与を下げるべきか迷う企業も多くあります。ただ、詐称があったからと言って一方的に給与を下げるとトラブルが発生することも十分にありえます。
そのため、もしも給与を下げるのであれば、保有資格や経験年数など、具体的に数値や資格など、可視化出来るフェアな条件を提示するようにしましょう。
そうすることで、不当に一方的な給与ダウンをしたことにはならず、公平性を保ったままの交渉ができます。
実際にあった経歴詐称での裁判事例
実際にこの章では、過去にあった経歴詐称に伴う裁判事例について紹介します。
経歴詐称での解雇が認められた事例
KPIソリューションズ事件
システムエンジニア・プログラマーを募集し採用したところ、職歴を偽っていたことが判明し当該社員を普通解雇しました。能力に自信を示し、給与の増額を行っていたにもかかわらず、実際はプログラムはほとんどできなかったということもあり、普通解雇を有効とした他、会社への損害賠償が認められた事例です。この事件では、「真実を告知したならば採用しなかったであろう重大な経歴」はないとして懲戒解雇は否定されました。もっとも信頼関係は破綻したとして、普通解雇が有効と判断された事例です。(引用元:企業法務ナビ)
正興産業事件
高校中退を高校卒業と偽って自動車教習所の指導員となった者につき、高卒の学歴を有していないことが当初から判明していれば採用することはなかったとし、就業規則の懲戒解雇事由に該当するとした事例です。(引用元:企業法務ナビ)
炭研精工事件
この事件では、実際には大学を中退していたのですが、当時の募集対象者が高校卒業者又は中学卒業者となっていたため、高校卒業と学歴を偽って採用されました。
裁判では、経歴詐称(学歴詐称)は就業規則の懲戒解雇の事由に該当すると判断したのですが、懲役刑の有罪判決を受けた事実、従業員の情状を考慮した上で、懲戒解雇を有効と判断しました。(引用元:なるほど労働契約法)
経歴詐称による解雇が認められなかった事例
マルヤタクシー事件
タクシー乗務員として採用されるにあたり、刑の消滅した前科を秘匿し、また職歴にも3ヶ月間の稼働期間の違いがあったという事案について、「前科」は賞罰欄に記載すべきですが、刑の消滅した前科については、その存在が労働力の評価に重大な影響を及ぼす特段の事情がない限り、告知すべき信義則上の義務はないし、また、3ヶ月間の職歴の稼働期間の違いでは、労働力評価を誤らせるということはできないとして、解雇を無効としました。(引用元:企業法務ナビ)
秋草学園事件
履歴書に職歴の不実記載をしたこと、学生や教職員に暴言等をしたこと等を理由とする私立短大教員に対する解雇につき、解雇事由としての職務の適格性の欠如に相当するまでの事実は認められないとして、右解雇が無効とされた事例。(引用元:労働基準判例検索・全情報)
経歴詐称者を企業に残しておくデメリット
調査を行った結果、経歴詐称が発覚した場合、その社員をどうするのかは非常に悩ましいものであり、場合によっては解雇ができず会社に残さなければなりません。
そこで、採用してしまったばかりに解雇ができず、会社に経歴詐称を行った社員が存在するとどの様なことが起こるのでしょうか。
人事部自体の信頼がなくなる
経歴詐称を見抜けなかったことや調査不足、更には最終的に解雇できない自体に陥ったリカバリー能力の低さなど、まずはじめに人事部に対しての風当たりは強くなるでしょう。
また、既存社員へそのことが知れ渡ることで、社内のケミストリーが崩壊してしまうことや、チームでの業務が円滑に進まなことも想定されます。
取引上における信用問題に発展する可能性も
さらに最悪の場合、何らかの形で取引先に知られてしまうと、取引上における信用問題にも発展しかねないため、経歴詐称者を会社に残しておくと、非常に多くのデメリットがあります。
そのため、選考の際に慎重になることはもちろんですが、実際に内定を出す前にその応募者の調査なども怠ってはいけません。
経歴詐称者を見抜く!事前の対策
ここまで解説したように、一度経歴詐称者を採用すると、デメリットが多かったり解雇できなかったりと何かと面倒なことが多いです。
そのため、事前に経歴詐称者を見抜き、内定を出さないことが求められます。経歴詐称を見抜くためのポイントは把握しておくべきと言えるでしょう。大きく分けて経歴詐称を見抜く方法は、主に以下のような方法があります。
- 各種書類のチェック
- 面接時の受け答え
- 第三者への調査依頼(リファレンスチェック)
書類のチェック
学歴や職歴の詐称は、それを証明する書類を提出してもらうことで未然に回避することができます。
| 学歴の場合 | 卒業証書、卒業証明書 |
| 職歴の場合 | 雇用保険被保険者証、年金手帳など |
| 免許・資格の場合 | 免許証、スコア証明書など |
| 年収の場合 | 源泉徴収票 |
面接時の受け答えでチェック
書類上では色々と嘘を並べられても、面接時に深堀りしていけば、必ずどこかでボロが出てくるものです。少しでも気になったり違和感を感じた場合には、事細かに質問し、受け答えの反応をしっかりと見るようにしましょう。
ただ、受け答えの回答を事前に準備して臨んでくる場合もあり得るので、想定外の質問をすることができたらベストです。
第三者への依頼調査(リファレンスチェック)
求職者の働きぶりや人物像を知る前職の上司や同僚などの第三者に調査依頼することで、本当に信頼できる人物かどうかを見極めることが可能になります。書類の詐称が見極められることはもちろんのこと、面接時にも分かりえなかった情報も入手することができるというメリットもあります。
リファレンスチェックには、オンラインですべて完結するツールなどもあり、活用してみるもの一つの手といえます。
人事を行う中で避けたいことのひとつとしてあげられるのは、ミスマッチではないでしょうか?企業と求職者に相違が生まれてしまうと、早期離職に繋がります。 離職以外にも、採用後のトラブルを未然に防ぐため活用できるのがリファレンスチェックです。[…]
まとめ
近年、新型コロナウイルスの影響により求人倍率が低下し、就職活動が非常に困難な状況が続いていました。しかし、現在ではコロナ禍も収束し、求人市場は回復傾向にあります。
このような状況下でも、求職者の中には少しでも有利に立とうと経歴を詐称する人が見受けられます。
企業の採用担当者は、経歴詐称を見抜き、内定を出さないよう注意深く業務に取り組むことが重要です。履歴書の詳細な確認、面接時の深掘り質問、リファレンスチェックの実施などの効果的な施策を行い、しっかり対策していきましょう。
即戦力を期待して中途採用を行ったものの、思ったよりも能力が低く、このままでは会社のプラスにならないと感じたことはないでしょうか? 実際に解雇に踏み切りたくても、法律的な縛りもあり、なかなか難しい部分がありますよね。 そこで今回は、能[…]