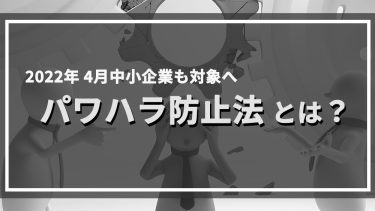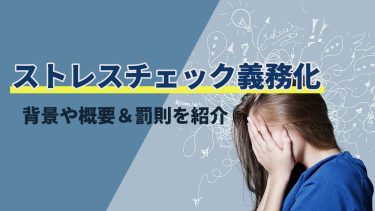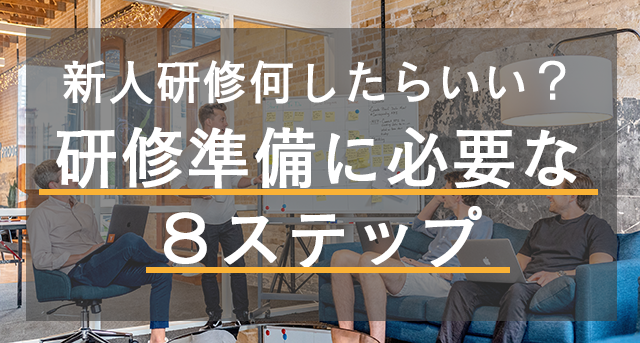怒りの感情は職場環境を悪化させてしまいます。しかし、怒りの感情を持つことが悪いわけではありません。
怒りの感情の表現方法や向き合い方を知らないと、パワーハラスメントなどの問題発生や環境悪化によるモチベーションの減少によって企業の生産性が落ちてしまうことにもなりかねません。
そこで、今回はアンガーマネジメントについて取り上げました。アンガーマネジメントに企業で取り組むメリットや方法も解説しています。アンガーマネジメントを習得してより働きやすい環境を整え、生産性アップや良い人材の採用を目指しましょう。
アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントを直訳すると「怒りの管理方法」です。劣等感や怒りなどのネガティブな感情を受け入れることを目的とした心理教育やトレーニングのことをアンガーマネジメントと呼んでいます。
アンガーマネジメントでは、怒らないことが良いわけではありません。必要なときには、怒りをコントロールしながら上手に対応することも大切です。
アンガーマネジメントは1970年代にアメリカで始まったといわれており、当初は犯罪者の矯正プログラムに活用されていました。現在では、一般化されて企業の研修にも取り入れられています。
アンガーマネジメントに取り組む重要性
では、企業でアンガーマネジメントに取り組むとどのような良いことがあるのでしょうか。アンガーマネジメントの重要性やメリット、導入の方法などを具体的に見ていきましょう。
アンガーマネジメントの必要性と背景
アンガーマネジメントが注目され始めた背景の一つとして、社会全体でハラスメント対策に力を入れているという点もあります。
これまでは教育として認識されていた「叱る」という方法もパワーハラスメントとみなされてしまったり、怒りの表現方法がわからず上手に叱れなかったりなど、怒りに関する問題を持った経験のある方もいるのではないでしょうか。
また、社会にはさまざまな価値観が存在しています。多様性を認める社会へ変わっている一方、まだまだ価値観の不一致を認められない人も多いでしょう。自分の価値観とは異なる人と接点を持つことがストレス要因となり、怒りをため込みがちになっている人がいることも否めません。
こういった背景から、アンガーマネジメントが企業で求められるようになっているのです。
メリット
アンガーマネジメントが注目された背景や必要性を踏まえて、企業全体で取り組むメリットを具体的に見ていきましょう。
社員の働きやすさ改善になる
まず、企業をあげてアンガーマネジメントに取り組むことによって、社員が働きやすい職場に生まれ変わります。
アンガーマネジメントで怒りと上手に向き合う方法を学べば、ハラスメントが生まれにくくなります。
ハラスメントが減少することによって、より社員が働きやすくなり、企業の生産性アップや離職率の低下にもつながるでしょう。
上司の印象が良くなる
信頼される上司は、その日の機嫌に判断を左右されません。「この前はこれでOKだったのに、今日は機嫌が悪くて怒られた」となれば、部下のモチベーションも下がってしまいます。
怒りの感情に振り回されることなく、必要なときに適切に叱れる上司は部下からの印象も良くなるでしょう。
怒り以外の解決策で業務効率もアップ
怒りの管理が上手にできると、感情に振り回されることなく仕事が進められます。仕事に対するストレスが減り、やりがいや意欲を持って取り組めるようになるでしょう。
社員個々のパフォーマンスが向上していくことで、企業全体の業務効率アップも目指せます。
アンガーマネジメントの企業研修を依頼する方法も
企業全体でアンガーマネジメントに取り組むためには、日本アンガーマネジメント協会などの団体に外部講師を依頼するのもひとつの手です。
日本アンガーマネジメント協会では、管理職向け・パワハラ防止・コミュニケーション・メンタルヘルスとさまざまな目的に合ったプログラムもあり、研修内容に合った講座を選択できます。
しかし、研修をしたからといってすぐに結果が出るわけではありません。研修で学んだことを実践する必要があります。
また、研修前にはアンガーマネジメントに取り組むことを周知して意識を高めていくのもポイントです。
近年、耳することが多くなった“パワーハラスメント”という言葉ですが、定義が曖昧で、パワハラの受け手(部下)の主張が大きく反映されやすい言葉です。 また、大企業では2020年6月からは「パワハラ防止法」という新しい法律が施行され、ますま[…]
怒りの仕組み

怒りとはそもそもどのように生まれるのでしょうか。ここでは、怒りの仕組み「第一次感情」と「第二次感情」について説明します。
第一次感情
第一次感情とは、不安・恐怖・悲しみ・寂しさ・疲れ・焦りなどの感情のことです。このような日々の生活の中で感じるネガティブな感情が怒りの裏側に隠れています。これらはマイナスな気持ちばかりですが、誰しもが抱えている感情です。
第二次感情
第二次感情は怒りとして現れるものです。怒りには必ず原因となる第一次感情が存在しています。第一次感情が大きいほど第二次感情として現れる怒りも大きくなるでしょう。
怒りを感じることは自然なことなので、問題はありません。しかし、非常に強い怒りを感じたり、過去に感じた怒りを引きずったり、1日中イライラが持続したり周囲の人や物に当たったりする怒りには注意が必要です。
「強度の高い怒り」「持続性のある怒り」「頻度の高い怒り」「攻撃性のある怒り」を感じやすい方にはとくにアンガーマネジメントを学んで、感情をコントロールする必要があるでしょう。
怒りのタイプを知ろう
怒りをコントロールするためには、まず自分の怒りのタイプを知ることから始めましょう。
自分がなぜ怒っているのか理由を知ることで、自分とも周囲ともより良い関係が築けるようになります。
また、研修後の面談は、怒りのタイプを意識して行うのも良いでしょう。怒りのタイプには以下の6種類があります。
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
公明正大タイプ
マナーや社会のルールを守れない人に対して怒りを感じるタイプです。正義感や道徳心が強く、他者の間違いを正そうとして、物事に介入しすぎてしまう傾向があります。
自分の価値観が正義と思い込まず、相手の意見を受け入れることが怒りの解消につながるでしょう。
博学多才タイプ
優柔不断な人に対して怒りを抱きやすいのが博学多才タイプです。完璧主義で自分にも他者にも厳しくなってしまいます。
必ずしも白黒はっきりさせる必要がないという考え方を身に付けるのがイライラ解消のカギです。
威風堂々タイプ
周囲からの評価が気になるタイプです。自分の思い通りにならなかったり、評価が低かったりすると自尊心が傷付き、イライラを感じやすくなります。
優秀さを競うのではなく、それぞれの良さを認めると怒りの感情が現れる場面が減るでしょう。
外柔内剛タイプ
一見温和な雰囲気ですが、芯が強くブレないタイプです。我慢強く、お願いされると断れないのでストレスをためやすいでしょう。
断る勇気を持ったりストレスの発散方法を見つけたりする必要があります。
天真爛漫タイプ
自分の意見をはっきり言わない人や思い通りに行動できないとイライラしてしまう傾向があります。自身は、目上の人にも意見や感情を伝えられ、行動力もあるので、物事がスムーズに進まないことが苦手です。
ときには立ち止まり、相手の意見を聞くようにすると、ストレスを減らせるでしょう。
用心堅固タイプ
パーソナルスペースが広く周囲への警戒心が強いため、人間関係においてストレスを感じやすい傾向があります。周囲から頼られるのも苦手でしょう。
ストレス軽減の第一歩は、相手を信じたり頼ったりすることです。まずは相手を信じることが、良好な人間関係の構築につながります。
近年職場環境が悪い企業や、長時間労働が常習化しているブラック企業の存在や、労災件数の多さなどから職場でのストレスに関しては多くの人が注目を集めています。 規定とされている企業は、ストレスチェック制度が義務化され、社員の精神衛生の管理は[…]
アンガーマネジメントの方法

怒りのタイプが分かったら、次にアンガーマネジメントの方法を学びましょう。仕事中や日常生活において怒りを感じたら、次の方法を試してみてください。
6秒ルール
一つ目のアンガーマネジメントの方法は、6秒ルールです。怒りを感じたら、自分の中で6秒数えてみてください。「6秒あると理性が働く」と言われています。
怒りの感情は0にはなりませんが、理性的になれるので怒りをコントロールしやすくなるでしょう。カウントするだけでは効果を感じない方は「怒らなくても大丈夫」と気持ちを落ち着かせる言葉を心の中で繰り返したり、深呼吸したりするもおすすめです。
その場を離れる
6秒数えても怒りが収まらない場合は、物理的に怒りと距離を取りましょう。トイレやコンビニへ出て、その場から離れるのがポイントです。怒りの対象から気がそれて、冷静になることができます。
その場から離れたときには、怒りについてではなく過去のポジティブな出来事を思い返して気持ちを落ち着かせるのもいいでしょう。
怒りを点数化
怒りと向き合うときには、今抱いている怒りの感情が10段階で何点の怒りなのか考えてみてください。点数化することで「今日は過去に比べて点数が低いから怒らなくて良いかもしれない」と判断できるようになります。
また、点数を決めるために怒りの原因を客観視することができるのもメリットのひとつです。
リフレーミング
リフレーミングとは、意識的に相手の立場になって考えることです。怒りの感情は「~であるべき」という個々の価値観から生まれることも少なくありません。
自分の望んだ方向にことが進まなかったときに、なぜ相手はこの行動を取ったのか考えてみましょう。自分にとっての「当たり前」は相手にとっては違うことを理解できると、怒りがコントロールしやすくなります。
また「これなら許せる」という条件を付けて許容範囲を広げていくと、ストレス軽減につながるでしょう。
コントロールできない物事を把握する
怒りの原因として、自分ではコントロールできない物事もあります。例えば、「渋滞によってバスが遅れて遅刻してしまった」は自分ではコントロールできない事案です。
自分でコントロールすることのできない状況には「怒っても仕方ない」と諦めるのも大切です。
まとめ
アンガーマネジメントに企業で取り組むメリットや方法を紹介しました。
アンガーマネジメントの実践は、はじめは難しく感じるかもしれません。しかし、知識を付けて継続していくことで、とっさに実行できたり考え方が変わっていったりと怒りの感情をコントロールできていると実感できるようになります。
働く環境の良い企業には、入社希望者が増加し、より良い人材が集まりやすくなるでしょう。
ぜひ、アンガーマネジメントを社内研修に取り入れてみてください。
今回のテーマは「新入社員特徴と離職率を下げるための研修事例」です! 企業に新入社員が入社したら、必ず行われる新入社員研修。毎年4月~6月の約3ヵ月の間に、新入社員研修を実施している企業が多いのではないでしょうか。企業によって新入社員研[…]