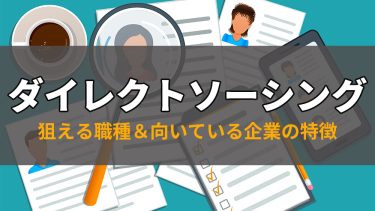ベストプラクティスは、「最善の方法・事例」のことを指しており、さまざまな使われ方をします。
ビジネスの場では、おもに「最善の方法」という意味合いで使われることが多いでしょう。そんなベストプラクティスは、導入することで業務効率化などメリットがあります。
しかし、上手に活用するためには、自社に合っているかどうかの見極めや導入コストについてなど、注意する点がいくつかあり、それを意識することが大切です。
この記事では、ベストプラクティスの概要をはじめ、メリットやデメリットについて解説していきます。
ベストプラクティスとは

ベストプラクティスとは、今の時点で考えられる「最善の方法」や「最良の事例・手法」を意味します。ベストプラクティスは、「Best(最善の、最良の)」と「Practice(実践、実行、練習)」を合わせた言葉です。
ある特定の実践や実例について「現時点で最も優れている」と評価される際に使われ、ビジネスの分野で多く用いられています。
ベストプラクティスは、あくまで今・現時点でベストな状況を指すため、その後新しい工程や手法がベストプラクティスとなることもあるでしょう。
ベストプラクティスと関連した言葉
ベストプラクティスには、似ている用語や同じような意味合いの言葉が存在します。以下で、いくつか紹介していきましょう。
ベストフィット
ベストフィットは、「最良適合・最適任」という意味をもつ言葉です。
ベストプラクティスが、事例や手法に用いられるのに対して、人材など特定の人物を指す場合に使われるのがベストフィットです。
例えば、「我が社にベストフィットする人材を選定する」といった使い方をします。
最良や最適など、言葉の意味は同じであっても対象となるものに大きな違いがあります。
セオリー
セオリーは、「理論・定石」などの意味をもつ言葉です。
現時点で最も優れている手法などを表すベストプラクティスとは違い、セオリーはごくごく一般的な、誰もが選ぶような手法を表す言葉です。
例えば、「何事もまずは、セオリー通りにやってみよう」「セオリーを確立させる」といった使い方をします。
バッドプラクティス
ベストプラクティスと対極にあるのがバッドプラクティスです。
現時点で最良の方法がベストプラクティスなら、最も非効率な手法とされるのがバッドプラクティスです。
失敗例や悪しき見本といった意味合いで使われることが多いですが、ベストプラクティスはバッドプラクティスと比較することで、優れた部分がよりはっきりと表面化されるとされています。
ベンチマーキング
ベンチマーキングは、自社の経営や業務において非効率的な部分を見つけ改善する方法のことです。
そのために重要なのがベストプラクティスで、ベストプラクティスを参考に比較分析を行い、効率の改善を図っていきます。
採用におけるベストプラクティス
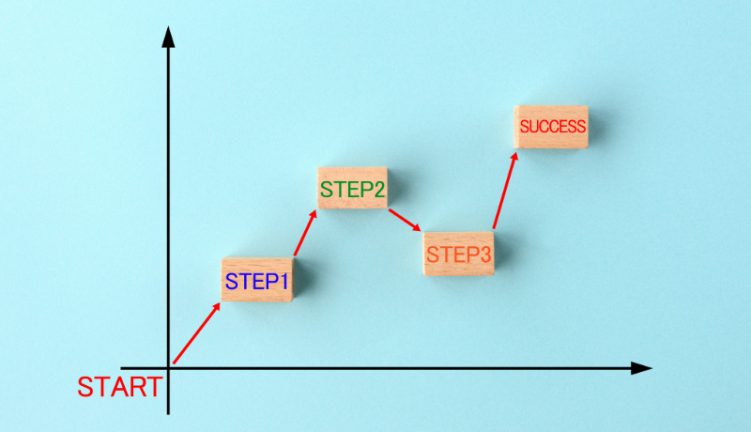
会社にとって人材は不可欠な要素です。採用市場は年々変化しており、これまでの採用手法では十分とはいえず、うまく進められない場合もあるでしょう。
ここでは、採用におけるベストプラクティスを紹介します。
明確な採用プロセスの構築
- 採用プロセスは、必ずしも決まった型やパターンがあるわけではありません。
そのため、「自社の採用目的」「欲しい人材」「採用したいポジション」などにより、現時点で最良な採用のプロセスを柔軟に組み立てていく必要があります。
どのような採用方法を取り入れ、アプローチしていくのか、入社後の社員育成はどうするのかなど、採用プロセスを明確にしていくことが大切です。
最新テクノロジーの活用
優秀な人材や企業の求める人材を効率的に獲得するために、最新のテクノロジーを活用する方法もあります。
例えば、人工知能(AI)を活用した採用ツールは、膨大な数の応募書類を効率的に処理することが可能で、適切な応募者を絞り込めます。
そのほか、候補者の質問に自動回答できるチャットボットや、多くの応募者との面接を可能にするオンライン面接なども、担当者の負担を軽減するでしょう。
オンボーディングの重要性
オンボーディングとは、組織にとっての新しい仲間(新入社員)が、順応して組織に溶け込めるように促進する取り組みです。
新卒や中途など、企業に入社した社員の早期離職を防止し、企業への定着率を上げることを目的としています。
まずは、企業の関連情報などを共有する新人研修といった場は、なるべく早く実施する必要があるでしょう。
オンボーディングは、社員が企業で成功するための土台となるため、重要性は高いといえます。
「折角、良い人材を採用しても転職されてしまった」、「転職率を低くするノウハウを教えて欲しい」との悩みをお持ちの採用担当者は少なくないと思います。 昨今、日本企業では新卒/転職者が数年以内に転職することが多いことから、これを防止する取り[…]
継続的なサポートと育成
新入社員が、企業から与えられた役割を果たすためには、継続的なサポートと育成の場が必要であり重要です。
特定の知識やスキルを身につけるのに適した個人的な育成をはじめ、チーム全体の能力やコミュニケーションを向上させるグループでの育成などがあります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側が求める人材を採用するため、企業主体で採用するための手段を考えて、行動にうつす採用活動を指します。
労働力人口の減少などで人材獲得競争が激化しているなか、さまざまある採用手法の中からベストな人材を選択するダイレクトリクルーティングは、現代の流れにマッチしたベストな採用方法といえます。
ダイレクトソーシングとは、採用担当者が能動的に求職者を探しだし、アプローチを仕掛ける採用手法です。 本記事では、ダイレクトソーシングが流行した背景や、メリット・デメリットなど基本情報を解説します。 ダイレクトソーシングとは […]
採用後のフィードバックと評価
採用活動後にフィードバックを活用し評価を行うことは、採用活動にとってとても重要なステップであり、ベストプラクティスのひとつといえます。
今の企業にとって必要だと判断した内容を実行に移した後は、結果に対する学びを抽出する必要があります。
ベストプラクティスのメリット
ベストプラクティスを導入すると、以下のようなメリットが期待できます。
業務効率化
ベストプラクティス導入のメリットは、業務効率化が期待できることでしょう。
ベストプラクティスが現時点での最良の手法であるなら、取り入れることでこれまでよりも業務効率がアップするのは、いうまでもなく当然といえます。
ただし、現時点で効果的な方法とされるベストプラクティスも、時間の経過とともに変化し、それ以上に効果的な方法が出てくるケースもあることを理解しておく必要があります。
成果の実証
一定の成果が実証されているベストプラクティスを取り入れることで、成果をあげやすくなるメリットがあります。
すでに実績があることから、周りの同意やサポートを得やすくなるでしょう。
成功実績があるベストプラクティスを取り入れれば、失敗のリスクを最小限におさえられ安定した成果を得やすくなるのです。
継続的な改善と適応
ベストプラクティスを取り入れて、これまでの事例を比較分析することで、継続的な改善と適応が可能になります。
これは、安定した成果を得られることに加え、失敗を未然に防ぐことにもつながります。
ベストプラクティスのデメリット
企業にとって、採用の場をはじめ、さまざまなシーンで「ベストプラクティスは何か」ということに視点をあてることは大切ですが、以下のようなデメリットにも注意しておきましょう。
理論と実践のギャップ
他の企業では成功しており、理論上で最善な方法であっても、自社では実現不可能な場合があります。そのような理論と実践のギャップは大きなデメリットといえます。
どんなに優れたベストプラクティスであっても、実践できなければ、時間を無駄に費やすだけで企業が得られるメリットはないでしょう。
導入コスト
ベストプラクティスとして新しい手法やシステムを導入する際、コストがかかる場合があります。
最善の方法だからという理由で取り入れる場合、社員たちが新しい方法ややり方に慣れるまでに時間を費やすこともあります。
そのため、導入コストを考えたときに、既存のやり方を続けるほうが効率が良いケースも考えられるでしょう。
革新の阻害
ベストプラクティスに頼りすぎてしまうと、革新の阻害につながる場合も考えられます。
ベストプラクティスが、現時点で最適な方法であることは確かといえます。そして、導入可能なベストプラクティスによって、企業が成功を収めることも可能です。
しかし、他社のベストプラクティスに頼りすぎ、自社の中で最適な方法を模索しなくなってしまうと、企業として大きな進歩はできなくなるでしょう。
ベストプラクティス導入の注意点

最後に、ベストプラクティスを導入する際の注意点について解説します。
自社に合った適用の見極め
ベストプラクティスを取り入れて、成果を出すためには、その手法が自社に合っているのか、自社に合った適用の見極めが大切といえます。
大企業にとってのベストプラクティスが、中小企業にそのまま適用できるかというとそうではないため、導入の際は「適用の見極め」がとても大切です。
導入コストと時間の考慮
これまで自社で取り入れていた手法やノウハウの変更は、大きな時間を費やします。
また、ベストプラクティスは導入時にコストがかかる場合があるため、時間とコストのリスク管理を考慮する必要があるでしょう。
新たにベストプラクティスを導入する場合、その手法が時間やコストを費やす価値があるものか、自社にとって最適かどうかを十分に検討することが重要です。
継続的な改善と適応
- ベストプラクティスは、導入するにあたり継続的なプロセスであるべきと、考えられます。
しかし、市場環境のほか、組織が求めるものが変われば、それまでのベストプラクティスが最適な方法ではなくなる場合もあるでしょう。そのため、継続的な改善が必須となります。
さらに、成果を出すためには、そのプロセスが自社の状況に適応できているのか見極めることも重要です。
まとめ
現時点での最適な手法を意味するベストプラクティスは、導入することで企業にさまざまなメリットをもたらします。
ただし、自社に合った手法の見極めや導入コスト、時間を考慮するといった注意点も存在します。
ベストプラクティスは、自社の目標などに合わせて多くの企業が導入しています。
この記事で紹介したメリットやデメリット、注意点などを参考に、新たな手法の導入を検討してみてはどうでしょう。
「人手が足りない…」「もっと業務の効率化ができないだろうか…」そんな企業必見!外部に委託することで自社の業務を効率化できるBPOを取り入れてみませんか? 本記事では、 多くの企業が課題と感じている「人材不足」から脱却するためのサービス[…]