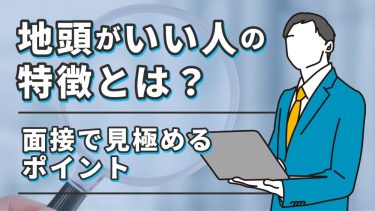「しごでき」という言葉をご存知でしょうか。仕事ができる人のことを省略した言葉で、若者の間で流行しています。
今回の記事では、そんな「しごでき」人材の特徴に迫ってみましょう。
また、仕事ができる人の業務の進め方や、そうでない人との違いを解説します。さらに、採用面接で仕事ができる人かどうか見極めるポイントもご紹介します。
時間とお金がかかる採用面接で、より良い人材を確保したい採用担当者は、ぜひチェック項目に取り入れてください。

●面接の基本と重要ポイント
ー面接で入社意欲を高める方法や効果的なコミュニケーション術
●具体的な質問例と応用方法
ー候補者の能力やスキルを見極めるための質問設定方法
●オンライン面接の成功ポイント
ーアイスブレイクやリアクションの重要性など、オンライン特有の対策
- 1 しごできとは?
- 2 仕事ができる人の特徴15選
- 2.1 挨拶ができて円滑なコミュニケーションが取れる
- 2.2 身だしなみを整えており清潔感がある
- 2.3 約束や時間を大切にできる
- 2.4 ゴールから逆算して計画的に仕事を進める
- 2.5 常にリスクを考えて仕事ができる
- 2.6 ミス無く効率良く仕事ができるように工夫する
- 2.7 ポジティブ思考でチャレンジ精神がある
- 2.8 ミスやトラブル発生時にすぐに報告・相談ができる
- 2.9 いつでも連絡が取れる
- 2.10 他の人の力を借りて仕事ができる
- 2.11 的確で素早い判断力がある
- 2.12 短時間で集中して成果を上げる
- 2.13 最新情報を得るためにアンテナを張っている
- 2.14 自分の考えを言葉にして相手に分かりやすく伝えられる
- 2.15 プライベートと仕事の切り替えが上手
- 3 仕事ができる人が企業に与える影響
- 4 仕事ができる人とできない人の違い
- 5 仕事ができる人の業務の進め方
- 6 仕事ができる人を面接で見極める方法
- 7 まとめ
しごできとは?

しごできとは「仕事ができる人」や「仕事ができる」を省略した言葉で、2019年ごろから流行し始めました。
高い成果を上げる人や、秀でた能力がある人を褒める際に使われます。また、しごできの使用シーンは業務中に限らず、日常のあらゆる場面でてきぱきと動く人をさして使われます。
なお、「しごでき」は「気が利く」「有能」「敏腕」などに言い換えが可能です。
ビジネスシーンなどのかしこまった場では、より丁寧な言葉で表現すると良いでしょう。
仕事ができる人の特徴15選
まずは、仕事ができる人に共通する特徴を見てみましょう。
挨拶ができて円滑なコミュニケーションが取れる
挨拶ができないと、相手にマイナスな印象を与えかねません。
どんな職業でも人とのコミュニケーションは必須なので、仕事ができる人はきちんとした挨拶ができます。
さらに、相手の名前を呼び、目を合わせて挨拶ができる人は相手に好印象を与え、その後のコミュニケーションも円滑になるでしょう。
身だしなみを整えており清潔感がある
仕事ができる人は、自分がどう見られているかを客観的に認識できます。
そのため、自分の身だしなみにも気を配っており、周囲の人に不快な思いをさせないよう意識をしています。
清潔感があると第一印象が良くなり、相手からの信頼が得やすくなるでしょう。
約束や時間を大切にできる
締め切りを守れる人は、周囲の人から信頼されます。反対に、締め切りを守れない人は相手の時間を奪ってしまうため、不信感に繋がりかねません。
また、仕事ができる人は、締め切りに間に合わないと分かった時点で相談し、スケジュールを柔軟に調整します。
ゴールから逆算して計画的に仕事を進める
業務のゴールを見極め、そこまでにやらなくてはいけないタスクを計画的にこなせる人は、仕事ができる人です。
TODOリストなどを使い、タスクをピックアップしてから取り組みます。
この時、業務内容の全体像が見えているので、やみくもに作業を開始するのではなく、段取り良く進められます。
常にリスクを考えて仕事ができる
仕事には予想外のトラブルやミスがつきものです。仕事ができる人は、そんな不測の事態も起こり得るものだと考えて、仕事の段取りを組んでいます。
どんなことが起きても、冷静に対処できるゆとりを持っている人は、周囲の人からも「あの人がいれば安心だ」と頼られるでしょう。
ミス無く効率良く仕事ができるように工夫する
仕事ができる人は普段の業務をこなしながら、効率化できるポイントはないか探しています。
また、ミスが頻発している工程があれば、改善策を探し出すでしょう。このように、業務を工夫してより良くするアイデアを提案します。
ポジティブ思考でチャレンジ精神がある
どんなことにもチャレンジできる人は、経験値が上がりやすくなるでしょう。
たとえ失敗してもポジティブに考え、「次はどうしたら成功するか」とトライします。チャレンジをくり返すことで、おのずとキャリアアップに繋がるのです。
ミスやトラブル発生時にすぐに報告・相談ができる
トラブルが起きた際に求められるのは、迅速な対応です。
仕事ができる人は、ミスに気付いた時点で上司に報告できるため、スピード感がある対応が可能になるでしょう。また、問題の原因究明や、解決にも積極的に取り組みます。
いつでも連絡が取れる
仕事ができる人は、すぐにレスポンスが返って来ます。
反対に、連絡がなかなかつかない人は返事を待たせて相手の時間を奪うため、不信感に繋がりかねません。特にクライアントや上司からの連絡には、素早い返信が求められます。
他の人の力を借りて仕事ができる
能力が高い人ほど、実は周りの仲間をよく見ています。
この人はどんなことが得意なのか、どんな能力があるのかを見極めて、上手に仕事を頼めます。
また、自分の限界を客観的に判断できるため、キャパオーバーになる前に周囲に相談できるでしょう。
的確で素早い判断力がある
ビジネスシーンで重要な「素早い判断力」を持ち合わせた人は、頼りになる存在です。
特に、臨機応変な対応が求められる場面では、優先順位を即座に考えて判断を下さなければなりません。
短時間で集中して成果を上げる
仕事ができる人は与えられた時間を効率よく使い、短期間で高い成果を挙げます。
また、最大限のパフォーマンスを発揮するための高い集中力も持ち合わせています。例外がある場合もありますが、残業時間が短い点も仕事ができる人の特徴です。
最新情報を得るためにアンテナを張っている
忙しい日々でも、最新情報を常に検索している人ほど成長します。
リサーチした情報を自分なりに解釈し、アイデアを生み出すでしょう。また、打ち合わせでの雑談など何気ない会話から、情報を得て行動に移すのも得意です。
自分の考えを言葉にして相手に分かりやすく伝えられる
仕事ができる人は、結論ファーストで自分の考えを言葉にできます。
プレゼン能力が問われるビジネスシーンでは、相手に分かりやすく論理的に伝えられなければなりません。アイデア力やスキルだけでなく、伝え方も重要なのです。
プライベートと仕事の切り替えが上手
プライベートが充実していると、休日にリフレッシュができてストレスを溜めずに仕事ができます。
熱心に仕事をするのも大事ですが、身体と心の健康無くしてはじゅうぶんなパフォーマンスを発揮できません。睡眠や食事にも気を付けると良いでしょう。
新卒や若手社員の成長のため、目指す先として掲げられるようなロールモデルを組織の中心に配置することは、チーム編成において非常に大きな効力を発揮します。 しかし、ロールモデルの配置と言っても、どの様なメリットがあるのか、どの様に採用すれば[…]
仕事ができる人が企業に与える影響

仕事ができる人が社内にいると、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここからは、「しごでき」な人が企業にもたらす影響をご紹介します。
自分の役割を認識して期待以上のパフォーマンスをもたらす
有能な人ほど、企業が自分に何を求めているかを深く理解しています。
チームの一員であれば誰のフォローをして、どんな仕事をするべきかが言われなくても分かるでしょう。上司からの指示や、フィードバックにかかる時間が短縮されます。
また、仕事ができる人はどんな仕事も当事者意識を持って行動します。
そのため、期待以上のパフォーマンスを発揮し、チームや企業全体にも貢献するでしょう。言われたことだけをこなす人よりも、さらに大きな成果を挙げられるのです。
他人の能力を分析し適切な役割分担ができる
仕事ができる人は、得意・不得意を見極めるのが得意です。そのため、チームのトップであれば、部下を適材適所に配置でき全体の業務を効率化できます。
また、有能な社員ほど、「仕事はチームプレイ」という意識が強いため、自分一人で抱え込もうとしません。
他の人へ任せるべき仕事と、自分がやるべき仕事を上手に線引きします。
他の人の仕事が多すぎる、または少なすぎることが無いようにバランスを取ってくれるでしょう。
無駄な仕事を見極めて業務の効率化が図れる
業務のなかで面倒だと感じる点があれば、改善して効率化できるかもしれません。改善ポイントを探すのが得意な人がチームにいると、業務の効率化が図れます。
また、仕事ができる人は豊富な知識や情報を持ち合わせているため、効率化するためのアイデアも柔軟に提案してくれるでしょう。
仕事ができる人とできない人の違い
次に、「しごでき」な人とそうでない人の違いを、下記の3点に注目してチェックしましょう。
責任感
仕事ができる人とそうでない人では、仕事に対する責任感が異なります。
責任感があれば、どんな仕事も自分事ととらえて取り組むため、自然とアイデアや工夫ができます。反対に責任感が無いと、自分から行動せず指示待ちになってしまうでしょう。
口癖
仕事ができる人の口癖は「できます」「教えてください」など前向きなものが多い傾向にあります。
それに対して、「でも」「だって」など言い訳が多く、ネガティブな発言が多い人は信頼を失いかねません。
プライドの高さ
仕事ができない人はプライドが高すぎる人が多く、周りの人からのアドバイスを素直に聞けないことがあります。
分からないことを誰かに聞いたり、人に頼ったりする素直さがあると、しごできに近付くでしょう。
仕事が円滑に進められないローパフォーマーな社員に悩む企業は少なくないでしょう。経営者や人事の担当者にとっては悩みの一つといえます。 対応を見誤ってしまうと、組織を窮地に追い込む事態へと発展する場合もあるため、ローパフォーマーへの対応や[…]
仕事ができる人の業務の進め方

仕事ができる人がどのように業務を進めているのが、気になる方も多いのではないでしょうか。ここからは、業務の進め方を例に沿ってご紹介します。
1、ゴールを明確にして無理の無い計画を立てる
まずは、仕事のゴールを明確にします。方向性や期日を確認してやるべきタスクを洗い出して、スケジュールを計画しましょう。
- この時に意識すべきポイントが、アクシデントの可能性です。
予想外のトラブルがあっても対応できるように、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
1日のスケジュールであれば、3時間ごとに15分を目安に空白の時間を作っておくと、予想外の業務に対応しやすくなります。
2、スピーディーに業務へ取り掛かる
仕事の方向性が決まったら、着手できることからすぐにスタートしましょう。仕事ができる人ほどタスクを先送りせず、できることから順に取り掛かります。
時間がかかる業務は、できるだけタスクを細かくするのがおすすめです。
例えば、プレゼン資料を作る場合なら、目次だけ作る、画像だけ探す、文章を作成するなど、工程ごとに切り分けると、取り掛かるハードルを下げられます。
3、疑問があればすぐに確認する
業務を進めていくなかで分からないことが合った場合、仕事ができる人はすぐに質問をします。
疑問をそのままにして業務を進めてしまうと、方向性を間違えて大幅な修正が必要になることも。
時間を無駄にしないためにも、疑問は放置せずにすぐに確認するよう意識しましょう。
仕事ができる人を面接で見極める方法
採用担当者であれば、より有能で仕事ができる人を採用したいところです。最後に、仕事ができる人かどうかを面接で見極めるポイントを解説します。
ハキハキとした挨拶や返事ができているか確認する
まず、面接が始まる前に学生が自分から挨拶をするかチェックすると良いでしょう。
挨拶はどんな業界でもコミュニケーションの基本なので、職種に関わらず確認するのがおすすめです。
また、相手の目を見ているか、名前を呼んで話しかけているかどうかもポイントです。
TPOに合った清潔感がある見た目かどうかチェックする
シワがついたシャツを着てくる人や、ネクタイが正しく結べていない人は身だしなみへの配慮が欠けています。
特に採用面接の場でだらしない印象を付けてしまう人は、仕事ができない傾向にあります。TPOに合った服装や髪型かどうかを確認しましょう。
さらに、見た目だけでなくニオイもチェックすべきポイントです。汗やたばこのニオイは、相手に不快な思いをさせることもあります。
また、鞄や靴などの持ち物を手入れしているかからも、しごできかどうか判断できます。
結論ファーストの受け答えができているか確認する
仕事ができる人は、面接で結論ファーストの受け答えができます。「結論から言うと」が口癖になっている人も多いため、面接でのチェックポイントにすると良いでしょう。
また、意見を簡潔にまとめる際に使う「簡潔に言うと」や「ひとことで言うと」なども、言葉での表現力を判断する基準になります。
面接では、自分が話したいことの核心を分かりやすく伝えられているか、確認してください。

●面接の基本と重要ポイント
ー面接で入社意欲を高める方法や効果的なコミュニケーション術
●具体的な質問例と応用方法
ー候補者の能力やスキルを見極めるための質問設定方法
●オンライン面接の成功ポイント
ーアイスブレイクやリアクションの重要性など、オンライン特有の対策
まとめ
周囲の人から「しごできだね」と褒められる人は、持ち前のポジティブ思考で企業にさまざまな利益をもたらします。
また、結論ファーストで自分の意見をしっかりと伝えられるので、社内・社外を問わず円滑なコミュニケーションが可能です。
そんな、仕事ができる人を見抜けるように、今回紹介したポイントを面接の際にチェックしてみてください。
これまで人材の採用には、学歴や経験などが重視されるケースが少なからずありましたが、企業によっては「頭のよさ」よりも「地頭のよさ」を重視する傾向も多くみられるようになっています。 しかし、実際に「地頭のいい人」を採用したいと思っても、ど[…]