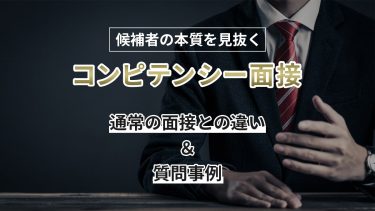多くの業界で人手不足が深刻な問題となっている今、少ない社員で高い売上を目指したいと考える人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
今回は、ほかの社員よりも高い成果を出す「ハイパフォーマー」に着目してみましょう。ハイパフォーマーの定義や行動特性をチェックすると、より良い人材の採用や育成が可能です。
また、ハイパフォーマーの離職を防ぐ具体的な方法もご紹介するので、人事担当者の方は最後までチェックしてください。
– 高パフォーマーを見極めるための評価指標や行動特性が理解できます
– ハイパフォーマーを育成・活用するための実践的な方法が学べます
– 社内での成果を上げる人材の共通点を知りたい方に最適です
– ハイパフォーマーをどう育て、組織で活かすかを具体的に知りたい方に向いています
ハイパフォーマーとは?

まずは、ビジネスシーンでハイパフォーマーがどのような人材を指すのかお伝えします。
そもそもハイパフォーマーとは何か?
ハイパフォーマーとは、組織のなかで高い成果を出す人材のことです。
ハイパフォーマーが在籍すると、期待以上の実績を上げて企業の成長に繋がったり、チームのモチベーションがアップしたりと、さまざまなメリットを得られるでしょう。
ハイパフォーマーの定義
企業のような集団においては「2:6:2の法則」が働きます。
集団では、上位2割がハイパフォーマーと呼ばれる優秀な人材です。続く6割の人材はミドルパフォーマーと呼ばれ、平均的な成果を出します。下位の2割はローパフォーマーと呼ばれ、売上に貢献できない人材です。
ハイパフォーマーを採用・育成してハイパフォーマーの比率を増やすことが、自社の生産性の向上に繋がります。
なぜ今ハイパフォーマーが注目されるのか
少子高齢化が進む現代では、多くの業界で人手不足が深刻な問題になっています。
人手不足のなかで成果を出し続けるには、少ない人材で高パフォーマンスを発揮することに重点を置かなければいけません。
そのため、1人でも高い成果を出し、周りにも良い影響を与えるハイパフォーマーは、注目を集めているのです。
ハイパフォーマーの特徴
企業によって求められるスキルや素質、経験は異なりますが、共通する特徴があります。
成果を出すハイパフォーマーの行動特性とは
まずは、ハイパフォーマーに共通する行動上の特徴を見てみましょう。
コミュニケーション能力が高い
円滑に業務を進めるには、社内・社外を問わず高いコミュニケーション能力が欠かせません。
ハイパフォーマーは、とりわけ高いコミュニケーションスキルを持っているのが特徴です。各部署からの信頼も厚く、連携して業務を遂行してくれるでしょう。
結果を残すために努力を惜しまない
ハイパフォーマーは、上司や企業が求める目標以上の実績を達成します。予想外のアクシデントが発生しても、その状況における最善策を考えあきらめずに努力して成果を出してくれるでしょう。
目標達成のために何をすべきか、自身に何が求められているかを分析し、着実に努力を積み重ねる人が、ハイパフォーマーと呼ばれるのです。
すぐに行動できる
すぐに行動に移せる点も、ハイパフォーマーの大きな特徴です。上司からの指示や取引先からの依頼を受けたら、その場で迅速に自分がなすべきことを考え、すぐに行動に移します。
迅速な行動力は、ハイパフォーマーを見極める上で重要なポイントのひとつといえます。
ハイパフォーマーに多い性格や思考パターン
次に、ハイパフォーマーに共通する性格や考え方を見てみましょう。
ポジティブ思考
ハイパフォーマーと呼ばれる人は、どのような状況でも常にポジティブに考えられるという共通点があります。業務を行うなかで困難な課題に直面しても、持ち前のポジティブ思考を発揮し、最善を尽くします。
また、ハイパフォーマーのポジティブ思考は周囲の人にも伝わり、チームにもいい影響を与えるでしょう。
自分に厳しい
仕事で成果を出すことに注力するハイパフォーマーは、自己管理能力に優れた人といえます。寝不足や体調不良に陥らないよう徹底した自己管理を行い、仕事中は最大限のパフォーマンスを発揮できるようオン・オフを切り替えます。
チャレンジ精神がある
ハイパフォーマーはチャレンジ精神があり、失敗を恐れずにさまざまなことに取り組むのが特徴です。
また、常に自己研鑽を積み、業務に必要な知識やスキルを磨いています。たとえ失敗したとしても、経験を次の機会に繋げてくれるでしょう。
一般社員との違いを比較表で確認しよう
ハイパフォーマーと一般社員との違いを表にまとめました。
| ハイパフォーマー | 一般社員 | |
| コミュニケーション | 必要な範囲にとどまらず、主体的に周囲を巻き込みながら情報共有・関係構築を行う | 必要な範囲でのやりとりがメイン |
| 成果・売上 | 期待以上の成果を出す | 期待通り、もしくは達成できないこともある |
| 考え方 | ポジティブで自己成長にも積極的 | ネガティブ思考になりがち、現状維持を好む傾向がある |
| チャレンジ精神 | 前向きで失敗を恐れずに挑戦できる | リスクを避け達成可能な範囲の目標にとどまる |
採用や評価の場では、上記の比較表を参考にハイパフォーマーかどうか判断する指標として活用してみてください。
ローパフォーマーとの違い|明確な判断基準
ここで、ハイパフォーマー・ローパフォーマーの具体的な違いを比較してみましょう。
成果・姿勢・影響力の違いを比較する
高い成果を出すハイパフォーマーに対して、任務遂行能力が乏しい人材をローパフォーマーといいます。ローパフォーマーは求められている仕事をこなせず、成果を出せません。
また、意欲的に仕事に向き合わない点もローパフォーマーの特徴で、誰かに指示されないと行動できないのも特徴です。ハイパフォーマー思考の人が自主的に動くのに対して、正反対の姿勢だといえます。
そのため、業務に意欲的ではないローパフォーマーに対して周囲の人は不満がたまり、モチベーションが下がるという悪影響を及ぼします。
マネジメント視点で見るべき評価ポイント
人事は、社員の評価が仕事の質や量に見合っているかを確認しましょう。成果を出さないローパフォーマーが他の社員よりも給与が多い状況では、不満に繋がります。
成果を出せない理由がスキル不足であれば研修の機会を設ける、目標設定を見直すなど、ローパフォーマーのメンタルに配慮しつつスキルアップできる機会を増やすことが必要です。
また、ハイパフォーマーの評価においては、実績や努力に基づいた公正な判断が必要です。年齢や入社歴にとらわれず、昇給や昇進を検討しましょう。
仕事が円滑に進められないローパフォーマーな社員に悩む企業は少なくないでしょう。経営者や人事の担当者にとっては悩みの一つといえます。 対応を見誤ってしまうと、組織を窮地に追い込む事態へと発展する場合もあるため、ローパフォーマーへの対応や[…]
ハイパフォーマーの見極め方

ここからは、社員のなかからハイパフォーマーを見極める方法と評価指標について解説します。
現場で使えるチェックリスト
ビジネスの現場でハイパフォーマーかどうかを見極める場合は、以下のチェックリストに当てはまるかどうかで判断できます。
- 常に新しいことに挑戦する
- 目標に向かって計画的に業務を進めている
- 楽しく仕事をしている
- 会社の理念やビジョンを理解している
- スキルアップに力を入れている
- 問題解決のために自主的に動ける
- 周囲と円滑にコミュニケーションを取れる
- 状況に合わせて判断できる
- 仕事に対して熱量が高い
- 失敗から学んでいる
- 失敗した人に寄り添いフォローできる
- 健康管理ができる
上記のポイントを確認して、ハイパフォーマーを見つけましょう。
人事評価面談で活用できる項目例
ハイパフォーマーを公正に評価しないと会社に対して不信感を抱かせる原因になり、最終的に離職に繋がりかねません。
人事評価面談では、社員に以下の質問をすることで、個人の成長、ひいてはチーム全体の能力向上に繋がるでしょう。
毎日楽しく仕事をしていますか?
仕事が楽しいと感じる人は、自分の強みを活かせています。その結果、自然と業績が上がり評価もついてくるでしょう。反対に楽しいと感じられない人は、なかなか実績に繋がりません。
上司からどのような指摘を受けて、どう改善しましたか?
ハイパフォーマーは向上心が高く、さらなる成長のためにどうすれば良いかを常に考えています。そのため、上司からの指摘を真摯に受け止めて自分の行動や考え方を改善することが多い傾向にあります。
上司からの指摘を素直に受け入れているかどうかは、人事評価面接での判断ポイントです。
健康のためにどんなことをしていますか?
ハイパフォーマーは、仕事でパフォーマンスを発揮するために健康管理を欠かしません。そのため、健康のためにしていることはあるかという問いに、具体的に回答できるでしょう。
行動観察と数値評価をどう組み合わせるか
社員を適切に評価する際は、行動観察と数値評価を組み合わせる必要があります。
行動観察とは、日々の業務に取り組む姿勢や言動、思考などを観察することを指します。デメリットとして、主観的な評価が入りやすいのが特徴です。
一方、数値評価は業務の達成率などの実績を数値化して業過する客観的な指標です。ただし、数字に現れない行動特性が評価されないという懸念点があります。
ハイパフォーマーを選定し自社の評価指標を作成するには、行動特性と数値評価の片方では足りません。どちらも組み合わせた上でハイパフォーマーを評価するのが重要なのです。
面接で応募者を見極めたい!
面接の基本と重要ポイント、具体的な質問例と応用方法、アイスブレイクやリアクションなど、オンライン特有の対策を解説
ハイパフォーマーの育成・活用法
ハイパフォーマーとは、言い換えると「仕事ができる人」のことです。企業には、ハイパフォーマーを育成し、能力を最大限発揮できる環境作りが求められます。
ここでは、ハイパフォーマーを育成し、適切に活用する方法を見ていきましょう。
モチベーションを高める関わり方のコツ
他の社員に比べて仕事ができるハイパフォーマーには、業務が集中するリスクが伴います。
日々の業務においてストレスや負担が蓄積していないか、業務体制をチェックしましょう。また、ハイパフォーマーとローパフォーマーとの間で評価や給与に差がない場合は、モチベーションを著しく低下させる要因になります。
評価制度を適切に整えて、ハイパフォーマーが無理なく業務をこなし、正当に評価される環境を作りましょう。
役割や権限を与えて成長を促す
ハイパフォーマーの能力を活かすには、ある程度権限を与えて自由に仕事をさせてみるのも有効です。
どれだけ優秀なハイパフォーマーでも、適切な権限がなければその高い能力を十分に発揮できない可能性があるからです。
役割や権限を積極的に与え、彼らが存分に能力を発揮できる機会を提供しましょう。
組織に与える好影響と配置の考え方
仕事に対するモチベーションが高いハイパフォーマーは、在籍するチームのメンバーにも良い刺激をもたらします。自分のスキルや経験、知識を共有するため、チーム全体の能力アップも図れるでしょう。
また、他の社員はハイパフォーマーの考え方を学ぶことで、新たなハイパフォーマーが生まれるきっかけにもなります。
意識改革を進めたいチームや、さらなる成長が期待される部署にハイパフォーマーを戦略的に配置することで、会社全体の成長に大きく貢献します。
自社にハイパフォーマーを増やすための改善チェックリスト
ハイパフォーマーを増やすことは、少ない社員で効率良く成果を出すために不可欠です。そこで、以下のチェックリストを確認してハイパフォーマーが増えやすい環境かどうか、チェックしましょう。
採用・育成・環境の観点でのチェック項目
ハイパフォーマーを増やすには、主に採用と育成、そして環境という観点からチェックする必要があります。
| 採用 | ・ハイパフォーマーの定義を明確にして採用担当者に周知する
・面接で確認すべき具体的な項目を設定する |
| 育成 | ・講演会など聞いて終わりになる一方的な研修ではなく、ワークショップやディスカッションの場を定期的に設定する
・学んだスキルを活かせる実践の場を用意する |
| 環境 | ・上司は1on1などで社員の様子を把握して、適切なフィードバックを行う
・個々にあった業務量や裁量を設定する |
社員全員をハイパフォーマーにすることは困難ですが、上記のポイントを実践することで、組織全体の能力底上げに繋がるでしょう。
取り組みの優先順位をどう決めるか
ハイパフォーマーを増やす取り組みは、まずハイパフォーマーの選定から始めます。
次に、複数のハイパフォーマーを分析して、共通点を調査してください。分析結果が出たら、自社においてのハイパフォーマーの定義を定めましょう。
ハイパフォーマーの定義を明確にしたら、自社の社員に求める資質を定めます。その後、一般社員とハイパフォーマーとの違いを埋めるため研修体制を整えます。
また、研修後にはチームのメンバーや上司がフォローアップし、学習内容が定着しているか確認しましょう。
ハイパフォーマーに関するよくある疑問(FAQ)
最後に、ハイパフォーマーについてよくある質問をまとめました。
コンピテンシーとの関係性は?
コンピテンシーとは行動特性のことで、ハイパフォーマー同士は行動や思考が似てくることが知られています。ハイパフォーマーのコンピテンシーを分析すると、採用や人材育成に活用できます。
採用面接のスキルや能力をはかる面接手法であるコンピテンシー面接をご存知でしょうか。今回は、コンピテンシー面接と通常の面接の違いや、効果的な取り入れ方についてご紹介します。 コンピテンシー面接とは? コンピテンシー(competency)[…]
ハイパフォーマーが退職しやすいのはなぜ?
ハイパフォーマーは、その高い能力ゆえに退職するリスクも高い存在です。周囲の社員に比べて抱える業務が多くなりがちにもかかわらず、正当に評価されないという場合には不満が募り、会社に対する不信感を招きます。
したがって、ハイパフォーマーがのびのびと仕事ができる環境を整え、かつ適切な評価制度を設けるのが、離職を防ぐために極めて重要なのです。
まとめ
ハイパフォーマーは、集団の上位2割が該当する優れた成果を出す人材のことをいいます。ハイパフォーマーを活かすことが中小企業の成長に直結します。
ポジティブ思考で向上心が高いハイパフォーマーは、売上に貢献するだけでなく、周りの社員にも良い影響をもたらします。
成長を期待するチームや、意識改革をしたい部署に戦略的に配置すると良いでしょう。ハイパフォーマーを見つけて採用や人材育成に活かすことで、企業の成長に繋げてください。
「しごでき」という言葉をご存知でしょうか。仕事ができる人のことを省略した言葉で、若者の間で流行しています。 今回の記事では、そんな「しごでき」人材の特徴に迫ってみましょう。 また、仕事ができる人の業務の進め方や、そうでない人との[…]