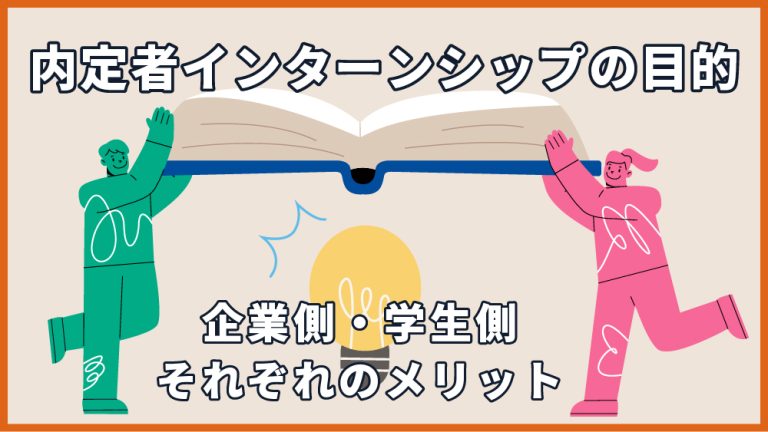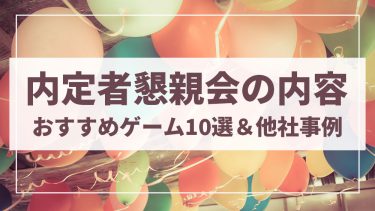内定者インターンシップは、本選考で内定を受けた学生を対象に行われる就業体験です。
企業は内定者インターンシップを行うことで、企業文化や仕事内容、職場の雰囲気などを理解してもらうことができ、内定者の不安や疑問を解消することにも繋がります。
この記事では、内定者インターンシップの目的に加え、メリットや取り入れる際の注意点などを紹介します。
後半では、内定者インターンシップ以外の内定者向けサポートについても紹介するので、併せて参考にしてみてください。
内定者インターンシップとは

「内定者インターンシップ」とは、企業が内定を出した学生を対象に実施する実務経験の機会です。
正式な入社手続きの前に、内定者が企業の文化や仕事内容、職場の雰囲気などを体験して知ることを目的に行われています。
内定者は実際の業務に関わることで、入社後に自身が働く姿をイメージできるので、入社に対する疑問や不安を解消するのに効果的な制度といえるでしょう。
内定者インターンシップを実施する目的
内定者インターンシップの効果をより明確にするためには、実施目的を具体的なデータや企業事例と併せて設定することが効果的です。
たとえば、「内定辞退率が〇%減少」「早期離職率が〇%改善」といった数値が示されていれば、導入意義がわかりやすくなります。
さらに、業務適応に役立てるためには、定期的なフィードバック面談や評価システムを取り入れ、効果を確認しながら運用するのが理想です。
ここでは、内定者インターンシップを実施する主な目的を3つ紹介していきます。
入社後の業務にスムーズに慣れてもらうため
入社前に業務の一部を体験することで、入社後の業務をスムーズに行えるようにすることが目的の一つです。
内定者は事前に企業の文化や雰囲気、業務内容に触れられるため、入社後の自身の働きをイメージしつつ、心の準備をする期間にもなるでしょう。
また、内定者インターンシップに参加した学生や求職者は、入社前に上司や同僚と関わることができます。
そのため、組織が内定者に期待する役割や業務の進め方などを理解してもらえる機会にもなるでしょう。
内定者の得意分野や適性を把握するため
内定者インターンシップは、企業にとって内定者の得意分野や適性を把握する場でもあります。
内定者はインターンシップ期間中、実際の業務に関わります。
企業側は取り組む姿を見て、専門的なスキルに加え、コミュニケーション能力や問題解決能力など、内定者の適性や能力を総合的に見ることができるのです。
内定者インターンシップは、業務体験の機会を内定者に与えるだけでなく、企業側が内定者について深く理解するための手段ともいえるでしょう。
内定者の不安を取り除き、安心してもらうため
内定者インターンシップは、内定者の不安を取り除き、安心してもらう目的もあります。
内定者は、「この企業にうまくなじめるのか」「期待に応えられる働きができるのか」など、不安を抱えてしまうケースも少なくありません。
職業経験のない学生の場合、なおさら不安になる場合もあるでしょう。
そのため、内定者インターンシップの実施は、内定者の不安を解消し、内定辞退を防ぐことにもつながります。
効果的なインターンシップを行うためのポイント
効果的な内定者インターンシップを実施するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
特にリソースが限られる中小企業では、短期間のインターンシップやオンライン形式で行うと効率的です。オンラインであれば交通費や会場準備が不要となり、社員の負担も軽減されます。
また、「OJT(実務研修)」を中心に、学生が補助業務を通じて企業の流れを体験できる内容にすると良いでしょう。
さらに、テンプレート化した評価シートやフィードバックシステムを活用することで、少人数でも効率的に運営できます。
ここでは、内定者インターンシップを効果的なものにするため、押さえたいポイントを紹介します。
導入している企業の具体例や統計を参考にする
内定者インターンシップの効果を明確にするため、導入している企業の具体例や統計を参考にするのが効果的です。
例えば、インターンシップを実施した企業で「内定辞退率が〇%減少」「早期離職率が〇%改善」などのデータを示すと、導入意義がわかりやすくなります。
実際に担当する仕事を経験してもらう
内定者インターンシップ参加者には、「この会社で期待に応えられる仕事をしたい」と、前向きな気持ちを持ってもらうことが大切です。
そのためには、まず内定者が体験する業務は、入社後に担当する実際の業務に近いほうが良く、達成感を感じやすい短期プロジェクトを用意すると効果的です。
簡単なデータ入力や雑務では、内定者が実際に働くイメージを持つことができず、入社後のミスマッチに繋がる危険性もあります。
例えば、2~3日で完結するマーケティングリサーチやデータ分析などのタスクを任せ、成果をチームで共有する場を設けると良いでしょう。
入社後のギャップは、実際に働く現場のリアルな情報を伝えることで、軽減できるともいえます。
社員と交流して会社の雰囲気を知ってもらう
内定者インターンシップでは、すでに企業で働いている社員との交流の場を設けて、内定者に会社の雰囲気を知ってもらうことも大切です。
内定者が抱える不安の中には、入社後の人間関係も含まれます。
既存社員と交流できる企画を実施することで、内定者の不安を解消することができるでしょう。
内定者が成長を実感できるフィードバックを提供する
内定者インターンシップでは、内定者が成長を実感できるフィードバック体制を整えることが重要です。
インターン期間中に社員とのQ&Aセッションを設け、不安を解消するとともに、体験後にはフィードバックシートで振り返りを行います。
成長点を確認することで、参加者の自信や意欲が高まり、入社後の満足度向上にもつながります。
内定者インターンシップのメリットとデメリット

内定者インターンシップのメリット・デメリットは、企業・内定者双方の視点で確認しましょう。リスク軽減には、事前に明確な目標設定とフィードバック体制が有効です。
また、学生の相談窓口を設けて密なコミュニケーションを確保し、終了後にはアンケートで満足度を確認することで、実施効果を把握し改善に役立てましょう。
企業側のメリット:内定辞退率の低下
内定者インターンシップを導入することで、企業イメージのギャップの差を減らすことができます。
内定者の「思っていたのと違うかも」という入社への不安を軽減できれば、内定辞退率の低下に貢献できるでしょう。
また、企業のイメージ像が崩れないということは、内定辞退だけでなく入社後の早期退職を防ぐことにも繋がります。
企業側のデメリット:準備に時間とコストがかかる
内定者インターンシップ導入のデメリットは、準備に時間とコストがかかる点が挙げられます。
内定者インターンシップの実施期間はさまざまで、数日間で終了するものもあれば、長期にわたるケースもあります。
特に内定者インターンシップを運営するにあたり、発生するコストの中でも大きい割合を占めるのが人的コストです。
新卒採用担当者に加え、内定者フォロー担当や内定者インターンシップ担当など、余裕を持って担当社員を配置できれば問題ありません。
しかし、実際は1人の担当者が、全てを管理する企業も少なくないでしょう。運営体制を整えるためには、時間やコストがかかることを意識する必要があります。
内定者にとってのメリット:職場に慣れやすくなる
内定者インターンシップは、内定者にとってもメリットがあります。大きなメリットは、職場に慣れやすくなる点でしょう。
内定者は「少しでも早く職場環境に慣れたい・仕事を覚えたい」と考えるため、入社前に実際の業務を経験することで不安が安心へと変わります。
また、これから一緒に働く現場の社員と関わることが、業務だけでなくスムーズな人間関係を築くことにも繋がるでしょう。
内定者にとってのデメリット:学業との両立が難しい場合も
内定者のデメリットは、学業との両立が難しくなる場合がある点です。
学生の場合、内定が決まったら終わりというわけではありません。卒業までに論文や研究、実験などさまざまな学業が残っています。
企業としては、こういった学生側の配慮も考えたうえで、運営していく必要があるでしょう。
内定者インターンシップ企画立案のコツ
内定者インターンシップを実践するにあたり、企業としては参加者の満足度を高めたいところでしょう。
ここでは、内定者インターンシップ企画立案のコツを3つ紹介します。
学生目線で、魅力的かつわかりやすい内容にする
内定者インターンシップの企画立案の際は、学生目線で行うことを心がけましょう。
内定が決まってから入社するまでの間、学生は何かと不安を抱えている場合がほとんどです。
そのため、学生目線に立ち、不安が解消できるような魅力的でわかりやすい内容の企画を用意しましょう。
実際の業務に触れられる体験を盛り込む
実際の業務に触れられる体験を盛り込むのも、内定者インターンシップ企画立案のコツです。
企業によっては、誰でもできるような簡単な業務や雑務を任せるケースもあります。
しかし、それでは内定者の満足度を上げることはできないでしょう。
誰でも可能な業務は特別感がなく、「自分でなくてもいいのでは?」と思わせてしまう要因になります。
フィードバックや振り返りの時間を設ける
内定者インターンシップを実施する場合、フィードバックや振り返りの時間を設けることも忘れてはいけません。
フィードバックを通じて、内定者自身が成長や強み、改善すべき点を理解して実感することが、内定者インターンシップ成功のキーポイントともいえます。
「内定者懇親会」を検討実施する企業様は多いと思いますが、毎年気になるのは、他社はどんな感じで開催しているかですよね! そこで本日のテーマは、新卒採用の『内定者懇親会、他社事例と学生の声』! 人事担当者 他社[…]
内定者インターンシップを実施する際の注意点

ここからは、内定者インターンシップを実践する際の注意点について解説していきます。
報酬や条件はきちんと契約書で交わす
内定者インターンシップは契約書の作成義務はありません。
しかし、内定者インターンシップを実施する中でのトラブル回避のために、報酬や労働の条件などは必ず契約書で交わすことが重要です。
また、労働に関する法規制遵守確保の観点からも契約書は非常に大切です。
「法的な要件を満たす企業」というのは、内定者が抱える不安を払拭することにも繋がるでしょう。
学業への影響がないよう配慮する
内定者インターンシップの実施は、学業への影響がないよう配慮することも必要です。内定が決まっていたとしても、卒業まで内定者の本業は学生です。
どんなに魅力的な内定者インターンシップを立案しても、学生自身が学業とのバランスが難しくなり、卒業に必要な単位を取得できなければ意味がありません。
そのため、企業側は内定者のスケジュールなどを考慮して実施することが望ましいでしょう。
参加できない内定者へのフォローを忘れない
内定者インターンシップを実施する際、忘れてはいけないのが参加できない学生へのフォローです。
内定が決まった全員が、内定者インターンシップに参加するわけではありません。住む場所が遠方の方や学業の都合で参加できない方もいます。
参加した学生とそうでない学生との間に差が生じないようにするためにも、オンライン形式にしたり、定期的に面談を行ったり、フォロー体制を整える対策もしておきましょう。
内定者インターンシップ以外の内定者向けサポート
内定者インターンシップは、採用戦略の中でも有効な方法の一つです。
企業にとって重要な取り組みではありますが、内定者インターンシップで全ての不安が解消するわけではないでしょう。
そこで、内定者インターンシップ以外の内定者向けサポートを準備しておくことが大切です。
懇親会や社内イベントに招待する
入社前に内定者を親睦会や社内イベントへ招待するのは、内定者フォローの有効な方法といえます。
親睦会や社内イベントなどの場では、内定者同士や既存社員と交流でき、社内インターンシップとは違った雰囲気を感じられる機会となるでしょう。
オンライン研修やeラーニングで知識を補強する
オンライン研修やeラーニングで、知識を補強する機会を設けるのもおすすめの方法です。
このようなサポート体制は、授業や論文など学業との両立で忙しい学生にとって、入社前の期間を有効に活用できる嬉しいサポートの一つです。
定期的な面談を実施し、個別の不安や疑問に対応する
定期的な面談の実施は、個別の不安や疑問に対応するために有益な方法といえます。
面談で直接、内定者の不安や期待に耳を傾けることで、内定者が抱える不安や疑問を解消し、さらにはモチベーションを高めるのに役立つでしょう。
個別にメールや電話連絡をするのも内定者フォローとして有効です。また、内定者がよく活用しているSNSなどの連絡手段に注目してみるのも良いでしょう。
応募者(学生)にとっては、内定通知が届いた時点で就活のゴールといえるでしょうが、企業側としては、内定通知後が勝負となります。 内定を出した後に内定者に向けて行う内定者面談は、内定者が実際に入社をしてくれるかどうかを確認、促すものでもあ[…]
まとめ
内定者インターンシップは、企業の採用戦略の中でも大切なステップの一つです。
内定者は実際の業務を経験することで、入社後の働く姿をイメージでき、入社に対する不安などを解消できます。内定辞退や入社後の早期退職を防ぐのにも有効な取り組みといえます。
企業だけでなく内定者にとってもメリットの多い内定者インターンシップの導入を検討してみてはいかがでしょう。
「インターンシップを実施したいけれど、時間も人手も足りない」「効果的なプログラムをどう設計すればいいかわからない」「優秀な学生を集めたいけど方法がわからない」こんな悩みを抱えていませんか? インターンシップは、学生に企業を知ってもらい[…]