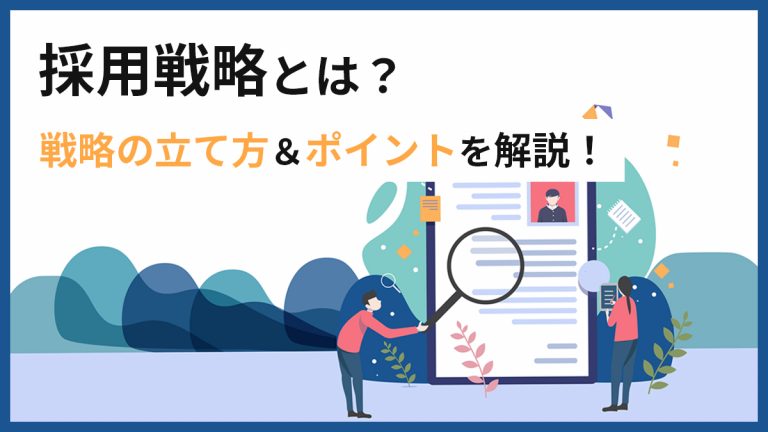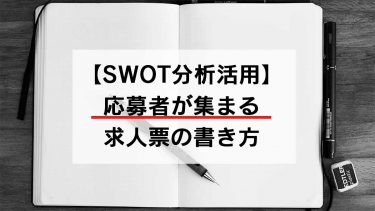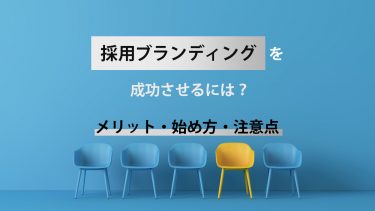企業によって求める人材は変わってきます。時間とコストがかかる採用活動を、効率よく行うために重要なのが採用戦略です。
採用戦略の立て方は企業ごとに異なりますが、しっかり戦略を立てることで、応募が来ない状況や内定辞退・早期離職を予防することができます。
今回は、「採用戦略の立て方や手順、成功した企業の事例など」を紹介します。
採用戦略とは

採用戦略とは、企業が求める人材確保のために行う戦略のことです。企業が目標を達成するためには、人材の確保が欠かせません。
そのため、採用戦略は経営戦略の中でも特に重要な項目です。
採用学からみる「採用戦略」
他の企業ではどのような戦略を取っているのでしょうか。最近では、採用を学問化した「採用学」という学問を確立化する動きもあります。
まず、採用学では採用活動を3段階で捉えています。
2つ目が「選抜(選択)」。企業による求職者の選抜と求職者による企業の選択の段階です。
3つ目が「定着(社会化)」。入社への内諾を得て、企業に入ってなじんで活躍してもらうという段階です。
この3段階において、それぞれの問題点をデータを取りながら検証していくことが「採用学」です。
採用戦略を立てる目的
採用戦略は、事業の計画を進めるためにどのような採用活動をすれば良いのかを設定し、そのために必要な人材を確実に採用することを目的としています。
前述した採用学の観点から採用戦略を考えた場合にポイントとなるのは、他社と違うことをすることです。それはつまり、自社がどのような層の学生を狙うかを明確化するということです。
採用戦略を立てる目的は、まさにそこにあります。
誰もが知る大手企業であれば、旧帝大クラス・早慶上クラスをターゲットにすることも可能です。しかし、一般的な企業では、採用にかける予算が限られていて、大々的なプロモーションを打てない点であったり、学生からしたらマイナスの要因を抱えているため、このクラスの学生をターゲットにすることはなかなかの難題かもしれません。
戦略をしっかり立案することで、応募が来ないケースや内定を辞退するケースを防ぐことが可能です。母集団形成に苦戦している企業こそ、採用ターゲットをはっきりと明確化しておくことが重要になってきます。
採用戦略の重要項目
採用戦略立案の際に重要な項目は、3つあります。
自社の強みを把握する
採用を戦略的に行うためには、まず採用担当者自身が自社の強みについての理解を深めることが必要です。
企業理念や経営理念を把握し、会社の目指す方向や考え方などを再確認しましょう。こうすることで求職者の共感を後押しすることができます。
求める人材を明確にする
自社の強みを確認したら、求める人材を明確にしていきましょう。
年齢や性別・性格など細かく設定することで、採用に関わる担当者全員が同じ認識を持ち、採用計画を立てられるようになります。
自社の立ち位置を確認
採用戦略を立てるときは、他社と比較することにより、自社の立ち位置を確認することができます。
比較するのは、同業の企業、求めるターゲット層が重なる企業などになりますが、それらの企業と自社との差別化ポイントを整理しておきましょう。
採用戦略の立て方・手順
採用戦略の立てる際は、4つの手順があります。順番に説明していきます。

採用すべきターゲットを決める
採用戦略では、長期的な視点でターゲットを定めていくことが重要です。今後の経営目標を確認し、それらを実現するために必要なスキルは何かを考えることで、採用すべきターゲットが定まるでしょう。
採用目標やスケジュールの設定
ターゲットを設定したら、目標とする採用人数やスケジュール、採用担当者などの採用計画を具体的に決めていきます。
採用目標を決める際は、経営側にヒアリングを行い、採用人数の設定をすると良いでしょう。また、スケジュールが短期的か、中長期的かにより採用戦略も変わります。
求人方法の選定
求人方法は企業のホームページや企業が集まる合同セミナーなど、さまざまな方法があります。どのような求人方法が自社の求める人材を集めることができるかを考え、効果的なものを選ぶようにしましょう。
入社後のフォロー体制を整える
必要な人材を確保しても、早期離職をする人もいるでしょう。そういった事態を防ぐためにも、事前に入社後のフォロー体制を確立しておくことが重要です。
基本的な採用戦略のフレームワーク
フレームワークを活用することで、情報を整理し、自社の目的にあった採用戦略を効率よく立てることが可能です。自社や競合の企業の分析に使用可能な フレームワークを紹介します。
3C分析
3C分析は、「自社」「競合」「求職者」という3つの視点から分析していくフレームワークです。
求職者の立場になり、求められるニーズや価値観を分析していきます。また、競合となる他社と比べ、どのようなマイナスポイントがあるのかをできるだけ客観的に分析することで、自社がどのように対応していくべきなのかがわかるようになります。
SWOT分析
SWOT分析は、要因を「強み」「弱み」「機会」「脅威」という4つのカテゴリーで分析するフレームワークです。
採用戦略を立てる際、自社の強みを理解するのも大切ですが、弱みも把握するといいでしょう。また、機会の生かし方やリスク管理として脅威の把握も必要です。ターゲットとなる求職者を対象にすることで、どのようにアピールするか考える際に役立ちます。
少子高齢化や人口減少などによって人材獲得競争が激化している昨今、単純に求人媒体を出すだけでは人材の確保が難しい世の中になりました。 欲しい人材を効率的に採用するには、自社の現状を把握し会社の成長に繋げることが大切です。 SWOT[…]
採用戦略を立てるときのポイント

求める人材を獲得するためには、細かい採用戦略を立てることが必要です。ここでは、戦略を立てるときのポイントを2つ紹介します。
求職者の目線で自社の魅力を考える
自社のアピールポイントを知ることは採用活動をする際に重要です。
給料や雇用条件はもちろんですが、職場の雰囲気ややりがいを知りたい求人者もいるでしょう。さまざまなケースを想定し、求人者視点に立ったときに何が自社の魅力と映るのかを考えましょう。
面接の質の向上
面接の際、面接官は求職者が求める情報に答えつつ、性格や能力を見極める力が必要です。
採用活動にも大きく関わってくるため、面接官の質を上げるための育成計画も立てるといいでしょう。
新卒と中途による採用戦略の考え方の違い
新卒と中途による違いは、「採用時期」「採用基準」の2つがあります。これらの違いを考え、採用戦略を立てていくことが大切です。新卒と中途に分け、紹介していきます。
新卒採用の場合
新卒採用の場合、学生の卒業時期に合わせ、採用計画を立てられることが特徴です。
同じタイミングで多くの学生を選考するため、まとまった人数を採用することができます。潜在能力や人柄の部分に焦点を合わせた選考が多くなるので、入社後の育成計画を事前に立てておくといいでしょう。
中途採用の場合
中途採用の場合、求職者ごとに転職活動の時期は異なります。
企業が必要になったタイミングで採用活動をスタートするため、求めている人材からの応募があれば、短期間で進めることも可能です。
短期的な成長が見込める中途採用は、特定の業務に関する知識やスキルを要件として設定することで、求める人材を確保できる可能性があります。採用を成功させるためにも、応募者の業務経験を細かくヒアリングする計画を立てておくといいでしょう。
採用戦略の例
採用戦略の事例を紹介します。
株式会社オプト

オプトは、デジタルマーケティング・インターネット広告代理サービスなどを提供する会社です。
エンジニア採用のために、ブログやイベントでの企業の情報発信から始めています。面接にエンジニアに行ってもらうことで、働くイメージを高められるよう工夫をし、内定承諾率を大幅に向上していきました。結果、1年でエンジニア組織が50人に達しています。
株式会社TBM

株式会社TBMは、石灰石を原料にプラスチックや紙の代替となる素材「LIMEX」を生産する会社です。
採用戦略としては、自社にあった求人広告の利用や各学生にリクルーターを付け、魅力づけやフォローを行いました。結果としては、短期間で11名の新卒採用に成功しました。内定承諾率はなんと9割以上とかなり高い数値をたたき出してます。
面白法人カヤック

デジタルコンテンツを制作する面白法人カヤックでは、さまざまな採用手法を取り入れ、面白法人カヤックならではの採用活動を実施しています。
ゲーム好きの人に対して評価する「いちゲー採用」やエントリーシート不要でWEB上の活動のみを評価する「ワンクリック採用」、4月1日限定に実施されるエイプリル採用などが挙げられます。
ユニークな採用手法を取り入れることで、より会社に合った人材を採用することに成功しました。
見直した方がいい採用戦略の例
採用戦略がしっかり立てられていないと、結果的に採用した人材が離職してしまうケースも出てきます。 見直すべき採用戦略の例を紹介します。
入社後に企業と採用者の認識のズレが起きてしまった例
【例1】
採用戦略を明確に立て、面接のときにズレをなくすことが大切です。求める人材に合わせて伝えられるように考えましょう。
入社後のフォロー体制ができていなかった例
【例2】
そのため採用者は孤立し、成果もあげることができず、その後退職してしまった。
即戦力となる人材が採用できても、その後適宜フォローを行うことが大切です。
採用戦略の立案が進まない企業の特徴
採用戦略の立案が進まない企業の特徴として、前例の振り返りが活かせていない場合があります。まずは今までの採用計画がどのような結果なのかを振り返りましょう。
採用戦略を生かすためのおすすめサービス
採用戦略を効率よく行うために、便利なサービスがあります。このようなサービスを利用することで、求めている優秀な人材を確保することが可能です。ここでは3つ紹介していきます。
採用代行サービス
採用代行サービスとは、人材採用の業務の一部、もしくは全般を専門会社に委託することです。
採用業務は膨大であり、多くの手間と時間がかかります。本来の業務に支障が出てきてしまう状況を防ぐために、採用代行サービスが活用されています。
採用代行(RPO)の料金比較15社!採用アウトソーシング会社の特徴まとめ
人材紹介サービス
人材紹介サービスとは、企業と求職者の仲介を行うサービスのことです。
企業側は求める人材を伝えることで、条件にあった求職者を推薦してくれます。面接日程の調節や、企業・職種の魅力を伝えてもらうこともできるため、企業側は少ない工程で採用活動を行うことが可能です。
AI採用サービス
AI採用サービスとは、人工知能であるAIを活用し、採用活動を行うことです。
過去のデータを事前に判断基準が一貫しているA Iに学習させることにより、公平に選考ができます。また、書類選考に費やす時間を減らす点がメリットです。
まとめ
今回は、採用戦略についてお伝えしました。企業によって採用に関する悩みは異なります。
企業の成長のために少しでも悩みを解決したい方は、紹介した採用戦略の手順やポイントなどを参考に、取り入れてみてください。
「求人サイトを利用して採用活動を行っているのに、なかなか母集団形成がうまくいかない!」とお悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。 応募数を集めるためには、会社を多くの人に知ってもらう必要があり、一般的に認知されていない企業ほ[…]